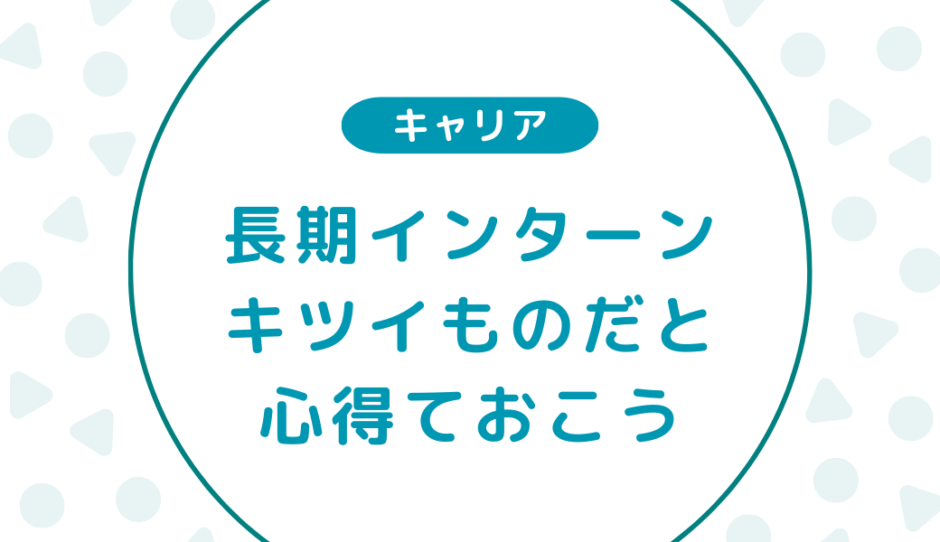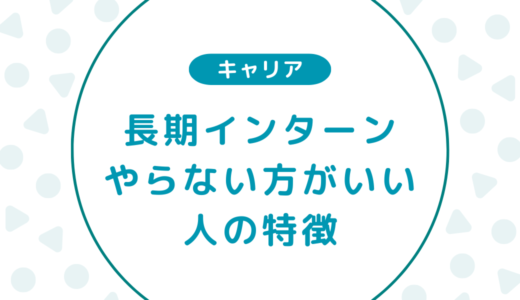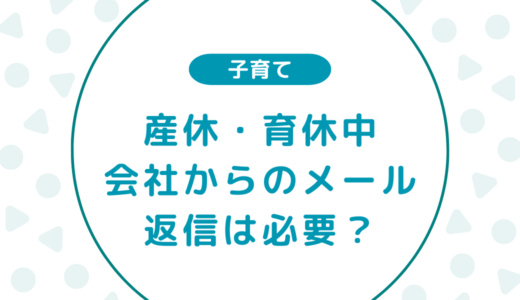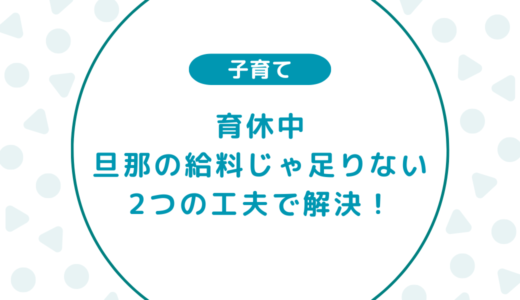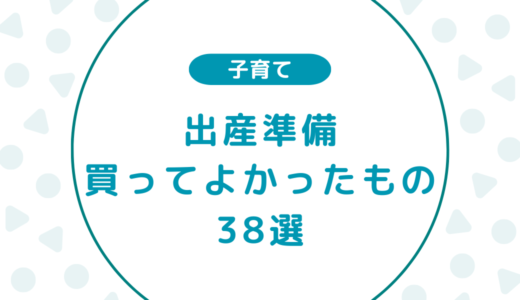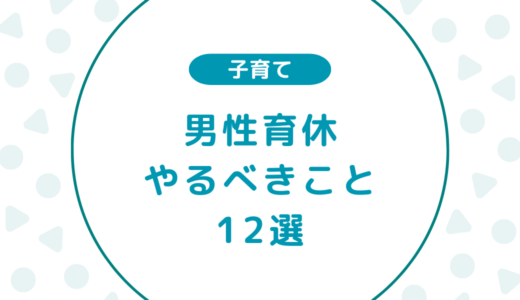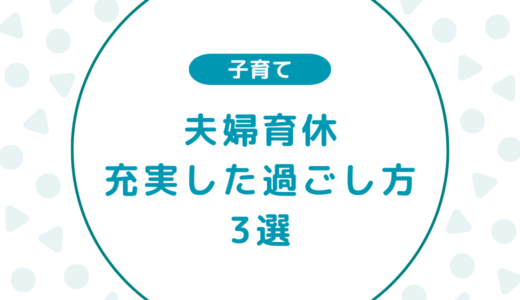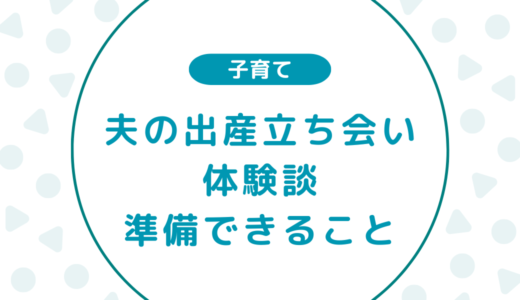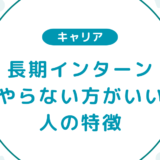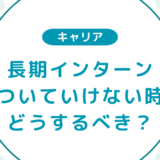この記事では、
- 「就活に備えて長期インターンをしようか迷っている」
- 「けど長期インターンって『きつい』って聞くし、自分にできるかどうか不安。するべきかどうかいろんな意見を知りたい」
という方に向けて、
- 長期インターンがなぜ「きつい」ものであるのか
- 長期インターンを始めるにあたって必要な覚悟・心構え
について、実体験ベースでお伝えします。

まるで1個上の先輩とサシ飲みに行ったかのように、「有益な情報が得られた」「心が少し軽くなった」「また明日から頑張ろう」、そんな気持ちになっていただけたら嬉しいです。
1. 前提:私の会社の特徴、私の長期インターン生マネジメント経験

私は「長期インターンをしていた大学生」側ではなく、「長期インターン生をマネジメントしていた担当社員」側の人間になります。
以下、私の勤めている会社、および私の長期インターン生のマネジメント経験の前提についてお伝えします。
(※私の勤めている会社、および私の長期インターン生のマネジメント経験の前提については、以下記事で別で詳しく記載しているため、ぜひ併せてご覧ください。)
私がマネジメントしていた長期インターン生の状況は、以下の通りです。
- 【長期インターン生に任せていた仕事】
・SEOライティング、SEO戦略・戦術の作成
・Webサイトの数値分析
・後輩のマネジメント - 【勤務条件】
・月50時間以上働くことが必須
・卒業まで働くことが必須
・フルリモート - 【私がマネジメントしていた長期インターン生の在籍大学】
・東大生・京大生・慶應生・東工大生・その他複数大学
以上の前提をもとに、以降では私のマネジメントの実体験をもとに「なぜ長期インターンはきついものであるのか」について、解説していきたいと思います。
2. 長期インターンが「きつい」ものである理由

ここからは、一般的に長期インターンがなぜ「きつい」ものであると言われているのか、について解説をいたします。
①求められるレベルが高い
長期インターン生に求められるレベルとしては、以下のようなものをイメージしておくと良いかと思います。
- 「大学生」としてではなく「一社会人」として扱われ、「一社会人」としてのスキル・ビジネスマナーを求められる。
- イメージとしては、数歳年上の社会人、例えば新卒2〜3年目レベルと同等レベルで成果を出すことが求められる
- アルバイトのように、ただ所定の時間分働いていればいいというわけではない。
「◯時間働きました」だけでは「だから何?契約通りの時間働くのは大前提だけど。」「その時間・時給を使ってどういう成果を出したのかを述べて」と言われてしまう。
「一社会人」として扱われるとはつまり、
「長期インターンをしていない普通の大学生と比べると、スキルもビジネスマナーもあるよね」ではダメで、
「新卒2〜3年目レベルの社員と比べても見劣りしないレベルでスキル・ビジネスマナーがついているよね」というレベルが求められるということで、
基準を「大学生」においているようでは、その時点で視座が低すぎる、となります。
日頃のミーティングでの発言の仕方、メール・チャットのやり取りなども、大学生のようなフランクな喋り方・コミュニケーションの取り方は当然許されず、一社会人として適切な喋り方・コミュニケーションの取り方が求められます。
また長時間働くのは「当たり前の大前提」でしかなく、評価の観点となるのは「何時間働いたか」ではなく「どれだけの成果を出したか」の1点のみになります。
加えて当然ですが、「ビジネスマナーもついていない」「就活も経ていない」大学生を、卒業までの数年間に会社で成果が出せるレベルまで育成をしなければいけないため、社員からのフィードバックも常に厳しいものにならざるを得ません。
もし長期インターンを大学1年生の春から始めようものなら、
この前まで高校3年生だった子がいきなり、「大学生」を飛び越えて「一社会人」として扱われ、5・6歳年上の社会人と同等の働きぶりを急に求められるようになるわけですので、
それはもちろんついていくのが大変になります。
②理想と現実のギャップに苦しむ
「長期インターンに参加してビジネスの現場に身を置きたい」と思うくらい意欲が高い学生ですので、
表面上がどれだけ謙虚でも、やはりある程度「自分のスキルに対する自信」を持っている学生が多いです。
しかし、どれだけ有名大学に在籍していて地頭が良い学生でも、
ビジネスの現場でゴリゴリに働いている社会人の目線から見ると、当たり前ですがまだまだ未熟なところは多く、たくさんのフィードバックをする必要があります。
そうすると
- 自分はもっとできると思っていたのに、実際は全然通用せず、毎回たくさんのフィードバックをされてしまう
- 自分よりランクの低い大学に通っている先輩・社員の方が全然成果を出してる
- 「起業したい」とか「自分で商品を生み出したい」とか思っていたけど、それが今の自分にとってどれだけ非現実的で大変なことなのかがわかった。
- 先輩・社員のように世に通用するレベルになるまでに、どれだけの研鑽を積まなければいけないんだろうと思うと、気が遠くなり途方に暮れてしまう
など、理想と現実の間にあるギャップの大きさに、自信が砕かれてしまう学生も多くいます。
③多くの時間を長期インターンに割く必要がある
基本的にビジネススキルというのは一朝一夕で身につくものではないため、スキルを身につけ成果を出すためには多くの時間を長期インターンに割く必要があります。
具体例として、例えば私の勤めている会社だと、長期インターンで成果を出していた学生は、1ヶ月の勤務時間が70〜80時間以上、多い人だと100時間を超えている、ということが多かったです。
「長期インターン」も「アルバイト」も「部活・サークル」も「学業」も「就活」も「ビジネスコンテスト」も「ボランティア」も「留学」も、、、「全て頑張りたいです!」というのは、基本的に非現実的で、まず通用しません。
長期インターンをするのであれば、他の活動の何か一つは諦めることになるというのが現実的なところで、これを受け入れられない学生は、かなり苦しんでいることが多かったです。
3. 「きつい」には2パターンある

個人的には、「長期インターンはきついものだ」と言っている学生には、2種類のパターンがあると考えています。
以下で詳しく解説いたします。
前述の
- ①求められるレベルが高い
- ②理想と現実のギャップに苦しむ
- ③多くの時間を長期インターンに割く必要がある
に対して「きつい」と感じる、と一口に言っても、それを
- 「辛い」に近い意味で「きつい」と感じているのか
- 「痛気持ち良い」に近い意味で「きつい」と感じているのか
で、種類が別れると考えています。
「辛い」に近い「きつい」
長期インターンに目的意識を持つことができておらず、いつまで経っても成果を出すことがない、うだつが上がらない状態でダラダラと働いているような学生は、
- 社員から日々きついフィードバックを受けることになる
- 周りの長期インターン生からも冷めた目で見られる
- いつまで経っても、評価・時給が上がらない
- 明らかに「チームのお荷物」感が漂っている
という状態になり、会社・本人の双方にとってよろしくない状態になっていきます。
こうなると、
- 周りの社員・先輩からの視線が痛い
- 長期インターンは、ただただ辛いだけの時間だ。
など「辛い」に近い「きつい」の状態になると考えています。
「痛気持ち良い」に近い「きつい」
成長に関する環境は3つに分類されると言われています。
- 【コンフォートゾーン】
苦労や努力なしに簡単に達成できる水準のこと。そのため、成長は見込めない。 - 【ストレッチゾーン】
今の状態では背伸びしてやっと届くか届かないかの水準、つまり簡単には達成できない水準のこと。
背伸びして挑戦することになるので、目標に対して不安やストレスを感じる。そのため快適で居心地がいいというわけにはいかない。
しかし成長にはつながる。 - 【パニックゾーン】
不安やストレスを過度に感じるほどの水準。
パニックになってしまうほどに高い水準では、目標に向かった挑戦ができなくなってしまうので、成長は望めなくなる。
【参考】
・ストレッチゾーン?パニックゾーン? | 『日本の人事部』プロフェッショナルコラム
私が考える、「痛気持ち良い」に近い「きつい」とは、
常に「ストレッチゾーン」に身を置き、自分の一歩先のところに目標を設定しチャレンジをしているため、背伸びをし続ける必要があり「きつさ」を感じるが
自分がなりたい姿・ありたい姿に近づいているという実感を持ちながら働くことができるため、「気持ちよさ」も感じることができる、という状態のイメージです。
基本的に、「自分から積極的に社員にフィードバックをもらいにいく」「自分から積極的に仕事を生み出す」といった行動をして、成果をどんどん出していくことができる学生が、こちらに当てはまります。
こちらのパターンの学生だと、前述の
- ①求められるレベルが高い
- ②理想と現実のギャップに苦しむ
- ③多くの時間を長期インターンに割く必要がある
についても、前向きな「きつさ」として受け入れることができていると感じています。
どちらのルートでも、長期インターンは「きつい」ものになる
- 長期インターンに目的意識を持つことができていないため、成果を出すことができず、落ちこぼれていくルート
- どんどんフィードバックを吸収して成長していき、成果を出していくルート
どちらのルートでも、ある意味、違った意味で長期インターンは「きつい」ものになります。
ですので、基本長期インターンは「きつい」ものだと思っておくのが良いでしょうという結論になります。
もちろん、目指したい「きつい」状態は後者の方ですね。
長期インターンを「きつい」と思えていない学生は、それはそれで問題
逆に、長期インターンを「きつい」と思えていない人は、
- 長期インターンで成長をしよう、成果を出そうという意欲が端からない。
長期インターンに参加できた時点で目標達成だと割り切っている。 - 常に自分にとって簡単な仕事にしか手を上げない。「コンフォートゾーン」に身を置いている
といったタイプの学生だと考えられます。
上記のような状態では、長期インターン生として働いている意味がまるでないですし、雇ってもらっている企業に対しても不誠実な態度ですよね。
もし万が一周りの先輩に
- 「うちの長期インターンは全くきつくないから。超楽だから」
- 「自分は長期インターンをきついと思ったことなんて一回もないし」
などという謳い文句で長期インターンに誘ってこようとしてくる人がいたとしたら、そう言う先輩には安易について行かない方がいいと言えます。
真面目に働いている人であればきっと
- 確かに最初はできないことやわからないことが多くて、自分も大変だった
- 社員の人からは厳しいフィードバックをもらうこともある
- でも自分の成長につながるいい経験ができるから、おすすめしたいんだよね
といった、ある程度「きつさ」があること前提で誘ってくるはずです。
4. 「辛い」という意味で、長期インターンを「きつい」と感じてしまう学生の特徴

ここからは、「辛い」という意味で「きつい」と感じてしまう学生とはどういう学生なのかについて、改めて解説をいたします。
長期インターンでどんな経験・スキルを得たいのか、目的意識のない学生
個人的には、長期インターンで落ちこぼれるか、成果を出すかの分かれ目は、一言で言えば「目的意識の有無」によって決まると考えています。
目的意識のない学生とは、以下のような学生のことを指します。
- 「ガクチカに書くネタを作りたい、就活を有利に進めたい」という理由で長期インターンに参加している学生
- 「責任感・主体性を身につけたい」「意識が高い人に囲まれることで自分の姿勢を正したい」などマインド面の話しか出てこない学生
- 「パソコンを使いこなせるようになりたい」など、手段・テクニックの部分の話しか出てこない学生
(※長期インターンに目的意識を持つことができていない学生の特徴については、以下記事で別に詳しくまとめているため、ぜひ併せてご覧ください。)
長期インターンに目的意識を持つことができていない学生だと、ちょっとの障害物・出来事で凹んでしまい、
- なんでこんなに言われなきゃいけないんだ
- 学生の本分は学業なのに、なんで長期インターンでこんな辛い思いをしなきゃいけないんだ
といった状態になることが多いと感じています。
※「目的意識の有無によって、目の前の障害物をどう捉えるようになるか」については、
下記youtube動画の、00:00〜2:10あたりまでの「身長の話」が、イメージとしてはとてもわかりやすいためぜひご覧ください。
なお余談ですが、何かの言い訳の際に「学生の本分は学業」と言い出す学生で、本当に学業を頑張っている長期インターン生を、私は見たことがありません。
大抵長期インターンで成果を出すことができていない人は、学業でもそこまで成果を出すことはできておらず、
長期インターンで成果を出すことができている人は、学業及びその他の活動の場でも成果を出すことができていることがほとんどでした。
5. 「痛気持ち良い」という意味で、長期インターンを「きつい」と感じられる学生の特徴

ここからは、「痛気持ち良い」という意味で「きつい」と感じられる学生とはどういう学生なのかについて、改めて解説をいたします。
長期インターンでどんな経験・スキルを得たいのか、明確に目的意識がある学生
- 将来起業を考えているため、ビジネスの全体像を把握できる場所に身を置き、事業計画や戦略を作れるようになりたい。
- マーケティングについて一通りの知識を身につけ、自分の力で商品を作り出し、売りだすことができるようになりたい。
- SEOの知識・Webライティングの力を身につけることで、自分でブログ立ち上げ・収益化できるようになり、それで生きていけるようになりたい。
- 将来は学校の先生になる予定だが、一通りのビジネススキルを持った上で先生になり、それを校務の現場に活かしたい。
上記のように、明確に「自分の人生をこういうふうに進めていくために、長期インターンという場でこういう経験・スキルを得たい」と目的意識を持っていた人は
たとえ厳しいフィードバックを受けたとしても、
「自分のなりたい姿・ありたい姿」を常に見据えられており、そこに着実に歩みを進めることができているという実感を持ちながら、その経験を受け入れることができるため
「痛気持ち良い」「足りていない点についてもっとフィードバックしてほしい」と、スッキリ明るい表情で働くことができている印象がありました。
7. 最後に
長期インターンが「きつい」ものである理由をまとめると
となります。

新しい物事にチャレンジするのは、誰だって勇気がいることです。
自分の実体験が、少しでも皆さんの心を軽くしたり、背中をそっと押すものになることができたら嬉しいです。
このサイトでは、後輩を応援したいという気持ちで、これからもさまざまな記事を執筆していきますので、ぜひご覧ください。
 わたしたちについて
わたしたちについて
またこのブログでは、他にもキャリア・長期インターンについて記事を執筆していますので、ぜひ併せてご覧ください。