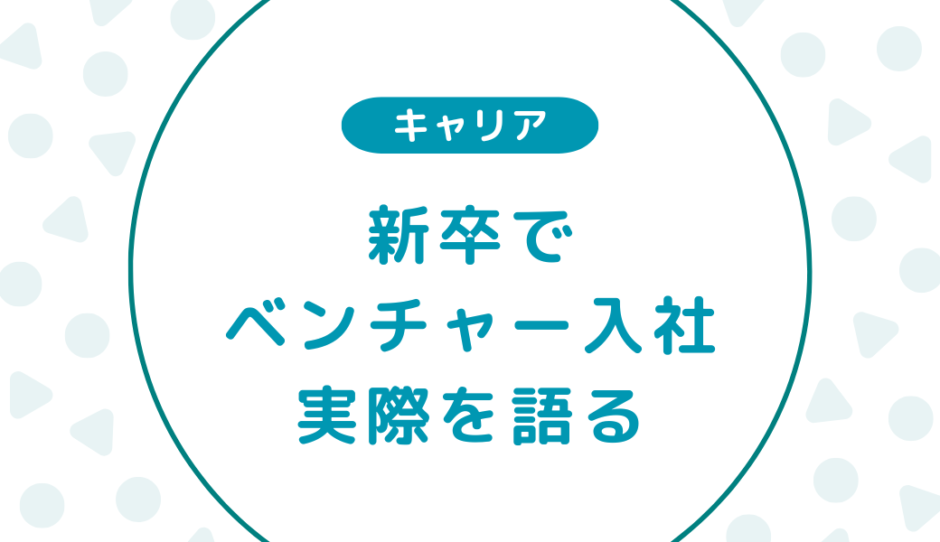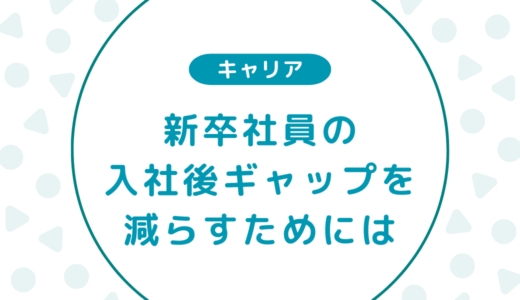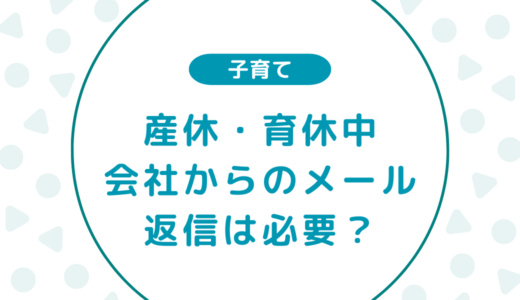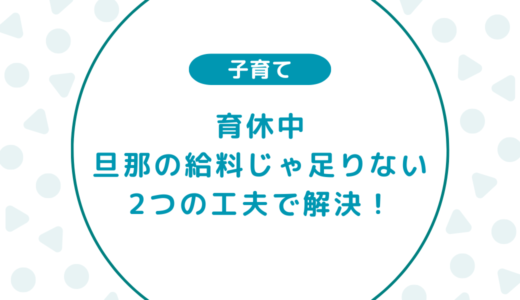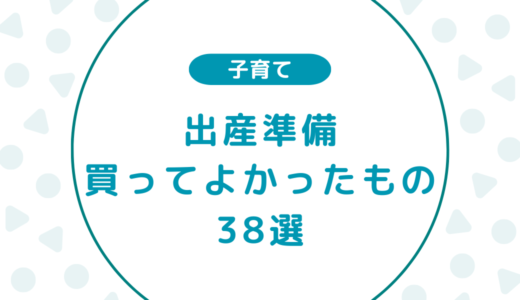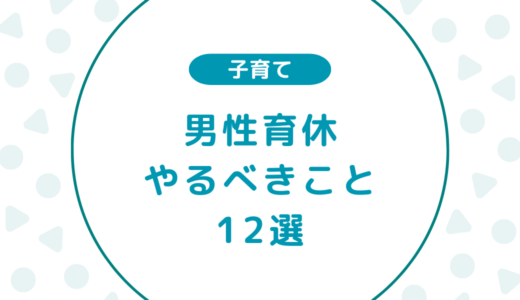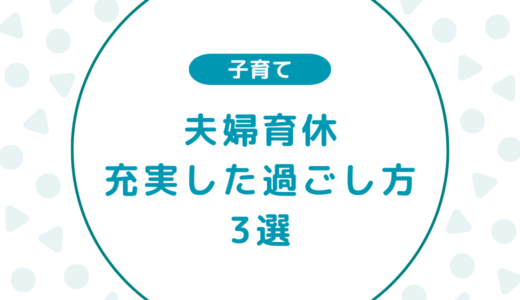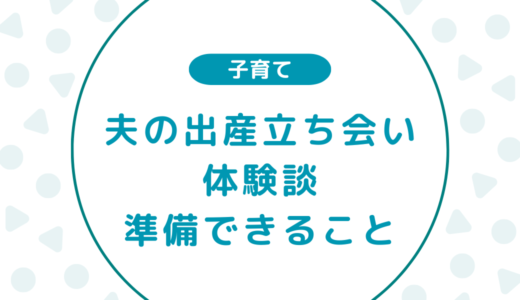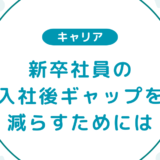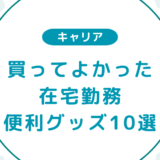この記事では、
- 「ベンチャー企業と大手企業、どちらに入社するのが良いのか迷っている」
- 「ベンチャー企業だと実際どれくらいスピード感持って成長できるのか知りたい」
という方に向けて、
- 実際に新卒でベンチャー企業に入社してから私が行った業務内容
- 私の実体験を踏まえ、ベンチャー企業に入社することのメリット・デメリット
について、実体験ベースでお伝えします。

まるで1個上の先輩とサシ飲みに行ったかのように、「有益な情報が得られた」「心が少し軽くなった」「また明日から頑張ろう」、そんな気持ちになっていただけたら嬉しいです。
1. 入社してからの数年間、実際に任された仕事の内容

区切りとして、私の新卒3年目までの仕事内容を載せます。
私の事例を元に、少しでも「裁量権のリアルさ」「経験を積むスピード感のリアルさ」などについてイメージを持っていただけたら幸いです。
新卒1年目
■BtoC事業の新サービス立ち上げ・ローンチ
【担当業務】
- 3C・STP・4P分析で、自社が攻めるべき領域を検討
- テストマーケティングでVOC取得
- 集客用のLP・バナー作成
- 取引先との広告出稿の調整
- プロダクトの作成
- 派遣社員への研修資料の作成
- 価格設計(コスト・損益分岐点の計算、簡易PLの作成)
- 顧客対応のオペレーション設計(問い合わせから契約・サービス提供までのフローチャート作成、メール・電話対応のテンプレート作成)
- 顧客対応(メール・電話対応)
【組織構成】
- グループメンバー1名(自分のみ)
新卒で入社後、いきなり新規事業の立ち上げを1人で行うことになりました。
チームメンバーというものは存在せず、企画書・プロダクト・LP・オペレーションフローの作成の何から何まで、自分1人で全て作り上げていく、ということが課せられました。
またお客様から電話で「事業の責任者を出せ」とクレームをいただいた際には、私(新卒入社数ヶ月程度の人間)が「私が最高責任者です」と矢面に立っていた、という状況でした。
新卒2年目
■上期:既存サービスエリア拡大のための、Webマーケ施策の検討・実行
【担当業務】
- 市場規模・問い合わせ数上限の数値シミュレーション
- 電話・アンケートによるVOC取得
- サイト数値分析、課題発見
- コンテンツSEOの戦術検討
- Webページの新規作成、リライト
【組織構成】
- グループメンバー1名(自分のみ)
■下期:部内オペレーションチーム(顧客対応)のサポート
【担当業務】
- 新入社員・新人アルバイト入社時の受け入れフロー・マニュアルの整備
- 新入社員・事務アルバイトへの研修
- 顧客対応(メール・電話対応)
- 派遣社員応募者の面接(160名程度)※本期間以外の対応含め累計値
- グループウェア導入PJの実施
【組織構成】
- グループメンバー10数名
- 社員数名、アルバイト10数名
1年目の際に立ち上げた新規事業については、引き続きお客様対応を1人で続けつつ、それに追加して新たに既存サービスのエリア拡大業務が加わりました。
この時期から会社全体の方針として、「Webマーケターを育成したい」というものが掲げられ、結果私も例に漏れず、Webマーケティングの分野に携わっていくことになりました。
また2年目の下期には、部内オペレーションチームで大量離職が発生したため、
オペレーションチームの業務内容を即キャッチアップ、人員不足を自分の労働力で補いつつ、離職に合わせて大量採用された社員・アルバイトに対して研修を行うなどしていました。
新卒3年目
■既存サービスWebサイトの自然検索チーム責任者
【担当業務】
- サイト数値分析、課題発見
- コンテンツSEOの戦略・戦術・KPI・KDI作成
- 大学インターン生・アルバイトのマネジメント・育成(入社オリエンテーション、研修、毎週の定例MTG・1on1、フィードバック、評価面談等)
- クラウドソーシング上での、単発ライターとの契約・マネジメント
- ライティング/画像作成マニュアル・ガイドラインの整備
- ユーザーインタビューによるVOCの取得
- Webサイトリニューアルの企画
- メールマガジンの立ち上げ、メルマガ配信ツールを用いた運用
- 中途採用応募者の一次面接(20名程度)
- オペレーションチームへのマーケティング施策(新サービス開設・料金変更等)の落とし込み(説明資料作成・説明会開催等)
【組織構成】
- グループメンバー10数名程度
- 社員1名(自分)
- 大学インターン生(ライティング・SEO戦略・戦術作成業務)10数名
- アルバイト(マーケアシスタント業務)数名
- 単発ライター(ライティング業務)累計20数名 ※クラウドソーシング上で都度募集
新卒3年目からは、マネジメント業務も行うことになりました。
相変わらず社員は1名で、常に自分が責任をとる立場にありました。
また新たに中途社員を採用することになり、その一次面接も担当することになりました。
中途採用で応募してくる方は、自分よりも年上の方ばかりだったため、どういうスタンスで面接をするべきか、なかなかに難しかった記憶があります。
2. ベンチャー企業に入社してよかったなと思うこと

以上の業務内容の実体験を踏まえ、「ベンチャー企業に入社してよかったなと思うこと」「ベンチャー企業に入社するとこういうメリットがあると思う」といった点についてご紹介します。
①早い時期に、サービス責任者のレベルで裁量権を持つことができる
会社にもよると思いますが、やはりベンチャー企業だと、大手企業と比べると、サービスの規模はそこまで大きいものではないことが多かったりします。
さらにそれが、少数精鋭でありながら事業多角化のためいくつもサービスを抱えていたりする会社だったりすると、たとえ新卒であったとしても、必然的に「一人一つサービスの責任者になる」くらいの勢いで責任者の立場が回ってきたりします。
「立場が人を作る」とは本当にその通りで、責任者という立場を与えられると、「このサービスをよくするためにはどうしたらいいか」を真剣に自分の頭で考えるようになり、ただ与えられた業務をこなしているだけの時よりも、視座が高く視野が広くなりやすいと感じています。
②自分の手でなんでも変えていけるので、やりがいを感じやすい
部長や上長は存在するものの、裁量権はほぼ自分の手に渡されているため、以下のように、自分の手で変えていける範囲が広いです。
- お客様から値引き交渉をされたり、返金対応を求められたりした際、その対応にどこまで応じるか自分で判断をすることができる
- このプロモーションの仕方ではお客様に刺さらないのではと思った際に、別のプロモーション案を自分で作り上げて、打ち出し施策の実行まで行うことができる
- 人員を増やしたいと思った際に、採用計画作成から実際の採用面談まで自分の手で行うことができる
- 他の人の担当領域であったとしても、「もっとこうした方が良いのでは」と思ったことがあれば自由に提案を行うことができ、なんなら仕事を積極的に巻き取るということも日常茶飯事。
「このサービスは私が育てた」と言えるレベルで、自分の手でサービスを作り上げることができるため、やりがいを感じやすいと思います。
また、もっとここの部分をよくしたいと思った際に、なんの制約に阻まれることなく自由に即動き出しを始めることができるのも良い点だなと思います。
もちろん、会社・部署の方針と異なる方に勝手に進まれたり、無計画に予算をガンガン使われては困るため、部長や上長に一言承認をいただく必要はあります。
が、毎週の定例ミーティングの場で「これくらいの金額がかかりそうですが、これくらいのリターンが見込めるので、予算を使っていいですか」等、具体的な数値を提示しながら論理的に説明を行うことができれば、その場でスムーズにOKが出ることが多いです。
決裁までに時間がかかったり、ハンコのスタンプラリーなどがあったり、というのは私の場合は基本的にありませんでした。
③社長や経営陣との距離が近く、刺激を得やすい
ベンチャー企業と一口に言っても、従業員数は会社によってそれぞれかと思いますが、それでも従業員数1000名を超えるような大手と比べると、圧倒的に社長や経営陣との距離は近いように思います。
特に私が新卒で入社した会社は、従業員数が80名程度の会社で、頑張れば会社内のほぼ全社員の顔と名前を一致させることができるくらいの規模でした。
当然「社長室」などの部屋もないため「社長や経営陣が近くの席で働いている」というのが日常の風景でした。
また夜遅くまで残っていると、社長や経営陣の方に飲みに誘ってもらえることも多い、という状況でした。
会社を立ち上げ、さまざまな苦労を乗り越えて事業・会社を大きくしてきた張本人から、直々にその時の苦労話を聞くことができたり、今の自分に合わせて適切に仕事のアドバイスをもらうことができるのは、非常に貴重でありがたいことだなと思っていました。
3. ベンチャー企業に入社して後悔したこと

会社によって状況は異なるとは思いますが、私が個人的に「思っていたのと違った」「大手と比べると見劣りするな」と思った点がいくつかあるため、ご紹介します。
もちろん、ベンチャー企業に入社して後悔したことも多くあります。実際、入社後ギャップも大きかったです。
ベンチャー企業に入社した後の入社後ギャップについては、別で以下記事に記載しているため、ぜひ併せてご覧ください。
①教育・研修制度が整っていないことが多い
ベンチャー企業に入社するのであれば「ベンチャー企業に『教育』『研修』などという概念は存在しない」と覚悟しておくくらいがちょうどいいと思っています。
実際私も、新卒でベンチャー企業に入社した際「研修期間はなし、入社翌日から実業務開始」という状況でした。
挨拶の仕方・電話の取り方・メールの書き方・議事録の取り方などについて細かく指導されることはなく、「わからないことは自分でググって調べて」というスタンスが基本でした。
また新入社員の育成担当になった社員に対しても、適切な教育・研修はもちろん行われていないため、
- 新人を育てるときの基本の流れ
- 適切な指示の出し方
- 新人がつまずいたときの適切なフォローの仕方
といった基本のことがわかっていないまま、なんとなくの感覚で新入社員を育てているということが多く、
またマネジメントをすることになったからといってその人の業務量が減らされるわけではないため、マネジメントする側の社員にも心の余裕がなくなり、
結果「キツイ物言いで指導をする」「パワハラをする」などが起きてしまう、ということも日常茶飯事です。
また、上記のような状況を憂いた社員が、新しく研修制度や教育制度を会社内に取り入れようとすると、「俺たちの時はもっと大変だったのに」「今の新人は楽でいいね」など反発が起こったり嫌味を言われることすらもあります。
②社内にロールモデルが少ない
特に「新卒1期生募集!」など掲げている、「新卒を新しく採用する」「新卒を取り始めて間もない」という企業であればあるほど、
社内にロールモデルとなる人がいないため、入社後に「自分の今後のキャリアをどう築いていけばいいのか」に悩みやすくなる可能性があります。
個人的には、新卒6期生以降くらいになってくると、それまでの新卒社員の成長スピード・成長過程などの事例を参考に、「◯年目までにこれくらい仕事ができるようになっていればいいんだな」「◯年後には、自分もあの先輩みたいになりたい」と目安が立てやすくなるように思います。
またその頃になると会社・上司側も、過去の新卒社員の事例を参考に「この子はあの先輩とタイプが似ているから、こういうふうに育てればいいかも」とPDCAを回しながらより効果的・効率的に新卒社員を育ててくれるようになるため、かなり過ごしやすくなると思います。
逆に「新卒1〜5期生」くらいまでは、会社の制度が整っておらず、且つ上司も手探りで新卒を育てるという状況になるため、かなりの荒波に揉まれる可能性があり、何があっても挫けない力や自分で道を切り拓いていく力が必要になると思っています。
③評価制度が曖昧
よく「大手企業は年功序列、ベンチャー企業は実力主義」など聞くかもしれませんが、個人的にはベンチャー企業の評価制度にそこまで期待は持たない方が良いのではと考えています。
私の会社も「実力主義で評価」と口では言っていますが、実際のところは
- 同期とそこまで評価の差がつけられることはない
- どれだけ活躍しても、新卒の先輩の給料や、年齢の高い中途社員の給料を追い抜かしてしまわないよう、調整がかけられる
- 上司も忙しいので、一人一人の評価をつけるのにそこまで時間をかけていない。一人あたり数分程度で、なんとなくの感覚で評価がつけられているのが現状
- なんなら評価面談の際に「あ、ごめんここの評価つけるの忘れてた、まあ◯年目になったしこれくらいの評価でいっか」とその場で点数をつけられることも
- 評価担当者によって、評価を緩くつける厳しくつけるの差が激しい。
- 明らかに今の会社の事業フェーズと評価項目があっていないなと思っても、会社として評価制度の改修に人材を貼る余裕がないため、随分昔に作られた評価制度のまま評価項目が変わっていない。
といった現状です。
もちろん会社によると思うので、評価制度を重視して就活するのであれば、面接時等に、
- 「実力主義で評価」というが、具体的に「同期内でこれくらい評価に差がつけられている」などの事例はあるか
- 新卒社員が、年齢の高い中途社員(30代・40代・50代等)よりも給料を高くもらっている事例はあるか
- 評価制度・評価項目の見直しはどれくらいの頻度で行われているか
- 人間が評価をつける以上、評価担当者ごとに評価内容のバラツキが生じると思うが、その調整は会社全体ではどのように行われているか
などは質問しておくと良いかもしれません。
がそもそも「人間が人間を評価する以上、完璧な評価制度などこの世に存在しない」ということは知っておいた方が良いと思います。
④採用基準は結構緩い
ベンチャー企業は、大手と異なりどうしてもネームバリューがないため、採用の母集団の形成にはかなり苦労をしています。
またさらに、せっかく入社をしたとしても、前述の通り教育体制・評価体制が整っていなかったりするため、その過酷な環境に耐えられず入社後数ヶ月経ってすぐに転職してしまう、という社員が一定数存在します。
そのため、採用時にいちいち人を選り好みする余裕がなく、結果よほど社会人としてマナーがなっていないなどでなければ即採用、となることが多いです。
私の会社も、入社した社員に対して「うちの会社は選考基準が厳しいから、入社できたことに自信を持って」など口では言っていますが、
実際は部長が裏で「あいつには選考時にB-の評価をつけたけど、とりあえず人手が足りないので入社させた」など周りの社員に吹聴していたりするのが現状です。
⑤福利厚生の制度が、大手と比べるとどうしても見劣りする
これは、私が妊娠・出産を機に、初めて気にした点になります。
大手の会社の中には、「出産お祝い金として◯百万支給します!」「住宅手当を毎月◯万円支給します!」など福利厚生が充実している会社がいくつもあると思います。
しかし基本ベンチャー企業には、資金に余裕がないことが多いので、そのような福利厚生はあることは少ないです。
また育休取得についても、会社の雰囲気としてかなり取りづらさがあるように感じています。
ベンチャー企業は常に人手不足であることが多いため、妊娠が報告された際には「え、あの人が抜けたらその分の仕事がこっちに回ってくるじゃん」「え、男なのに育休とるの?」などの雰囲気が職場に蔓延したりします。
4. こんな人は、そもそもベンチャー企業を選択肢に入れない方がいいかも

まず「こんな人はベンチャー企業をそもそも選択肢に入れない方がいいと思う」という方を挙げていきたいと思います。
毎日を安定してゆっくり過ごしたいと思う人
ベンチャー企業は「安定」「ゆっくり」「穏やか」「ほのぼの」などの概念からはかけ離れた場所にある存在です。
常にキャパオーバーな量の仕事が振られる、平日は残業で帰りが遅くなってプライベートの時間が確保できない、最悪の場合土日返上で働くこともある、というのはザラにあります。
就活でベンチャー企業のキラキラ新卒採用人事の方と話したりすると、「ベンチャー企業ってオシャレにスマートにキラキラしながら働くことができる場所なのかな」など思ってしまうこともあるかもしれませんが、実際はベンチャー企業はかなり過酷な場所です。
キラキラ感を夢見ながらベンチャー企業に入ろうとするのは、かなり危ないと言えます。
「バリバリ働きたいからベンチャー」という考え方をしている人
逆にもし「バリバリ働きたいからとりあえずベンチャーに入りたい」と考えている方がいらっしゃるとしたら、それもそれで考えものだなと思っています。
ベンチャー企業に入ろうが大手企業に入ろうが、激務な会社は激務です。しかし個人的には、同じ激務なら大手企業での激務の方が良いのではと考えています。
理由は以下の通りです。
- 名の知れた大手企業で働いている、という社会的な信頼度の高さ
- 給料もベンチャー企業より良いことが多い
- 福利厚生の充実度
- 携わっているサービスの規模が大きい。世の中に対しての貢献度の大きさがベンチャー企業とは桁違い
「ベンチャー企業でこういった経験を積みたい」という考えが明確にあるのであれば、ベンチャー企業を選択肢に入れても全然良いと思いますが
「ベンチャー企業だとなんとなくバリバリ働けそう」くらいであれば、いったん立ち止まって考え直すことをおすすめします。
後述しますが、大手からベンチャー企業に転職するのは簡単でも、ベンチャー企業から大手に転職するのは手間がかかったりします。
ベンチャー企業に入るのは、キャリア的にリスクになる部分が一定数あるのです。
普通にバリバリ働きたいだけであれば、ベンチャー企業ではなく大手企業で働くのが良いと考えています。
「ビジネスを立ち上げる」ということにあまり興味がない人
過激派なベンチャー企業だと「0→1こそが全て」「1→10なんて誰でもできる簡単な仕事」という雰囲気の会社もあります。
やりたい業務内容が「ビジネスの立ち上げ(0→1)」というよりも、
- ルールを徹底させること
- オペレーションを正確に効率的に回すこと
- 整然とした組織体制を作り上げること
といった「1→10」「10→100」に向いている方は、会社のフェーズにもよるとは思いますがベンチャー企業ではなく大手企業で働いた方が良い可能性があります。
5. こんな人は、ベンチャー企業に入りたいと思っていても、まずは新卒のうちは大手に入ったほうがいいかも

「人生で一度はベンチャー企業で働いてみたい」と思っている人でも、以下に当てはまる人は、新卒のうちはまず大手に入るのが良いと考えています。
教育・研修を受ける期間をちゃんと確保したいと思う人
前述の通り、ベンチャー企業では新入社員に対して「OJTという名の放置」が行われることが多くあります。
ですので、「ちゃんと教育・研修を受けてから実践の場に出ていきたい」という方は、まずはベンチャー企業ではなく大手企業に入ることを強くおすすめします。
将来独立や起業を考えている人
「将来独立や起業を考えているから、ビジネスの全体像を見ることができるベンチャー企業に入りたい」という方もいらっしゃるかと思いますが、
独立や起業を検討しているのであれば尚更、「大手企業出身である」という肩書きを持つことは有利になると思うので、まず最初は大手企業に入った方が良いのではと思います。
人生で一度は大手で働いてみたい、と思う人
新卒でベンチャー企業に入ることのデメリットとしてよく言われるのが、「大手からベンチャーには簡単に行けるが、ベンチャーから大手に行くのは大変」というものです。
私もその通りだと思っています。
もちろん「ベンチャー企業から大手企業への転職は絶対に不可能」というわけではありませんが、選考時に「自分がどれだけ使える人間か、どれだけのスキルがあるのか」というのを丁寧に説明をするコストがかかります。
もし「大手で働くという経験をしてみたい」と思っているのであれば、新卒のうちに先に大手を経験しておくのが良いと考えています。
6. こんな人は、新卒からベンチャー企業に入社するのがおすすめ

最後に、「こんな人であれば新卒からベンチャー企業に入るのでも良いと思う」という方を挙げていきます。
ここで私が問いたいのは、「限りある新卒切符をベンチャー企業に使うメリットとは」ということについてです。
「ベンチャー企業で働くことのメリット」自体は前述の通りいくつかありますが、それらは「新卒でベンチャー企業に入ることのメリット」にはならないと考えています。
ベンチャー企業で刺激を受けながら自分の手でビジネスを作り上げていきたい、と思っているとしても、
それは、いったん大手に入って基本的なビジネスマナーをつけて、数年経ってから第二新卒としてベンチャーに入社するのでも、十分遅くないのではないでしょうか。
ベンチャー企業は人の出入りが激しいので、第二新卒として入っても「新卒優遇」を受ける対象に入ることができる可能性が高いと考えています。
ではどういう人であれば、新卒からベンチャー企業に入社した方が良いのでしょうか。
いち早く、経験を積みたい人
新卒切符をベンチャー企業に使うことの最大の利点は、「いち早く」経験を積むことができる、という点だと考えています。
20代のうちの数年間は、その後の社会人人生での価値観を形成するにあたって、確かに重要な期間になると思っています。
「いったん大手に入ってから第二新卒でベンチャーに入社するのでは遅すぎる、数年の誤差さえも惜しい」と思う人は、新卒でベンチャー企業に入るのが良いでしょう。
逆に、そこまでのスピード感を求めているわけでないのなら、「まずは大手企業に入って適切な教育を受け、社会人生活に慣れ、多少の荒波にも耐えられそうなメンタルを身につけてからベンチャー企業に入る」というのが健全で良いのではと考えています。
7. どんな会社に入ったとしても、選んだ道を正解にするしかない

最後に、ベンチャー企業に入社して数年経った先輩の立場として、就活生に伝えたいことをいくつかまとめます。
ここまで、ベンチャー企業のメリット・デメリットを書き連ねてきましたが、私は基本的に、人生に正解がないのと同じように、会社選びにも正解はないと思っています。
完璧で100点満点の会社など、この世に存在しません。
大手企業でもベンチャー企業でも、どんな会社を選んだとしても、入社後に「思っていたのと違った」となることは必ずあると思います。
ですので大切なことは、
- 「選んだ道を正解にする」
- 「自分の人生の責任は自分でとる」
という覚悟を持って、会社選びをすることだと考えています。
8. 最後に
ベンチャー企業に入社することのメリット・デメリットをまとめると
- 【メリット】
①早い時期に、サービス責任者のレベルで裁量権を持つことができる
②自分の手でなんでも変えていけるので、やりがいを感じやすい
③社長や経営陣との距離が近く、刺激を得やすい - 【デメリット】
①教育・研修制度が整っていないことが多い
②社内にロールモデルが少ない
③評価制度が曖昧
④採用基準は結構緩い
⑤福利厚生の制度が、大手と比べるとどうしても見劣りする
となります。

新しい物事にチャレンジするのは、誰だって勇気がいることです。
自分の実体験が、少しでも皆さんの心を軽くしたり、背中をそっと押すものになることができたら嬉しいです。
このサイトでは、後輩を応援したいという気持ちで、これからもさまざまな記事を執筆していきますので、ぜひご覧ください。
 わたしたちについて
わたしたちについて
またこのブログでは、他にもキャリア・就活について記事を執筆していますので、ぜひ併せてご覧ください。