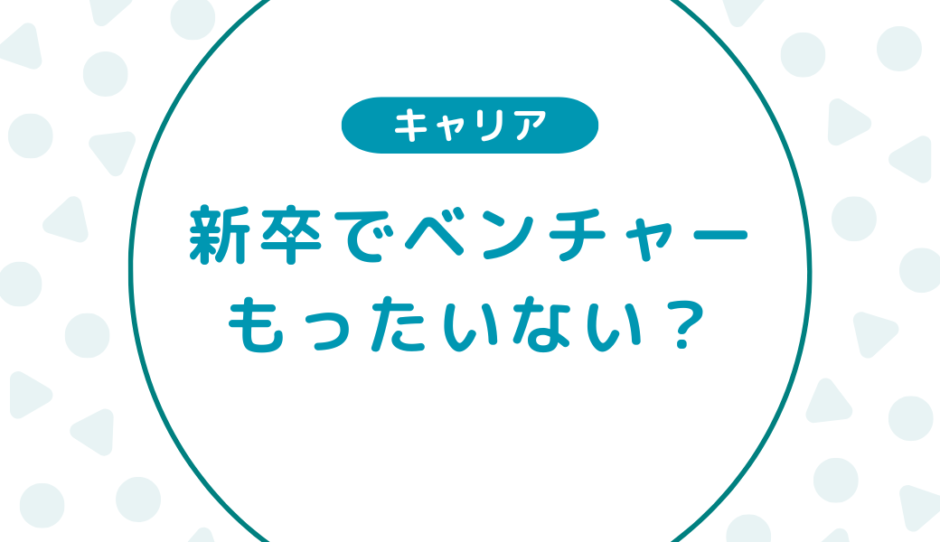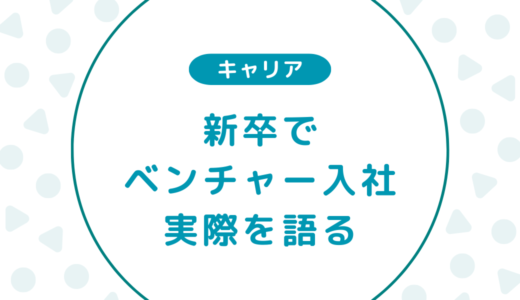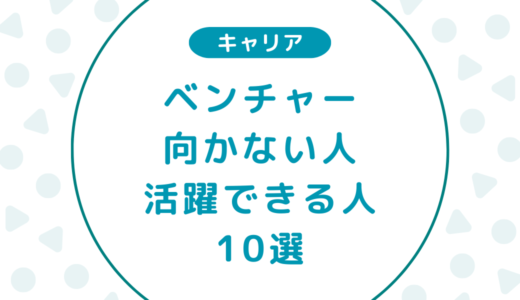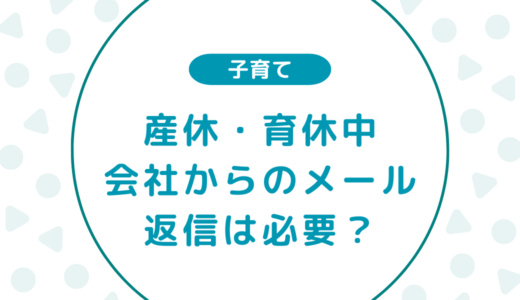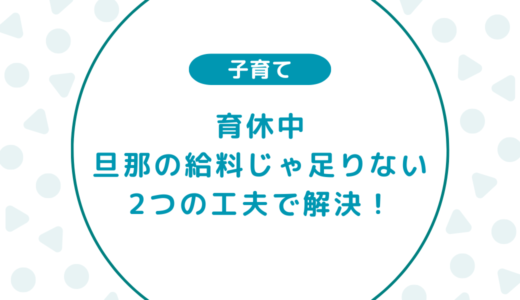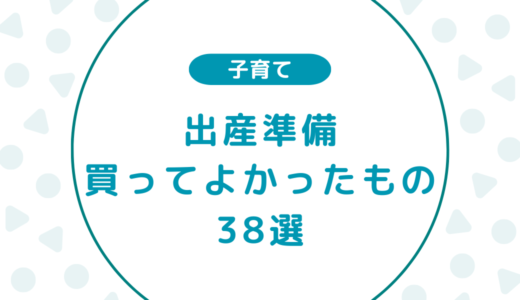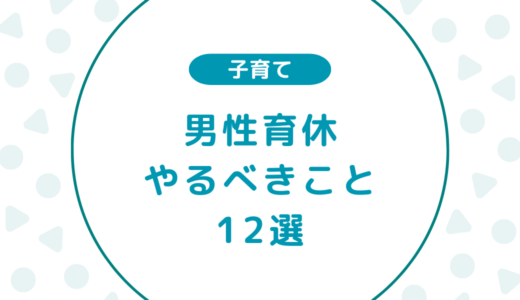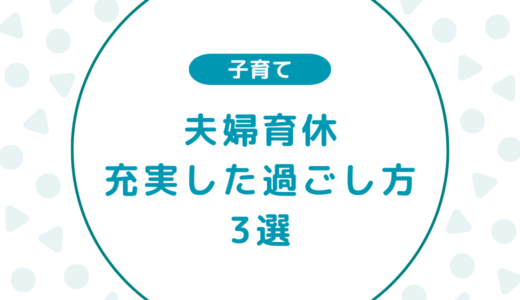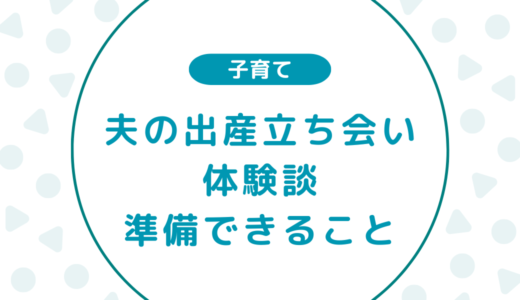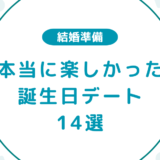この記事では、
- 「新卒でベンチャー企業に入るのが不安」
- 「新卒でベンチャー企業に入るか迷っている」
という方に向けて、
- ベンチャー企業と大手企業の違い
- なぜ新卒でベンチャー企業は「やめとけ」「もったいない」と言われるのか
- ベンチャー企業で身につくスキル
- 会社選びで後悔しないようにするための3ステップ
- 良い企業の見分け方
について、自分も同じように不安になったり挫折した経験を踏まえ、実体験ベースでお伝えします。

まるで1個上の先輩とサシ飲みに行ったかのように、「有益な情報が得られた」「心が少し軽くなった」「また明日から頑張ろう」、そんな気持ちになっていただけたら嬉しいです。
1. ベンチャー企業と大手企業の違い

新卒の就職活動において、1度はベンチャー企業と大手企業のどっちがいいの?という話題が挙がると思います。そもそもベンチャー企業と大手企業って何が違うんだ?という方もいると思うので、ベンチャー企業で働いている経験談と大手企業で働く友人、取引先のお客様の働いている様子をもとに、それぞれの特徴をお伝えします。
ベンチャー企業とは
- 従業員が少なく、平均年齢が若いことが多い
- 創業から日が浅く、成長過程にある
- メンバー1人の業務範囲が広い(裁量権がある)傾向がある
大手企業とは
- 従業員数が多く、企業のネームバリューがある
- 会社の歴史が長く、経営基盤が安定していることが多い
- 働きやすくて、福利厚生が充実しており、育成環境も整っている

お気づきの方もいるかもしれませんが、明確な定義がないんです!
あくまでも、そういう傾向があるとか主観的な感想だとか、人によってとらえ方が変わってしまうというのが実態です。そのため、「〇✕株式会社は大手企業だよね」という暗黙の了解となっていることや「メガベンチャー」というベンチャー企業と大手企業の両方の要素を兼ね備えているような企業の表現がある状態です。
中小企業庁の定義
経済産業省の下部組織である中小企業庁の定義を見てみましょう。
日本の行政機関が発表している内容なので、基準が明確になっています。
(1)大企業
(2)及び(3)に該当しない企業
(2)中小企業
- 製造業、建設業、運輸業その他の業種:資本金3億円以下又は従業者規模300人以下
※ゴム製品製造業は、資本金3億円以下または従業者規模900人以下- 卸売業:資本金1億円以下又は従業者規模100人以下
- サービス業:資本金5000万円以下又は従業者規模100人以下
※ソフトウェア業、情報処理サービス業は、資本金3億円以下又は従業者規模300人以下
※旅館業は、資本金5千万円以下または従業者規模200人以下- 小売業:資本金5000万円以下又は従業者規模50人以下
(3)小規模企業
中小企業庁.”中小企業・小規模事業者の数(2021年6月時点)の集計結果を公開します”.2021-12-13.https://www.chusho.meti.go.jp/koukai/chousa/chu_kigyocnt/2023/231213chukigyocnt.html,(参照2025-02-11)
- 製造業、建設業、運輸業その他の業種:従業者規模20人以下
- 卸売業、小売業、サービス業:従業者規模5人以下
※宿泊業・娯楽業は、従業者規模20人以下
業種によって異なりますが、従業員数と資本金で企業の名称を区分しています。
そのため、良く聞く大手企業とベンチャー企業の区別は、
その人の主観に基づいた内容になっていることが多いというのを認識しましょう。
大手企業でもここで記載したベンチャー企業の要素を持つ企業もあれば、
ベンチャー企業でもここで記載した大手企業の要素を持つ企業もあります。
2. なぜ新卒でベンチャー企業は「やめとけ」「もったいない」と言われるのか

Googleの検索欄に「新卒 ベンチャー」と入力すると、「やめとけ」「もったいない」というキーワードが出てくる場合があります。これからベンチャー企業に入社をしようか考えている人にとって、このような言葉は意思決定を迷わせる言葉だと思います。このように言われる理由を把握することで、自分の選択の納得度を高めることができます。
①大手企業は中途入社するのが難しい
最近では、大手企業でも中途採用を始めているところも増えてきましたが、
新卒一括採用で入社した人を育成して昇進させていくというこれまでの時代背景が強く残っているため、
新卒で大手企業に入社する方が中途で大手企業に入社するよりも入社しやすいと言われます。
そのため、中途でも入社しやすいベンチャー企業にわざわざ新卒カードをを使うのはもったいないという主張があります。
しかし、どうしても行きたい会社が新卒採用しかしていない場合でもない限り、大手企業への道が完全に閉ざされるというわけではないので、大手企業に固執するほどではないと思います。
②労働時間が長く、教育環境が整備されていない
労働時間の長さに関しては、大手企業、ベンチャー企業という区分に問わず、残業が多い会社は多いです。
ただ、ベンチャー企業は大手企業と比較して、会社として生存していけるかどうかという部分があるので、
大手企業と比較すると、労働時間が長い会社が多いのかもしれません。
ただ、「ベンチャー企業=労働時間が長い」ではないということは理解しておいてください。
教育環境に関しては、何をもって十分とするかと画一化をどう捉えるかの2つが議論のポイントになりそうです。
何をもって十分とするかについては、企業が従業員を教育する理由は「成果を出してもらいたいから」だと思います。
そこで、企業に対して教育をしてもらわなければ成果を出さないというスタンスになると、
自分で努力して成果を出す人がいた場合、努力して成果を出してくれる人を企業は評価するでしょう。
成果を出さなければ、評価をされないのは当たり前のことなので、従業員として働く以上、評価をしてもらいたければ、
教育環境の有無にかかわらず、成果を出すために頑張るしかないのです。
また、大手企業であれば、教育環境が整備されているというのは、多くの従業員に対して一定のスキルを持ってもらうための画一化されたプログラムだと思った方が良いでしょう。新入社員が数百名といる企業で1人1人のレベルに合わせた教育プログラムを考えることは難しいので、全員に共通した教育プログラムを提供することになります。
そこで、もっと学びたいと思ったときに、周りに合わせる必要があるため、もどかしさを感じる人もいるかもしれません。
それに対し、ベンチャー企業では、1人1人が最大限のパフォーマンスを発揮できるように、できる人にはどんどん仕事(学習機会)を与えてもらえます。
教育環境があると一概に言っても、見方によって捉え方は変わることを知っておくと良いでしょう。
③給料が低く、経営が安定していない
給料については、ベンチャー企業は大手企業と比較すると、初任給や初年度の給料は少し見劣りするかもしれません。
しかし、ベンチャー企業でも、成果を出せば若くして昇格・昇給していけるケースもあるので、
「ベンチャー企業=給料が低い」というのは長期的に比べてみないと分からないかもしれません。
ベンチャー企業の実際の給料については、別記事で公開予定ですので、お楽しみに!
経営基盤については、大手企業ほど安定していないというのは事実あると思います。
しかし、今の時代、会社が倒産したら他の企業のどこで働くこともできないということはないと思います。
大手企業であれば、スキルを身につけなくても、働き続けることができるかもしれませんが、
他の会社で働くことができないような会社依存の状態にならないように注意する必要があります。
ベンチャー企業でも、「もし会社がつぶれたら他の会社に行けばいい」くらいの気持ちで、
会社でしっかりと働いていれば、雇用先は見つかると思います。

総じて、「ベンチャー企業はやめとけ」というのは一理あるものの、大手企業でだらだらと働くくらいであれば、ベンチャー企業でしっかりとスキルを身に着ける方が何かあったときもキャリアとして自立した状態になることができると思います。
妻が新卒でベンチャー企業に入社した実際の体験談を書いていますので、気になる方はぜひ読んでみてください。
また、どんな人はベンチャー企業が向いていないのか、活躍できる人はどんな人なのかについてもまとめていますので、こちらもご参考にしてみてください。
3. ベンチャー企業で身につくスキル

ここまで読んで、ベンチャー企業に入社するのが不安になっている方向けに、実際に新卒でベンチャー企業に入社して営業を中心として活動してきて、身に付いたスキルをお伝えします。実際の業務内容を抽象化してお伝えするので、それぞれの内容についてより詳しく知りたいという方はコメントいただければ、別の記事にてお伝えしようと思います。
サービスを販売する全体像がわかる
- お客様を集める方法はどうするか?
- 集めたお客様に対する営業活動はどうするか?
- 購入後のオンボーディングはどうするか?
サービスを企画する全体像がわかる
- 会社としてそのサービスをやる意義はあるのか?
- 誰にどんな価値をいくらで届けるのか?
- そのサービスを欲しがる人はどのくらいいるのか?
- 提供条件や提供方法、発注/支払方法はどうするのか?
- サポート体制や利用規約はどうするのか?
他の企業との協業の進め方がわかる
- 両社にとってWin-Winな仕組みがつくれているか?
- ビジネスのシナジーはあるか?
- お互いの強みは何か?
- 研究・開発・マーケティング・営業のどこで連携をするか?
- 協業を推進する社内の動機づけはできているか?
4. 会社選びで後悔しないようにするための3ステップ

新卒でベンチャー企業を選ぶとしても、大手企業を選ぶとしても、
後悔しないようにするためのポイントをお伝えしておきます。
①自分の理想の生活を明確にする
社会人になったときに、どんな生活をしたいか、今後3年、5年、10年でいつまでに何をしていたいかを考えてみましょう。
そして、考えた内容は「なぜそう思ったのか?」の理由まで明確にしておくことで、解像度が高まります。
この際、自分が何よりも大事にしたいものや価値観までしっかりと押さえておけると、
将来的に計画が変わった時でも立ち返ることができます。
②考慮する必要のある項目を明確にして優先順位をつける
①で考えた理想の生活を実現するために、考えなくてはいけない項目が出てくると思います。
まずは抜け漏れがあっても問題ないので、考えて書き出して整理していくことが重要です。
例えば、30歳までに結婚したい → 子供が欲しいのと老後も一緒に暮らしたいから同年代がいい
→結婚する前に同棲をしておきたいから、27歳くらいまでには彼女を作っておきたい
→若いうちは仕事も頑張りたいから、25歳までは仕事を全力で頑張って、そこから2年間で恋人探しの余裕が欲しい
→30歳くらいまではそんなに稼げなくてもいいけど、結婚したら子育ても考えてお金の余裕が欲しい
このように考えることで、22歳で社会人になる場合は、最初の3年間は頑張って働ける環境であること、
そこからプライベートも視野に入れて、両立を目指せそうな環境であること、
どの年代で子供が生まれている人が多いか、給与の上がり方はどうか、など
その会社で働き続けることができるかどうかのイメージをつけることができます。
むしろ、この場合3年で転職すると割り切って、最初にハードワークの会社を選ぶのもありだと思います。
しかし、自分が理想とするシナリオをすべて叶えることができる会社を探すのは難しいと思います。
そのため、自分が妥協できる範囲を考えるためにも優先順位をつけておくことで、
意思決定をする際の判断基準が明確になります。
③自分の意思決定を信じて行動する
入社する会社を決めた後は、自分の意思決定を信じて、行動をしましょう。
ずっと悩んでいても、前には進めません。行動をすることで、自分の意思決定を間違いじゃなかったと思えるように、
行動していくことが何よりも重要です。
5. 良い企業の見分け方

では、出会った企業が良い企業なのかを見分ける方法はどうしたらいいのか?を知りたいという方向けに、どのようにして良い企業と判断したらいいのかをお伝えします。
自分の判断基準で企業を選ぶ
世の中には、「〇〇な企業が良い企業です」という説明もありますが、それは本当にあなたにとって良い企業ですか?
良い企業というのは、誰にとって良い企業なのかによって、基準が変わります。
そのため、自分の判断基準で良いと思った企業を選ぶ以外、誰かにとっての良い企業を選んでいることに過ぎないので、
自分にとって良い企業なのかどうかを判断することはできません。
6. 最後に
新卒でベンチャー企業を選ぶのはもったいないのかについてまとめると
- 結論、一理あるが、見方次第で捉え方は変わる!
- 前提となるベンチャー企業と大手企業の違いは曖昧である
- 良い企業の判断は自分でしか決めることはできないため、世の中の言葉に惑わされる必要はない
となります。

新しい物事にチャレンジするのは、誰だって勇気がいることです。
自分の実体験が、少しでも皆さんの心を軽くしたり、背中をそっと押すものになることができたら嬉しいです。
このサイトでは、後輩を応援したいという気持ちで、これからもさまざまな記事を執筆していきますので、ぜひご覧ください。
 わたしたちについて
わたしたちについて
またこのブログでは、他にもキャリアについて記事を執筆していますので、ぜひ併せてご覧ください。