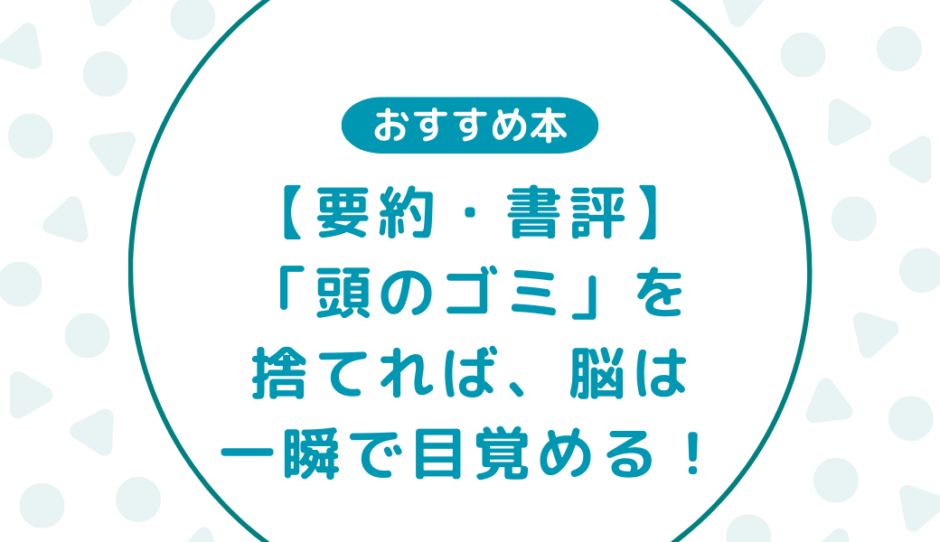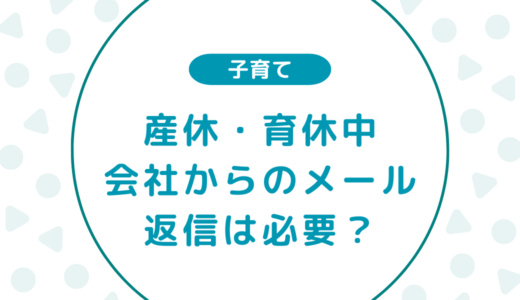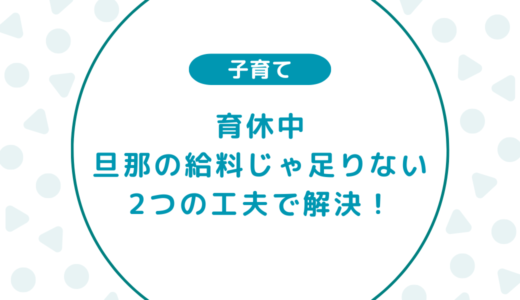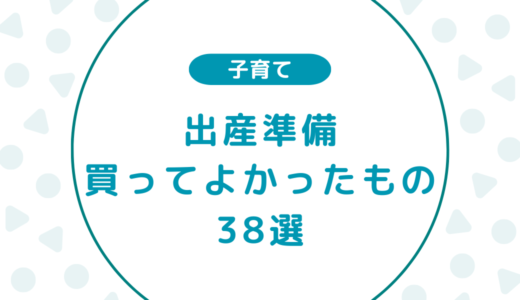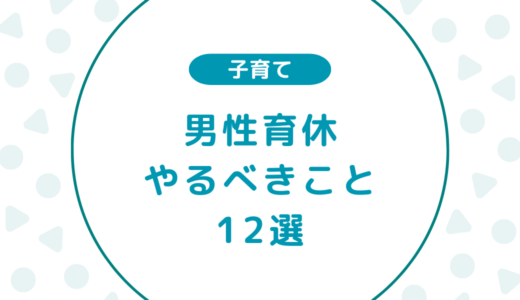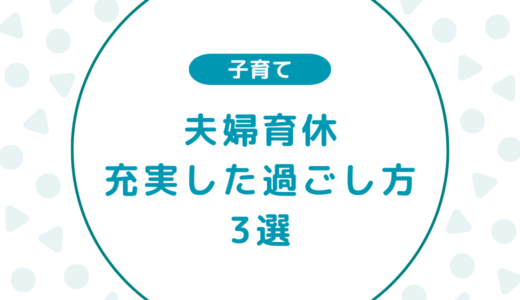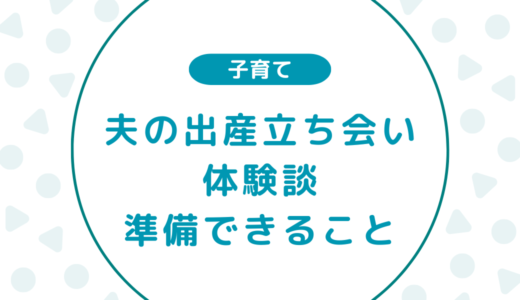この記事では、
- 「『頭のゴミ』を捨てれば、脳は一瞬で目覚める!」の本ではどんな内容が読めるのかを知りたい
- 自分はこの本を読むべきなのか知りたい
という方に向けて、
- 本の要約
- 実際に自分が抱いた感想
についてお伝えします。

まるで1個上の先輩とサシ飲みに行ったかのように、「有益な情報が得られた」「心が少し軽くなった」「また明日から頑張ろう」、そんな気持ちになっていただけたら嬉しいです。
書籍の基本情報
第1章:イライラ、怒り、嫉妬…生産性を下げる「感情のゴミ」を捨てる
第1章の要約
- 感情に振り回されない。
- 抽象度を高めることで、俯瞰する
- 心から望むゴールを設定して、ゴール達成に関係のない感情は捨てる
第1章の感想
第1章では「途中にある幸福感を目的としない。あくまでもゴールを達成する途中に幸福感がある」という考え方が非常にタメになりました。
「ゴールを見誤らないようにする」というのは、大事なことでありつつ、ついつい忘れがちなことなので、気を付けなくてはならないなと改めて思わされました。
一時の感情に振り回されずに、人生を俯瞰してみていきたい、と第1章を読んで思わされました。
第2章:満たされなさと焦燥感…「他人のモノサシ」というゴミを捨てる
第2章の要約
- 自分は他者との関係にまつわる情報でできている
- 人間は、自分にとって重要なものだけに意識を向けている
- 本音で考える。自分にウソをつかず、自分の理想を考える。
- 自分のモノサシで価値を測り、他人と比較しない。
第2章の感想
第2章では「重要という判断材料すらも、外部情報の影響を受けている。」という考え方が非常に参考になりました。
個人的には、他者の影響を受けて自分の価値観が形成されることは悪いことではなく、一つの人生としてすごく魅力的だなと思いますが、重要なのは、その中に自分の軸を持つことなのだろうなと思わされました。
世の中には色んなモノサシがあるが、迷わず、自分の軸で判断をしていこうと改めて思わされました。
第3章:変わりたいけど変われない…「これまでの自分」というゴミを捨てる
第3章の要約
- 過去は変えられないが、未来は変えられる
- 脳は、恒常性維持機能を持つため、現状維持をしてしまいやすい
- 過去が未来をつくるという思考ではなく、未来が過去をつくるという思考へ
第3章の感想
第3章では、「これまでの行動をリセットして、新たな行動を起こす。良い未来を描いて、行動すれば未来から見た過去も良いものになるはず」という考え方が非常に参考になりました。
これまで自分は「過去の行動が未来の自分を作る」と考えていたのですが、それが第3章でひっくり返されました。
良い未来を描き、それを軸にして考えることで、今を良いものにしていく。
脳の恒常性維持の基準を未来に持っていくことで、そちらに引っ張られるようにしていきたい、と思わされました。
第4章:自分に自信が持てない…「マイナスの自己イメージ」というゴミを捨てる
第4章の要約
- 世界は言語で成り立っている。ポジティブな自己対話よりもネガティブな自己対話が多い。
- ネガティブな自己対話は自己イメージをマイナスにする。
- 自己評価は子供の頃から聞かされてきた言葉で作られる。
- 失敗体験は捨てて、ポジティブな自己対話をする。失敗は学習と成長の機会と捉える。
- 自己評価を高めることで、できない理由を無くす。
- 他人はあなたの過去しか見ていない。夢を潰す他人の声は無視して、自らを拠り所とする。
第4章の感想
第4章では「自己評価が低いと、できない理由ばかりを意識してしまい、自分の未来を描く上で、一番の障壁が自分となってしまう。」という考え方が非常に参考になりました。
自分自身はポジティブ思考な人間なので、親に良い育て方をしてもらったのかなと思うことができました。
できる理由だけを考えて、学習と成長を繰り返して進んでいきたいなと改めて思わされました。
第5章:「なりたい自分」になるためにまずは「我慢」というゴミを捨てる
第5章の要約
- have to ではなく、want to
- やりたくないことをやめてもどうにかなる
第5章の感想
第5章では、自分が日常の中でどれだけhave toと考えてしまっているかを考えさせられました。
「~しなければいけない」という発想では、それらはやろうとしても結局パフォーマンスが上がらないので、そういった考えは無くし、やりたいことをやろうと思うことができました。
第6章:やりたいことが分からない…「自分中心」というゴミを捨てる
第6章の要約
- これまでの内容にある要らないものを捨てて、本当に必要なものが何かを考える
- ゴールについて考えることは自分にとっての幸福とは何かを考えること
- 幸せになるためには、自分だけが幸せになるということはない
- やりたいことを見つけるためには、何をすれば他人が喜んでくれるか?を考える
- コンフォートゾーンの外側にゴールを設定し、そのゴールの解像度を高める
第6章の感想
第6章では「自分にとっての幸せは何か?」「それを実現するための具体的な方法は何か?」を考えさせられました。
自分にとっての幸せを実現するということは、周囲の人に影響を与えることにもなるという考え方が新鮮でした。
また、本音であればそれが「want to」となる、というのは考え方の参考になりました。
また、自分にとっての幸せを実現するためには、恒常性維持から抜け出すためにも、コンフォートゾーンの外の状況をいかに臨場感高い状態でイメージすることができるかが重要であるとわかり、身が引き締まりました。
第7章:失敗するのが怖い…「恐怖」というゴミを捨てる
第7章の要約
- 感じている恐怖のほとんどは思い込み
- 失敗は最高の人生を手に入れる過程で考えれば、必要な学習と成長の機会だったと捉える
- 怖がっているヒマがあれば、行動すればいい
第7章の感想
第7章では、恐怖というネガティブ思考をポジティブ思考に変えることの重要さを学びました。
恐怖は前に進むための行動意欲を阻害するため、恐怖と捉えず「学習と成長の機会」と考え、行動するのみ、という考え方に、非常に納得しました。
第8章:「論理へのとらわれ」というゴミを捨て「ひらめき脳」を手に入れる
第8章の要約
- 全体を理解することで、部分を捉える
- 全体俯瞰と細部へのフォーカスを行き来できるようにする
- 抽象度を上げて物事を捉えられるようにすることで、全体と細部の関係性を認識する力を高める
- 全体と細部の関係性を捉える力をつけることで、些細なことからひらめきが生まれるようになる
- 興味を持って、知識を取り入れる
第8章の感想
第8章では、細部にとらわれず全体を俯瞰して捉えることの重要性を学びました。
「細部と全体の行き来をスムーズにできるようになることで、様々な事象との結びつけが出来るようになる。それに必要な知識をつけるためにも、自分のやりたいことを明確にして興味を持った分野に触れることが重要になる。」という考え方が非常に参考になりました。
最後に
以上、「『頭のゴミ』を捨てれば、脳は一瞬で目覚める!」の要約と感想をご紹介しました。
まとめると、捨てるべきものは
- 「感情のゴミ」
- 他人のモノサシ
- これまでの自分
- マイナスの自己イメージ
- 我慢
- 自分中心
- 恐怖
- 論理へのとらわれ
となります。
この本を読み、自分の頭の中にどれだけ「ゴミ」となるものが溜まっていたのかを思い知らされました。
本記事を読み、この本に興味を持たれた方は、ぜひ読んでみてくださいね!

新しい物事にチャレンジするのは、誰だって勇気がいることです。
自分の実体験が、少しでも皆さんの心を軽くしたり、背中をそっと押すものになることができたら嬉しいです。
このサイトでは、後輩を応援したいという気持ちで、これからもさまざまな記事を執筆していきますので、ぜひご覧ください。
 わたしたちについて
わたしたちについて
またこのブログでは、他にもキャリア・おすすめ本について記事を執筆していますので、ぜひ併せてご覧ください。