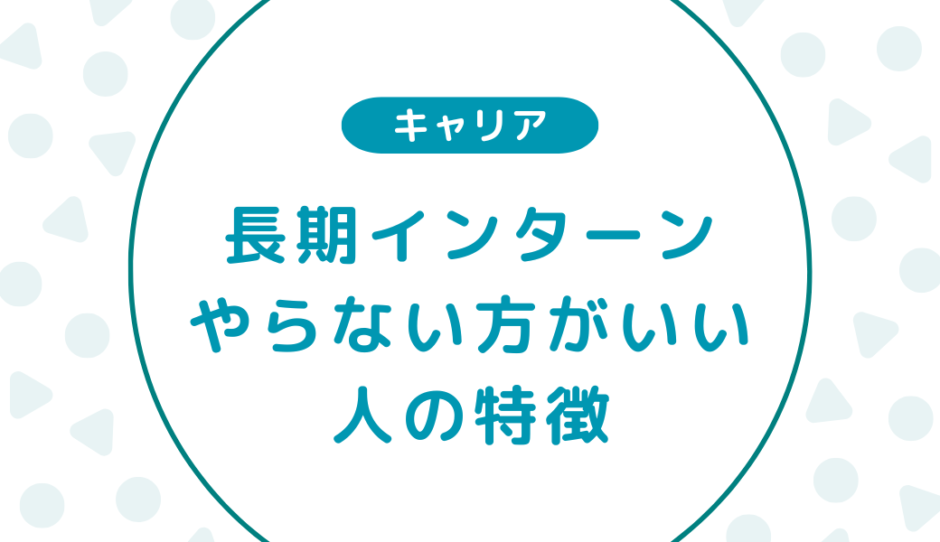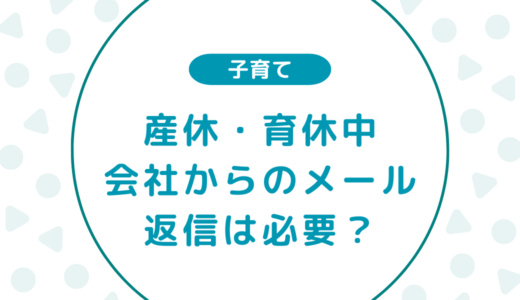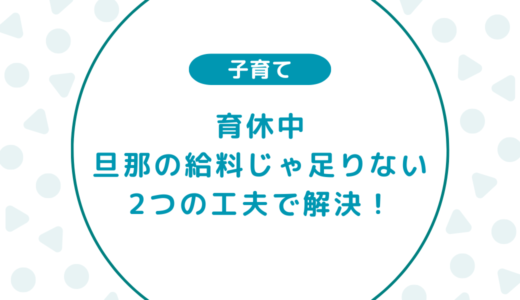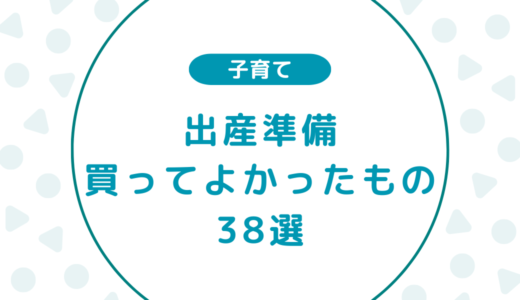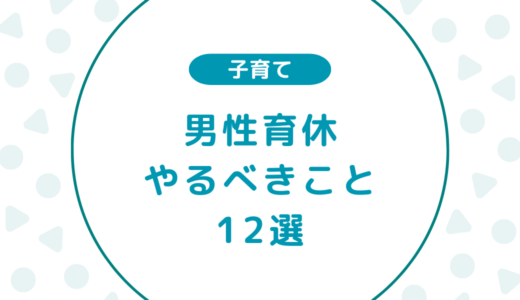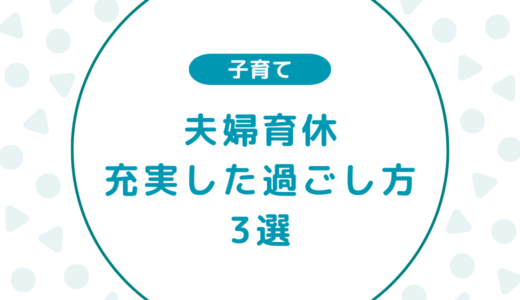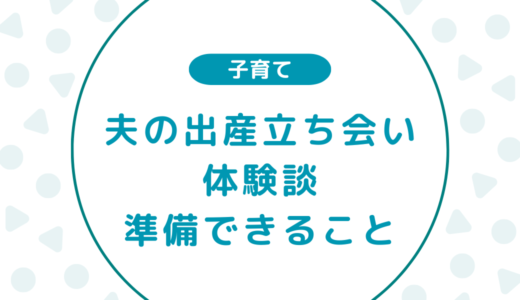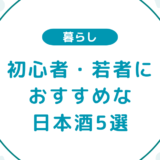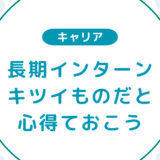この記事では、
- 「就活に備えて長期インターンをしようか迷っている」
- 「けど長期インターンってなんとなく大変そう。するべきかどうかいろんな意見を知りたい」
という方に向けて、
- 「こんな人は長期インターンをやってもいいと思う」「こんな人は長期インターンはしない方がいい」
- 長期インターンで実際に成果を出す人とはどんな人か
について、実体験ベースでお伝えします。

まるで1個上の先輩とサシ飲みに行ったかのように、「有益な情報が得られた」「心が少し軽くなった」「また明日から頑張ろう」、そんな気持ちになっていただけたら嬉しいです。
1. 前提:私の会社の特徴、私の長期インターン生マネジメント経験

私は「長期インターンをしていた大学生」側ではなく、「長期インターン生をマネジメントしていた担当社員」側の人間になります。
以下、私の勤めている会社、および私の長期インターン生のマネジメント経験の前提についてお伝えします。
私の会社の特徴
私が勤めている会社は、数十年前に社長が「学生起業」で立ち上げた会社になっています。
そのため、現役大学生を巻き込み一緒にビジネスを作り上げていくという「文化」が根付いている会社でした。
最近では「長期インターン」という言葉も一般的なものになってきましたが、
私の会社では、「長期インターン」という言葉がまだ一般的ではなかった頃から、少なくとも10年以上前からは、長期インターン生の受け入れを行っていました。
が、そんな私の会社も、今後は長期インターン生の採用を見送る方針で動きつつあります。
理由は以下の通りです。
- 「長期インターン生の質が下がっている」こと。
- 長期インターン生を受け入れていたのは、「学生起業」の流れを汲んだただの「文化」であって、そこに明確なビジネス的なメリットが何もないこと
まず、会社が長期インターン生を採用する理由には、以下のようなものがあると考えられます。
- ①扱っているサービスが大学生向けのものであるため、学生内のコネクションや知恵を借りたい(就活サービス系等)
- ②「学生運営」を打ち出すことで共感や同情を誘うことができそうな商材を扱っている(地方創生系等)
- ③長期インターンから新卒採用に繋げたい
- ④販管費の削減
私の会社が長期インターン生を受け入れていたのは、「学生起業」の流れを汲んだただの「文化」であったため、上記①〜③のどの理由にも当てはまっていない状態でした。
せっかく手間暇かけて学生を育てたとしても、4年経ったら学生は卒業してしまい、会社には何も残らないため、本当に「慈善活動」のような形になっていました。
強いて言うなら「④販管費の削減」のメリットが享受できていたくらいです。
それでもやはり、「手間暇かけて育てた学生が、一人前のビジネスパーソンとして成長し、社会に羽ばたいていく姿を見れる」ということに、一定の「エモさ」を感じられるため、
ここまで「長期インターン生を受け入れる」という「文化」が継続されてきていました。
しかしそれも、最近になって事情が変わってきました。
経営陣・マネジメント社員が口を揃えていっているのが「長期インターン生の質が下がった」ということです。
後述しますが、「ビジネスの現場で実践経験を積みたい」という明確な意志を持って長期インターンに臨んでいる学生が減り
- 周りの友人が長期インターンをし始めたから、自分もなんとなく
- 長期インターンをしている方が就活に有利になると聞いた
といった、ふわふわな理由で長期インターンを始める人が増え、
そういった人は「長期インターンに参加することがゴール」になっているため、もちろん業務で大した成果を出すこともなく、
結果ただチームのお荷物になっているだけ、マネジメントの工数が無駄に増える、という状況が度々見られるようにました。
- 長期インターン生を受け入れることにビジネス的なメリットがなく
- 且つ長期インターン生の質もそこまで高くなく、マネジメントの工数を無駄に増やしているだけ
ともなれば、「長期インターン生の受け入れはもうやめようか」となるのは必然の話です。
私の長期インターン生のマネジメント経験
とは言いつつ、これまで十数年続いていた「長期インターン生と共にビジネスを作り上げていく文化」を、いきなり数日で断ち切れるわけでもないため、
新たな人材の確保方法を検討し、実行に移すまでの数年間の間は、私の会社でも引き続き「長期インターン生」の受け入れを続けていくことになります。
私はちょうどその「過渡期」の時期に、長期インターン生のマネジメントを数年間担当することになりました。
私がマネジメントしていた長期インターン生の状況は、以下の通りです。
- 【長期インターン生に任せていた仕事】
・SEOライティング、SEO戦略・戦術の作成
・Webサイトの数値分析
・後輩のマネジメント - 【勤務条件】
・月50時間以上働くことが必須
・卒業まで働くことが必須
・フルリモート - 【私がマネジメントしていた長期インターン生の在籍大学】
・東大生・京大生・慶應生・東工大生・その他複数大学
以上の前提をもとに、以降では私のマネジメントの実体験をもとに「こんな人は長期インターンはやめておいた方がいい」と思う学生について、述べていきたいと思います。
2. こんな人は長期インターンやめとけ。長期インターンで成果を出せていなかった学生の特徴

ここからは「長期インターンで成果を出すことができていなかった学生」の特徴を解説します。
長期インターンは「教育機関」ではなく、「ビジネス」の場です。
会社として給料を支払っている以上、長期インターン生にも厳しくコミットメント・成果を求めることになります。
ビジネスマナーもついていない、就活も経ていない大学生を、卒業までの数年間に会社で成果が出せるレベルまで育成をしなければいけないため、当然社員からのフィードバックは厳しいものにならざるを得ません。
かけた教育コストに見合わずいつまで経っても成果を出すことがない、うだつが上がらない状態でダラダラと働いているような学生は、
- 社員から日々きついフィードバックを受けることになる
- 周りの長期インターン生からも冷めた目で見られる
- いつまで経っても、評価・時給が上がらない
- 明らかに「チームのお荷物」感が漂っている
という状態になり、会社・本人の双方にとってよろしくない状態になっていきます。
ですので、よほどの覚悟がない人は、長期インターンの世界に安易に足を踏み入れることはしない方が良いと、個人的には思っています。
以下では、どのような学生が長期インターンで成果を出すことができていなかったか、について述べていきます。
①長期インターンでどんな経験・スキルを得たいのか、目的意識のない学生
まず第一に「長期インターンを通してどんな経験・スキルを得たいのか」を明確に持つことなく、ただなんとなくで長期インターンを続けていた学生は、成果を出すことができていませんでした。
目的意識のない学生とは、例えば以下のような学生のことを指します。
- 「ガクチカに書くネタを作りたい、就活を有利に進めたい」という理由で長期インターンに参加している学生
- 「責任感・主体性を身につけたい」「意識が高い人に囲まれることで自分の姿勢を正したい」などマインド面の話しか出てこない学生
- 「パソコンを使いこなせるようになりたい」など、手段・テクニックの部分の話しか出てこない学生
有名大学に在籍している学生だと地頭がよいため、明確な目的意識がなくてもある程度のところまではそつなくこなし成果を一定出すこともあるのですが、
それでも一定レベルのところで必ず頭打ちになり、明確な目的意識を持って働いている人にどんどん抜かされていく、となるのがオチでした。
「どんな経験を積めば、就活を有利に進められるのか」について自分なりに仮説を持ち、その経験を得るための手段の一つとして長期インターンを検討している、というのであれば問題ないのですが、
「長期インターンに参加すれば就活に有利になる『らしい』から」という、自分の頭で考えることなく周りの意見・噂に流されてただただなんとなく長期インターンをやっている、という人は、
- 長期インターンに参加することがゴール
- 仕事を振られても基本受け身
- 厳しいフィードバックを受けたらすぐに凹んでやる気をなくす
という姿勢であることが大半なため、成果を出すことができず、結果大したガクチカを書くことすらもできていませんでした。
「責任感」「主体性」は一見するとそれっぽいワード・目的のように思うかも知れませんが、
「責任感」「主体性」というのはマインドの話であり、身につけようと思えば、今すぐにでも心を切り替えて身につけることができるものです。
またビジネスの現場に立つにあたっては、「責任感」「主体性」といったマインドは、最初から持っておくべき大前提の最低条件になります。
それを「数年かけて身につけたい」と言っている時点で、あまりに視座が低いと言わざるを得ませんし、大抵そういう人は、最後まで「責任感」「主体性」が身につくことがなかったように思います。
また「意識が高い人に囲まれることで自分の姿勢を正したい」についても
自分の力で自分を正す意志の強さがない時点で、厳しいビジネスの世界で通用することはまずなく、
結果、チームの中で「できない人ポジション・キャラクター」を確立してしまい、それに慣れて甘んじるようになり、「自分の姿勢を正す」ことは全くできていない、となるのがオチでした。
- 「パソコンを使いこなせるようになりたい」
- 「マーケティング力・営業力をつけたい」
などはどれも、あくまで何か「目的」を達成するための一つの「手段」でしかありません。
「その手段を用いて、どのような目的を達成したいのか」がないままに、ただ「手段」となるテクニックの部分だけを磨いても、
- 目的意識がないため、そもそものインプットの量が少なくなりがち
- 適切なアウトプットの場を自分で作り出すことができないため、腹落ちさせづらい
- こんなに辛い思いをしてこんなスキルを身につけたところで何になるんだろうと、虚しさを感じがちになる
などの状態になり、これもまた成果を出すことはできていませんでした。
②受け身の姿勢の学生
- 受けたフィードバックの内容をメモに取らない
- むしろ社員からフィードバックを受けることを避けようとする
- 「教えてもらってないからわからない」とわからないことについて他責にし、いつまでも放置しようとする
- ミーティングの日程調整にいつまでも回答しない、毎回リマインドされてからでないと動かない
- 「自分にはまだ仕事が多く振られていないので、働く時間もそこまで多く確保はしていないです」という学生
当たり前ですが、こういった「受け身」の姿勢の学生が成果を出すことはありませんでした。
「長期インターンに参加しておいて、上記のような状態になる学生なんて存在するのか?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
ただどんな有名大学に在籍をしていようが、「①長期インターンでどんな経験・スキルを得たいのか、目的意識のない学生」だと特に、上記のような学生は一定数いました。
③変に斜に構えている学生
- これくらいわかります
- こんな作業、自分がやるものではないと思うんですけど
- この仕事正直興味ないんですよね
- この会社ってこういうところがイケてないですよね
長期インターンをしようというくらい意欲がある学生なので、やはり上記のような変に斜に構えた姿勢の学生も一定数存在します。
しかし上記のような、頭でっかちで斜に構えていて謎に上から目線の学生も、もちろん成果を出せることはありませんでした。
大抵こういう学生は、大して他の学生とスキルに差があることはなく、むしろいつも口だけで行動することがないため、他の学生よりもスキルが劣っていることの方が多い、というのが実際でした。
④長期インターンに多くの時間を割くことができない学生
- 「長期インターン」も「アルバイト」も
「部活・サークル」も「学業」も
「就活」も「ビジネスコンテスト」も
「ボランティア」も「留学」も、、、全て頑張りたいです!
長期インターンをしようというくらい意欲がある学生なので、やはり上記のように「なんでも全部全力で頑張りたい」という考えを持っている学生は一定数存在します。
ただそういった学生は、結局「全部が中途半端。どれも納得いく結果を出すことができないもどかしさ」に押しつぶされてキャパオーバーになり、
ある日突然糸がプチンと切れたように連絡がとれなくなってしまう、ということが多かったです。
基本的にビジネススキルというのは一朝一夕で身につくものではないため、スキルを身につけるためには多くの時間を長期インターンに割く必要があります。
長期インターンをするのであれば、他の活動の何か一つは諦めることになる、と思っておくくらいがちょうどいいですし、
逆にそれくらいの覚悟がないのであれば、長期インターンを安易に検討することはしない方が良いでしょう。
3. 長期インターンで成果を出すことができていた学生の特徴

続いて、長期インターンで成果を出すことができていた学生の特徴を解説いたします。
では逆に、「長期インターンで成果を出すことができていた学生」「長期インターンの経験を自分の人生にとって有意義なものにすることができていた学生」というのは、どういう人なのでしょうか。
それは一言で言えば、「長期インターンで成果を出せていなかった学生の特徴」を裏返したような特徴の学生になります。
厳しいようですが、以下のような行動をとることができないのであれば、長期インターンをしてもただ苦しい時間を過ごすだけになると思われるため、
長期インターンへの参加はやめておいた方が良いでしょう。
①長期インターンでどんな経験・スキルを得たいのか、明確に目的意識がある学生
- 将来起業を考えているため、ビジネスの全体像を把握できる場所に身を置き、事業計画や戦略を作れるようになりたい。
- マーケティングについて一通りの知識を身につけ、自分の力で商品を作り出し、売りだすことができるようになりたい。
- SEOの知識・Webライティングの力を身につけることで、自分でブログ立ち上げ・収益化できるようになり、それで生きていけるようになりたい。
- 将来は学校の先生になる予定だが、一通りのビジネススキルを持った上で先生になり、それを校務の現場に活かしたい。
上記のように、明確に「自分の人生をこういうふうに進めていくために、長期インターンという場でこういう経験・スキルを得たい」と目的意識を持っていた人は
ちょっとやそっとのことでは折れず、社員からのフィードバックもどんどん吸収して、成果を出していっていました。
②積極性のある学生
- 今のチームはこういうところが課題だと思うので、こういうことをしてみたらいいと思うんですけど、どうですか
- こんなふうに後輩を巻き込んで、チームの課題点を洗い出してみました
- ここの部分についてもっと知りたい、スキルを伸ばしたいと思って、書籍を買って自分で勉強してみました
- 自分が得た学びをみんなにもシェアしたいと思って、スライドを作ってきました
上記のように、「自分から積極的に新しい仕事を生み出していく」「積極的に周りに働きかけ巻き込んでいく」といった姿勢の学生は、
自分に降りかかってきたさまざまなチャンスをものにし、どんどん成果を出していっていました。
「新しい仕事を生み出す」というのも、「何か仕事があればください」ではダメで、
「こういうことを新しくやるのはどうですか」と、言われるまでもなく自分から課題点・解決策を考えて動き出すという姿勢がある人が、成果を出していました。
③素直さ・愚直さがある学生
- 自分にはまだまだ足りていないところがたくさんあると思うので、そういった点は遠慮なく指摘してください
- こんな資料を自分なりに作ってみたんですけど、もっとより良くするためにフィードバックいただけませんか
上記のように、「きついフィードバックを受けることから逃げない」「積極的に社員にフィードバックをもらいにいく」といった学生は、やはりぐんぐん成長をし成果を出していました。
特に個人的には、「自分にはまだまだ足りていないところがたくさんあると思うので、そういった点は遠慮なく指摘してください」と言ってくる学生には痺れました。
このセリフが言える人って、社会人でもなかなかいないと思っています。私も、私の上司に対してこのセリフを言えるかどうかと言われると、ちょっと怪しいです。
④長期インターンに多くの時間を割いていた学生
これは結果論だと思いますが、長期インターンで成果を出している学生は、1ヶ月の勤務時間が70〜80時間以上、多い人だと100時間を超えている、ということが多かったです。
4. そもそも長期インターンは行うべきものなのか?

ここからは、そもそも大学生は長期インターンをするべきなのかどうかについて、私が個人的に思っていることをお伝えします。
就活には有利になるが、入社後に有利になるとは限らない
確かに巷で言われているように、長期インターンを行なっていると就活に有利になるケースが多いと、私も考えています。
実際私の会社で長期インターンをしていた大学生は、ことごとく日系大手・外資系コンサルなどの名だたる企業に就職していきました。
また入社後のスタートダッシュも、一時的にはうまく切れることが多いでしょう。
が「入社して数ヶ月経った後」については、「他の同期とトントン。むしろ長期インターンをしていなかった人の方が伸びている」というケースが多いように感じています。
理由は、
- 他の新卒社員とさほどスキルに差があるわけでもないのに
「自分は長期インターンをしていたから『わかっている』」「自分は『できる人間』なんだ」というように、
いつまでも変なプライドを持ち続けていたり、斜に構えていたり、変に上から目線な新卒社員なんて、
上司側からすると、シンプルに扱いづらい。社内でも普通に省られて終わるだけ。
というところだと考えています。
いくら長期インターンを数年間やっていたと言えども、そこでつけられる「差」というものは、長いビジネスパーソン人生から見ると、たかが知れています。
それをわかっておらず、いつまでも「長期インターンをやっていた」という事実にあぐらをかき、変に斜に構えている学生よりも
「自分何もわかっていないので、たくさん教えてください!」と、スポンジのように「素直に」「愚直に」知識・技能を吸収していく他の新卒社員の方が、上司にも可愛がられるし、ぐんぐん伸びて成長していく、というのはよく見る光景です。
「いやいや自分は長期インターンをしたからって、そんな天狗になることなんてない」と思う学生の方もいらっしゃるかもしれません。
しかし前述の通り、長期インターンをしていることで、就活に有利になったり、入社後のスタートダッシュも一時的にはうまく切れるケースが多くなることは確かで、
「他の学生よりも自分の方ができている」という期間が、事実として一定期間続くことになります。
そうすると、本当に驚くくらい、無自覚にも「自分は『優秀』な人間なんだ」と錯覚し天狗になるケースが、本当に本当に多くなります。
しかし再度になりますが、長期インターンを数年やっていた程度でつけられる「差」というのは、本当にたかが知れています。一瞬で他の同期に追いつかれ追い越されるのです。
実際私の会社で「長期インターンからの新卒採用」を行っていなかった理由は、上記のケースが非常に多いからです。
焦って長期インターンをするくらいなら、別のことで大学生活を充実させた方がよい
「『いち早く』ビジネスの現場に入ってみたい」など明確で強い意志があって長期インターンを検討するのであれば、それは良いと思います。
ただ「なんとなく、やったほうがいいのかなと思って」という理由で長期インターンを検討しているのであれば、
私は「焦って長期インターンをするくらいなら、別のことで大学生活を充実させた方がよい」とアドバイスをしたいです。
長期インターン生を採用・マネジメントしておいてなんですが、個人的には、大学生のうちは大学生のうちでしかできないことに時間を使った方が良いと考えています。
ビジネスというのは、社会人になってからでもいくらでも腐るほどできます。
それよりは
- 学問を徹底的に探求する。アカデミアの世界にとことん浸かる。
- サークル活動などで、本当に自分が大好きなものにとことん打ち込んでみる
- 各所に旅行に行き、さまざまな文化の人と触れ合う
- さまざまなアルバイトをしてみて、世の中にはこんな仕事もあるんだ、こんな働き方・生活をしている人もいるんだと知る
- NPOなどでボランティアをする
といった経験をさまざまに積む方が、その人の「深み」に繋がり、社会人人生を長いスパンで見た時に、むしろいわゆる「有利」になると考えています。
昨今は本当に、大学生を対象にした「長期インターンビジネス」「就活ビジネス」が非常に流行っています。
「長期インターンビジネス」「就活ビジネス」の営業トークに踊らされて、自分の人生を見失わないように気をつけてください。
5. 最後に
長期インターンで成果を出せていなかった学生の特徴をまとめると
となります。

新しい物事にチャレンジするのは、誰だって勇気がいることです。
自分の実体験が、少しでも皆さんの心を軽くしたり、背中をそっと押すものになることができたら嬉しいです。
このサイトでは、後輩を応援したいという気持ちで、これからもさまざまな記事を執筆していきますので、ぜひご覧ください。
 わたしたちについて
わたしたちについて
またこのブログでは、他にも長期インターン・キャリアについて記事を執筆していますので、ぜひ併せてご覧ください。