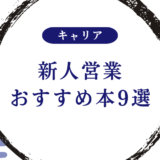この記事では、
- 「産休中、体調が良く時間がありそうなので、何か新しいことをやってみようと思っている」
- 「ブログを始めるのはどうかと思っており、他の人の体験談を知りたい」
という方に向けて、
- 私が産休中にブログでどのような活動をしていたか
- 産休中にブログを始めるメリット・コツ・注意点
について、自分も同じように不安になったり挫折した経験を踏まえ、実体験ベースでお伝えします。

まるで1個上の先輩とサシ飲みに行ったかのように、「有益な情報が得られた」「心が少し軽くなった」「また明日から頑張ろう」、そんな気持ちになっていただけたら嬉しいです。
1. 私が産休中に副業としてブログを始めた理由・きっかけ

まず、私がなぜ産休中に副業としてブログを始めることになったのか、そのきっかけ・理由についてご紹介いたします。
①夫が数年前にブログを開設したまま放置していた
元々「ブログを始めたい」と言い出したのは、私ではなく夫でした。
実は夫は新卒1年目の際、「本業の他にもお金を稼げるようになりたい」と一念発起し、ブログの開設を行なっていました。
しかし案の定、夫は本業が忙しくなっていき、ブログは1記事も書かれることなく、私が産休に入る数年後までずっと放置されてしまっていたという状態でした。
後述しますが、ブログを運営するにあたっては「レンタルサーバー」の契約を行う必要があります。
そのレンタルサーバー代だけが数万円毎年無駄に発生し続けているという状況であったため
夫と話し合った結果、「流石にレンタルサーバー代として払っている費用がもったいなさすぎる。せめて、かけた費用分はブログで収益を出して回収したい」ということになり、
私が産休に入ったことをきっかけに、再度本格的に腰を据えてブログ運営に取り組むことになりました。
②産休に入る前は「Webマーケター」として働いていた
「産休中にブログ運営を始めてみる」ということに私があまりハードルを感じなかった理由は、それまでの私の職種が「Webマーケター」であったということが大きく影響しています。
私は会社で
- サービスサイトの運営責任者
- コンテンツSEOの戦略・戦術作成
等、まさにブログ運営と近しい分野の業務を行なっていました。
(※私が新卒で入社してからどのような仕事を行っていたかについては、以下記事で別にまとめているため、ぜひ併せてご覧ください。)
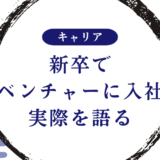 新卒ベンチャー入社の実際を語る|仕事内容・メリット・デメリット
新卒ベンチャー入社の実際を語る|仕事内容・メリット・デメリット
そのため、ブログ運営にあたって必要になる知識である「Webライティング」「SEO」「アフィリエイト」などについてはすでにノウハウを持っており
仕事の延長線上として、手軽な気持ちでブログ運営を始めることができたという経緯があります。
③キャリア復帰に向けて自分の頭を鈍らせないため
私は産休・育休併せて約1年半のお休みをいただく予定になっていました。
1年半も休んでいると、自分のスキル・性格上、復帰した時にはおそらく
- Webマーケ等、それまでの業務内容についての知識を忘れている
- シンプルに頭の回転が鈍っている
- 「前はもっとスムーズにバリバリ業務ができていたのに。なんだか今は頭に靄がかかったような状態に感じる」など、もどかしさやストレスを感じることになる
などが生じているだろうな、ということが容易に想像できました。
「ブログ運営」は「自分の考えを適切に言語化し、相手にわかりやすい形でアウトプットする」ことが求められるという性質を持っています。
そのため、「頭を鈍らせない」という目的で行うにはちょうど良いと個人的には感じており、せっかくなので産休・育休中に行なってみよう、と考えた次第です。
④収入源を増やしたいと思った
最後の理由はシンプルに「本業以外にも収入源を増やしたいと思った」というものです。
私は昔から「自分が子育てをするときは、子供に対してお金を理由に何かを諦めさせたり、お金に関する苦労をさせたくない」と考えていました。
しかし今の収入状態だと、例えば子供が「私立の学校に行きたい」と言ったとしてもそれを叶えるのはなかなかに難しそう、という状態でした。
自分の努力次第で家計の収入を増やすことができるなら、どんどんチャレンジしていきたいと思い、ブログ運営を始めるに至った次第です。
2. 前提:副業の種類

前述した内容以外にも、私が数ある「副業」の中であえて「ブログ」を選択したのには、いくつか理由があります。
以下ではそれを「そもそも副業とは?」という観点からご紹介いたします。
「副業」と一口に言っても、副業には大きく分けて
- フロー型
- ストック型
の2種類あります。以下では、それぞれの違いについてまず簡単にご説明いたします。
フロー型
フロー型とは、時間単価で稼ぐ副業や成果報酬型で稼ぐ副業のことを言います。具体的には、
- アルバイトのように企業と業務委託契約を結ぶもの
- クラウドワークスなどで単発で案件を獲得するもの
- Uber Eatsのように運んだ件数に応じてお金がもらえるもの
などを指します。
フロー型のメリットは、すぐにお金が得られることで、
逆にデメリットとしては、自分が働かないとお金を得ることができなくなることが挙げられます。
ストック型
ストック型とは、何かしらのコンテンツを通じて稼ぐ副業のことを言います。具体的には、
- ブログ運営
- SNS運営
- Youtube運営
など、コンテンツを蓄積していくことによる広告収入のような形でお金を得るものを指します。
ストック型のメリットは、コンテンツを蓄積していくことで、自分が働かなくてもお金を稼げる状態になれること、
逆にデメリットとしては、収益化までの道のりが長く、最初のうちはなかなかお金を稼ぐのが難しいことが挙げられます。
産休中の副業として「ストック型」であるブログを選択した理由
私が、産休中の副業として「ストック型」であるブログを選択した理由は
- 自分のペース・体調に合わせて進めることができる
というメリットがあったからです。
副業を始めると言ってもあくまで「産休中」のため、
- 後期つわり
- 腰痛・眠気・だるさ・胸やけなどのマイナートラブル
- 陣痛
など体の変化が多く発生します。
そんな中で、企業と業務委託契約等を結んで働く「フロー型」の副業を始めてしまうと、
- 突然体調が悪くなり、シフト通りに働けなくなる
などが起きてしまう可能性が十二分に考えられます。
実際私は臨月の際に一度「腎盂腎炎」になり、熱を出して数日ダウン、ブログ更新が2日間止まったということがありました。
しかし「ストック型」の副業であれば、あくまで自分1人で完結するものであるため、
自分が体調不良になったからといって、勤務できなくなったことを誰かにお詫びしたり、誰かにシフトの代打を頼むなどする必要はありません。
3. ブログでお金を稼ぐとは?

そもそも「ブログって副業になるの?」「ブログでどうお金を稼ぐの?」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
そこで以下では、ブログでお金を稼ぐ具体的な仕組みについて簡単にご説明いたします。
ブログ、つまり前述の「ストック型」の副業でお金を稼ぐ方法としては、大きく分けて以下2種類あります。
- ①「広告収入」でお金を稼ぐ
- ②「案件獲得」でお金を稼ぐ
①「広告収入」でお金を稼ぐ
王道なのがこちらの「広告収入」でお金を稼ぐやり方です。
広告収入には大きく分けて以下3種類あります。
- Googleアドセンスなどの「クリック報酬型広告」
- Amazonアソシエイト・楽天アフィリエイトなどの「物販」
- アフィリエイト広告
【参考】
・ブログで稼ぐ仕組みと具体的方法を公開!広告収入の大事な考え方も
よく「【使ってみた】〇〇商品のメリット・デメリットを徹底レビュー!」などのような記事を見かけたりしませんか?
あれは「その記事に貼られているリンクからその商品を買うと、ブログ運営者に一定金額の報酬が支払われる」という仕組みになっています。
また、よく読んでいる記事内に、そのサイトとは全く関係のない漫画や商品のバナー広告などが表示されていることはありませんか?
あれは、「その記事に貼られているバナー広告がクリックされると、ブログ運営者に一定金額の報酬が支払われる」という仕組みになっています。
②「案件獲得」でお金を稼ぐ
これは上級者編になりますが、例えば
- 自分で作ったハンドメイドなどの商品を売りたい
- 「Webデザイナー」「事業コンサルタント」として独立したい
などの際に、その宣伝のためにブログを運営し、認知度を広げ案件を獲得するという方法があります。
ただこれを目的としてブログ運営を行なっている人はかなりの少数派で、ほとんどの人は①の広告収入で稼いでいる状態です。
もしくは「①『広告収入』でお金を稼ぐ」でうまくいった人が、ブログ運営コンサルとしてさらに案件を獲得する、というケースが多くなっています。
4. 実際に私は産休中にブログでどのような活動をしたか

以下では、実際に私が産休に入ってから子供を産むまでに、どのようなブログ活動をしていたのかについて実例をご紹介いたします。
①ブログ開設の基本的な作業
- ①サーバー契約・Wordpress開設・Wordpress有料テーマの購入
- ②ブログのコンセプト設定
- ③プロフィールページの作成
- ④TOPページ・サイドバー・メニューバー等のデザインを設定
- ⑤アイキャッチ画像のテンプレ作成
- ⑥Google Analytics・Google SearchConsoleの設定
- ⑦プラグインの設定
- ⑧Google Chromeの拡張機能の設定
- ⑨プライバシーポリシー・免責事項・お問い合わせページの作成
- ⑩ASP(A8.net・もしもアフィリエイト)への登録
- ⑪Googleアドセンスへの申請
- ⑫X(旧Twitter)・Pinterestのアカウント開設
- ⑬ブログ運営の勉強
- ⑭根性の毎日投稿
ブログは、夫と2人で運営をしていく方針になったため、夫と私で書く記事の内容や方向性があまりにバラバラになってしまうことがないよう、
まずはブログの最低限のコンセプトや、デザインの方向性を揃えることを行いました。
また前述の「広告収入」を得るための準備として、各アフィリエイトサイトなどに申請を出したりしていました。
(※ブログ開設にあたって行なったことについては、以下記事で別にまとめているため、ぜひ併せてご覧ください)
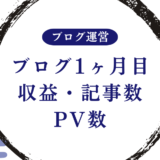 【ブログ運営報告】1ヶ月目の収益・記事数・PV数
【ブログ運営報告】1ヶ月目の収益・記事数・PV数
②根性の毎日投稿
サイトのコンセプトが決まったら、あとは早速記事を書くのみです。
実際私は産休中「毎日1記事書く」ことをルールとして自分に課し、子供を産むまでに以下37本の記事を書き上げました。
記事は、
- それまでの仕事の経験から書ける内容
- 結婚生活について
- 産休中の生活について
など、「『自分の強みが活かせる』×『競合が少ない』×『検索回数が一定数ある』」分野のジャンルを狙って書くようにしていました。
【キャリアに関する記事】
新卒ベンチャー入社の実際を語る|仕事内容・メリット・デメリット
適応障害になった経験から考える、新卒の入社後ギャップの減らし方
【現場社員が語る】こんな人は長期インターンやめとけ。やる意味ない人の特徴4選
【現場社員が語る】長期インターンは「きつい」ものだと心得よう。理由も解説
【通勤時間の有効活用】読書・資格勉強など私の過ごし方をご紹介
【社会人必見】ニュースのキャッチアップ方法、ビジネスの情報収集の方法とは?
【おすすめ本・読書に関する記事】
【Kindle Unlimited】ビジネスパーソンなら入れておくべき7つの理由
読書習慣が身に付く!ビジネスパーソンにKindle端末がおすすめな4つの理由
【私と夫が結婚に至るまでの過程に関する記事】
【実体験】大学生の同棲ってどんな感じ?実際に結婚までいった夫婦が解説
結婚前の同棲はあり?3年の同棲を経て20代前半で結婚した夫婦が解説
「結婚式をしない」選択も尊重されるべき|ナシ婚円満夫婦からの意見
【結婚の決め手】直感ではない。結婚を迷う人たちに伝えたいこと
【産休中の過ごし方に関する記事】
私の産休中の過ごし方|やってよかったこと、タイムスケジュールを紹介
【ブログ運営に関する記事】
【そのほか趣味・暮らしに関する記事】
物を捨てられなかった私が「シンプリスト」になったきっかけ・理由
【酒屋でバイトしていた私が語る】父の日に本当によく売れていた日本酒10選
5. 産休中にブログを始めるメリット

以下では実際に、私が産休中にブログ運営を行なってみて「よかったな」と思う点についてご紹介いたします。
①良い頭の体操になる
前述の通り、ブログ運営には「自分の考えを適切に言語化し、相手にわかりやすい形でアウトプットする」能力が求められます。
例えば記事を書く際には
- 「この表現の仕方で、言いたいことはちゃんと伝わるだろうか」
- 「この言い回しはそもそも日本語として適切か」
などを考える必要があります。
また私の場合は「毎日必ず1本記事を書く」というルールを課していたため、それを1日で終わる範囲(家事などに時間を使うためにも、ブログに割ける時間は3〜4時間程度)で仕上げるというスピード感が求められ、
シンプルに良い頭の体操になっていたと感じています。
②日常にメリハリがつく
産休中はまだ子供が産まれていないため、運よく体調が良かった場合には、
「何もすることがない」と暇になり、ついだらっとしてしまい時間感覚・曜日感覚が薄れていく、ということが起きてしまいがちだと考えています。
それが「ブログ記事を必ず毎日1本書く」というルールを自分に課したことで
- 今日はこの記事を書こう、明日はこの記事を書こう
- 今日の何時までにブログ記事を書き上げなきゃ
など日常の生活にメリハリがつくようになりました。
③気晴らしになる
出産間近になってくると、出産への恐怖などで、どうしても日常に緊張感が走ります。
それが「ブログを書かなきゃ」と何か一つ「やらなきゃいけないこと」があったことで、ちょうど良く不安を紛らわすことができていたように思います。
④達成感を感じられる
「②日常にメリハリがつく」と近しいですが、ブログ運営をしていると
- 「今日も1本記事を書き上げた」
- 「書いた記事が検索結果に表示されるようになった」
など毎日何かしら「成果」が出るため、日々の日常に「達成感」を感じることができるようになります。
また「産休中に私はこれを成し遂げた」ということが一つあるだけで、単純に自分の自信に繋がると感じています。
6. 産休中にブログを始める際のコツ・注意点

最後に、「産休中にブログを始めるのであれば、こういう点を意識すると良い」「こういう点に気をつけるべき」ということについてご紹介いたします。
①体調を第一優先に
まずあくまで「産休中」であるため、自分の体調を第一優先に行動するようにしましょう。
私は産休中、以下のように「やるべきこと」の優先順位をつけて行動をしていました。
- ①出産に備えるための妊婦運動
- ②料理・洗濯・掃除などの家事
- ③子育てに関する勉強
- ④資格取得(簿記2級・FP2級)の勉強
- ⑤ブログ運営
ここまでつらつらと産休中のブログ運営について書いてきましたが、実はブログ運営の優先度は一番最下位でした。
一番最優先して時間を使っていたのは「出産に備えるための妊婦運動」です。
(※私が産休中にどのようなスケジュールで行動していたかについては、以下記事で別にまとめているため、ぜひ併せてご覧ください)
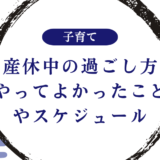 私の産休中の過ごし方|やってよかったこと、タイムスケジュールを紹介
私の産休中の過ごし方|やってよかったこと、タイムスケジュールを紹介
まずは「健康に過ごすこと」を第一優先にして過ごすこと、少しでも体調に不調を感じるようであれば休憩することを意識して、
その上で「余裕があればブログ運営を行う」くらいの気持ちで取り組むのが健全だと考えています。
②収益化までの道のりは遠い
前述の通りブログは「ストック型」の副業であり、そのデメリットとしては、収益化までの道のりが長く、最初のうちはなかなかお金を稼ぐのが難しいことが挙げられます。
以下動画によると、ブロガーに「ブログで月1万円以上稼ぐまでにどれくらいの期間がかかったか」についてアンケートをとったところ、
- 0〜6ヶ月:43.9%
- 6〜12ヶ月:32.4%
- 13ヶ月以上:23.7%
- ※N=579
という結果になったそうです。半数以上の人が、収益化までに半年以上かかっていることがわかります。
「いち早く収益化させたい」と焦ってしまったり、「なかなか収益化できない」とストレスを抱えてしまうのは、産休中としては精神衛生上よろしくないと言えます。
「気長に構えて、趣味の延長線上でゆるく行う」くらいの気持ちで取り組むのが、産休中のブログ運営としては健全な向き合い方だと考えています。
③ブログにどんな内容を書くか
- ブログを始めたいという気持ちになってきたが、いざ始めるとなると、何を書けばいいのか全く思いつかない
という方もいらっしゃると思います。
私は以下のことを意識して記事のジャンルの選定を行っていました。
- ①「『自分の強みが活かせる』×『競合が少ない』×『検索回数が一定数ある』」分野のジャンル
- ②YMYLのジャンルは避ける
やはりブログ運営を続けていくにあたっては、自分が「好き・書きたい・筆がのる」というテーマについて書くのが一番です。
しかし私たちが運営するのはあくまで「個人ブログ」であるため、企業が運営しているサイト・ブログに勝つことは容易ではなく、企業ブログが多く上位表示されているキーワードで自分のサイトを上位表示させるのはかなり難しいことです。
そこで「自分が書きたいと思うテーマ」の中で「企業ブログ(競合)が少ない」ジャンル・キーワードを探して記事を書いていく、というのが効率的で賢いやり方となります。
例えば私は、大学時代に2年間、現在の夫と半同棲生活を送っていました。
これはなかなか他の人にはない経験であるといえ、且つ企業サイトもあまり出てこないジャンルになるため、このテーマで記事を数本書く、ということを決めたりしていました。
※自分の強みを踏まえた上でのブログテーマの選定方法としては、以下書籍が参考になるため、ぜひ併せてご覧ください。
また産休・育休中の人がよく書きたがるテーマとして
- 子育てについて(子供の病気・風邪の対応方法)
- 家計管理について
などがあります。しかしそれらは「YMYL(Your Money or Your Life)」と呼ばれるジャンルに当てはまります。
YMYLのジャンルは基本的に、政府などの公的機関などのサイトが上位表示されるようになっており、個人ブログなどは検索結果に基本的に表示されないような仕組みになっています。
(例えば「コロナ」と調べると、必ず政府のサイトが上位表示されるようになっています。)
またGoogleアドセンスなどの「広告収入」を得るための審査も通りづらいと言われています。
こういったYMYLのジャンルでブログを運営し続けても、広告収入はおろか誰かにブログを見てもらうことすら難しいため、
ブログ運営をするのであれば、できる限りこういったジャンルは避けるのがおすすめです。
④収益化のためには、レンタルサーバーの契約・WordPressでのブログ開設がおすすめ
ブログを始めるにあたっては
- はてなブログ
- アメーバブログ
- note
といったすでにあるプラットフォームを使ってブログを始める方も多くいます。
しかし、ブログ運営で収益化をしっかり狙いたいのであれば、以下理由より、既存のプラットフォームを使用するのではなく、独自でレンタルサーバーを契約しWordpressを開設することがおすすめします。
- 既存のプラットフォームだと、広告掲載が規制されていることがあり、広告収入を得る機会が減ってしまうことがある
- 既存のプラットフォームだと、突然サービスが終了する恐れがある。
サービスが終了した場合、それまで書いた記事は全てこの世から消えてしまう。 - 既存のプラットフォームだと、デザインのカスタマイズができない
まず何よりも「note」などのプラットフォームだと、広告収入が得づらいというのがデメリットとして一番大きいです。
また「突然のサービス終了により、それまで『資産』として積み上げてきたものが一瞬で消えてしまう可能性がある」というのも、懸念点としては非常に大きいものです。
上記デメリットを避けるため、私たちは実際、既存のプラットフォームを使用するのではなく
「ConoHa」のレンタルサーバーで以下の通り契約を行っています。
- プラン名:ベーシック SSD 300GB
- 料金タイプ:WINGパック
- 契約期間:36ヶ月

また、Wordpressの有料テーマとして、「SANGO」のテーマを購入しています。
ConoHaの「WINGパック」とセットで購入することで通常より安く購入することができるようになっており、せっかくなので合わせて購入しました。

5. 最後に
産休中にブログ運営を行うことのメリットをまとめると
となります。

新しい物事にチャレンジするのは、誰だって勇気がいることです。
自分の実体験が、少しでも皆さんの心を軽くしたり、背中をそっと押すものになることができたら嬉しいです。
このサイトでは、後輩を応援したいという気持ちで、これからもさまざまな記事を執筆していきますので、ぜひご覧ください。
 わたしたちについて
わたしたちについて
またこのブログでは、他にも子育て・ブログ運営について記事を執筆していますので、ぜひ併せてご覧ください。