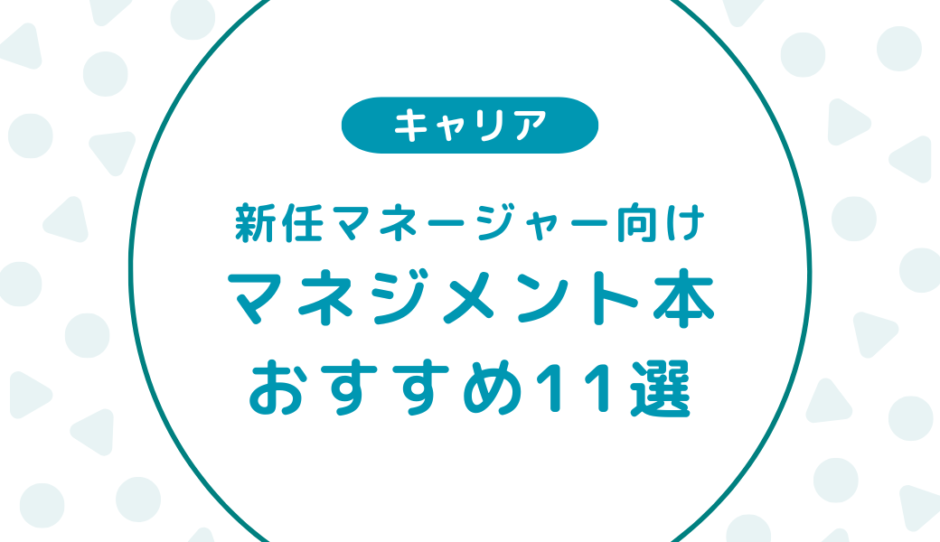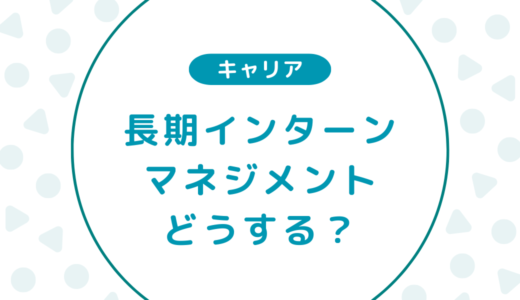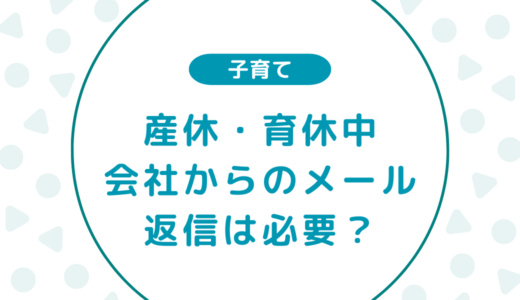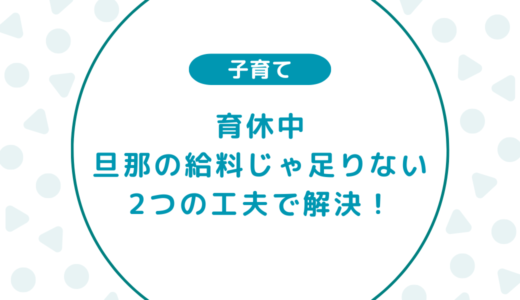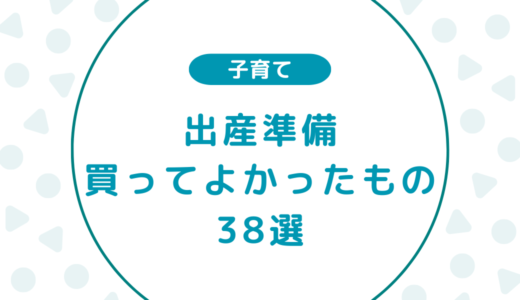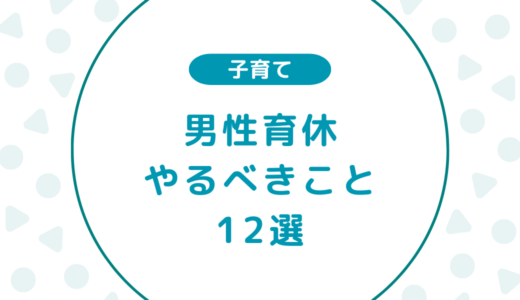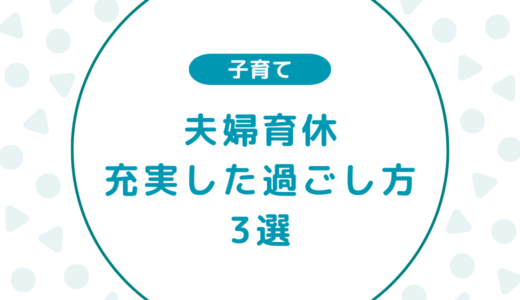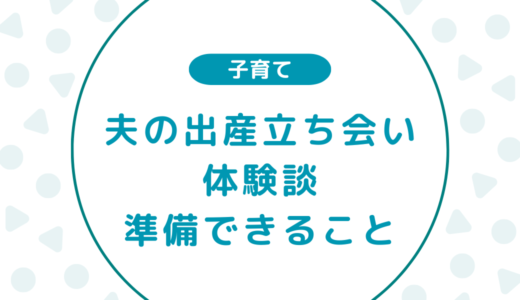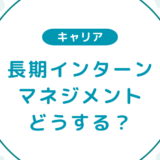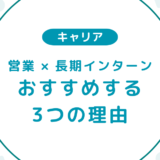この記事では、
- 「まだ自分自身も未熟なのに、いきなり後輩・部下・長期インターン生などのマネジメントを担当することになった」
- 「とにかく、即役に立つような書籍を読んで、マネジメントの全体像について把握できるようにしたい」
という方に向けて、
- 実際に私が新卒3年目で長期インターン生をマネジメントすることになった際に読んで、本当に参考になった書籍
- 周りの先輩に実際におすすめされた本
について、自分も同じように不安になったり挫折した経験を踏まえ、実体験ベースでお伝えします。
(※私が新卒3年目で長期インターン生をマネジメントすることになった際の詳細については、以下記事で別にまとめているため、ぜひ併せてご覧ください)

まるで1個上の先輩とサシ飲みに行ったかのように、「有益な情報が得られた」「心が少し軽くなった」「また明日から頑張ろう」、そんな気持ちになっていただけたら嬉しいです。
1. 「どうメンバーと接し、管理すればいいのか」に関する基本の本

まず
「『マネジメント』の業務で行わなければいけないことの全体像」
「上司・部下の関係性をどう構築すべきなのか」
などマネジメントの基本のキをまとめている本をご紹介します。
①無理・無意味から職場を救うマネジメントの基礎理論
【本のタイトル】
無理・無意味から職場を救うマネジメントの基礎理論
【目次】
- 第1章 なぜ企業は社員のやる気を大切にするのか
- 第2章 難しいのは機会の与え方と支援
- 第3章 組織をイキイキとさせる古典的理論
- 第4章 指令や判断の根源がコア・コンピタンス
- 第5章 見栄えのいいメソッドよりも錆びない基礎理論を
この本では、具体的な例題を用いて様々なマネジメントに関する基礎理論を紹介してくれています。
例えば「2W2R」という概念の紹介のために、以下のような例題が出されます。
Q.あなたは、いま「ハンバーガー」ショップで副店長として勤務しています。今日は新入りのアルバイトに、ハンバーガーのつくり方を教えることになりました。ちょうど、「ケチャップの塗り方」を講義しています。以下の教え方は、非常にまずい部分があります。どこが足りないでしょうか?
無理・無意味から職場を救うマネジメントの基礎理論
「ケチャップは、ミートの上に、均一に塗りなさい。そのあとで、ピクルスと玉ねぎをケチャップを塗ったミートの上に載せなさい」
私はこの本で「2W2R」という概念を知って非常に納得し、今でも誰かに仕事を振るときは「2W2R」を意識するようにしています。
「2W」とは、「What(何を)」「Way(どうやって)」、「2R」とは「Reason(理由)」「Range(範囲)」です。
問題に出てきた副店長は、このうちのWhat(何を)しか指導していない点がまずい部分となっています。したがって模範解答は以下のようになります。
「ケチャップは均一に塗りなさい(What)。そのためには、ケチャップをミートの真ん中に丸く落としなさい(Way)。そうすれば、どこから食べても同じ味になるはずです(Reason)」
無理・無意味から職場を救うマネジメントの基礎理論
このほかにも様々なマネジメントの王道・基本理論が網羅されているため、最初の1冊としてぜひおすすめしたい本です。
②フィードバック入門
【本のタイトル】
フィードバック入門―耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す技術
【目次】
- 第1章 なぜ、あなたの部下は育ってくれないのか?
- (日本のマネジャーが疲労している原因は「部下育成」にあり;「昔の上司は人を育てるのがうまかった」は本当か? ほか)
- 第2章 部下育成を支える基礎理論フィードバックの技術 基本編
- (部下育成の基礎理論:「経験軸」と「ピープル軸」で考える;経験軸―部下に適切な業務経験を与えているか? ほか)
- 第3章 フィードバックの技術 実践編
- (チェックポイント1.あなたは、相手としっかりと向き合っているか?;チェックポイント2.あなたは、ロジカルに事実を通知できているか? ほか)
- 第4章 タイプ&シチュエーション別フィードバックQ&A
- (すぐに激昂してしまう「逆ギレ」タイプ;何を言っても黙り込む「お地蔵さん」タイプ ほか)
- 第5章 マネジャー自身も成長する!自己フィードバック・トレーニング
- (フィードバックの実力をつける二つのポイント;「模擬フィードバック」で、自分のフィードバックを客観的に観察 ほか)
私はこの本で初めて
- ティーチングとコーチングの違い
- コンフォートゾーン・ストレッチゾーン・パニックゾーンという概念
を知ることができ、「だから私はこれまで上司から振られた仕事、上司の教育の姿勢に辛さを感じていたのか」と納得することができ、救われたという経験があります。
また、「すぐに激昂してしまう『逆ギレ』タイプ」「何を言っても黙り込む『お地蔵さん』タイプ」などの部下を持った際にはどうフィードバックをすればいいのか、などについてもパターン別に細かく解説がされており、非常に参考になります。
そこまで厚さがある本ではなく、短い時間でサクッと読むことができるため、おすすめです。
③急成長を導くマネージャーの型
【本のタイトル】
急成長を導くマネージャーの型―地位・権力が通用しない時代の“イーブン”なマネジメント
【目次】
- マネジメントは経験でもセンスでもない、「型」を身につけ実行するのみ
- マネージャーの役割を認識する
- 正確で素早い現状把握でロケットスタート
- チームの役割、目標、意義を設定する
- チームの戦略3点セット“方針・KPI・重要アクション”
- 強いチームをつくる
- 戦略と組織を動かす「推進システム」を作る
- 初期の成果とモメンタムをつくりだす
- 改善で継続的に成果を出し続ける
- 個人目標設定で成長のきっかけを与え、評価で努力に報いる
- ピープルマネジントでメンバーを動かす
- 3つのコミュニケーション技術を使いこなす
- マネージャーの立ち位置と心得
- マネージャーにとって一番大事なこと
この本は特に「ベンチャー企業」「スタートアップ」「新規事業立ち上げの現場」等、変化の激しい現場でマネジメントをしようとしている方におすすめの本になっています。
私はこの本の「マネジメントは経験でもセンスでもない、「型」を身につけ実行するのみ」という考え方にとても共感しました。
その言葉の通り、この本では「この型・手順に則ってマネジメントを進めていけばOK」というレベルで、それぞれのフェーズ・シーンでのマネジメントのやり方をこと細かく解説してくれており、非常にわかりやすい本となっています。
④識学三部作
【本のタイトル】
リーダーの仮面―「いちプレーヤー」から「マネジャー」に頭を切り替える思考法
【目次】
- はじめに なぜ、「リーダーの言動」が大事なのか?
- 序章 リーダーの仮面をかぶるための準備―「鎖覚」の話
- 第1章 安心して信号を渡らせよ―「ルール」の思考法
- 第2章 部下とは迷わず距離をとれ―「位置」の思考法
- 第3章 大きなマンモスを狩りに行かせる―「利益」の思考法
- 第4章 褒められて伸びるタイプを生み出すな―「結果」の思考法
- 第5章 先頭の鳥が群れを引っ張っていく―「成長」の思考法
- 終章 リーダーの素顔
【本のタイトル】
数値化の鬼――「仕事ができる人」に共通する、たった1つの思考法
【目次】
- はじめに ―いったん数字で考える思考法
- 序章 「数値化の鬼」とは何か
- 第1章 数を打つところから始まる―「行動量」の話
- 第2章 あなたの動きを止めるもの―「確率」の話
- 第3章 やるべきこと、やらなくてもいいこと―「変数」の話
- 第4章 過去の成功を捨て続ける―「真の変数」の話
- 第5章 遠くの自分から逆算する―「長い期間」の話
- 終章 数値化の限界
【本のタイトル】
とにかく仕組み化――人の上に立ち続けるための思考法
【目次】
- 第1章 正しく線を引く―「責任と権限」
- 第2章 本当の意味での怖い人―「危機感」
- 第3章 負けを認められること―「比較と平等」
- 第4章 神の見えざる手―「企業理念」
- 第5章 より大きなことを成す―「進行感」
- 終章 「仕組み化」のない別世界
「識学三部作シリーズ」は、ベストセラーとして書店の店頭などに置かれていたことも多かったため、目にしたことがあるビジネスパーソンも多いのではないでしょうか。
その名の通り、「プレイヤー」から「マネージャー」に視点を切り替えるために必要なマインドセットについて、わかりやすく解説がされています。
「シビアに淡々と」といった性格の手法のため賛否両論があるようですが、個人的には理論・考え方の一つとして非常に納得できるものであると考えており、食わず嫌いせずにまずは一度読んでみるべき本である、と思っています。
⑤世界基準の上司
【本のタイトル】
世界基準の上司
【目次】
- 第1章 世界基準で活躍する上司になる
- (こんな上司では、到底生き残れない;「責任」の意味をはき違えない;「世界基準で活躍する上司」の根本的考え方)
- 第2章 一つめの実践―部下と協力関係を築く
- (初めて部下を持った時、格好をつけず早く慣れる;部下をよく理解する;部下に信頼される)
- 第3章 二つめの実践―部下に具体的な指示を出す
- (目標を合意する:業績・成長目標合意書;具体的な指示を出す;アウトプットイメージ作成アプローチで成果を出させる)
- 第4章 三つめの実践―チームから最大の成果を引き出す
- (部下の成長を評価し、加速する;部下のやる気を高める;新しいチームを率いる;チームから最大の成果を引き出し、成功体験を与える)
- 第5章 四つめの実践―部下とのコミュニケーションをとる
- (常にポジティブックスフィーバックを心がける;部下の悩みを聞く;チームミーティングを効果的に実施する;チームには最大限情報共有する)
- 第6章 五つめの実践―部下をきめ細かく育成する
- (部下それぞれの接し方を変える;できない部下を育成する;できる部下を育成する;つぶれそうな部下を支える)
この本では「こういう嫌な上司、ダメな上司いるよね」「本当はこういう上司であるべきだよね」というのを一つ一つ挙げてくれており、
嫌な上司を経験したことがある人が読むと、ある意味スカッとできる本になります。
また「アウトプットイメージ作成アプローチ」など、部下に仕事を任せる際の具体的なテクニック実例も交えて解説してくれているため、実践に落とし込みやすく、おすすめな一冊になっています。
2. チーム運営における様々なシーンで活躍する本

チームを受け持つとなると、日々のマネジメント業務のみならず「採用」「入社後の研修」「評価面談」など、シーンごとに特定の業務も付随してきます。
以下、それぞれのシーンで活躍するおすすめ本をご紹介します。
①人事と採用のセオリー
【本のタイトル】
人事と採用のセオリー―成長企業に共通する組織運営の原理と原則
【目次】
- 1 人事のセオリー
- (そもそも、人事の役割とは何か;組織の成長に応じて、人事の考え方は変わる;採用と代謝は一つの流れで考える;配置によって人を育成する;評価と報酬では納得感を担保する)
- 2 採用のセオリー
- (採用計画はどのように立てるのか;候補者集団を形成し、選考する;面接の質を向上させる;優秀層を確保する;中途人材や外国人を採用する)
チームを受け持つと、業務量と人手のバランスを見て、必要に応じて自分自身で人材のリソースを確保しにいかなければいけない、という場面も出てくるのではないでしょうか。
この本は会社の人事向けに書かれている本ではありますが「Part2.採用のセオリー」で記載されている
- 採用チームの作り方
- 求める人物像の設定方法
- 採用の母集団の形成
- 面接でのポイント
が、採用活動の基本的な全体像を捉えるのに最適で、自分で採用活動を行う際に非常に参考になるため、おすすめな本です。
②さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 新版 ストレングス・ファインダー2.0
【本のタイトル】
さあ、才能(じぶん)に目覚めよう 新版 ストレングス・ファインダー2.0
【目次】
- 1 まず、あなたの強みを見つけよう
- (「いばらの道」を選ぶな;あなたは「強みのゾーン」にいるか;「才能」を「強み」にする;才能はあなたに見出されるのを待っている ほか)
- 2 あなたの強みを活用しよう―34の資質と行動アイデア
- (アレンジ;運命思考;回復志向;学習欲 ほか)
- 「各メンバーが持っている強みってなんだろう」
- 「あのメンバーには自分とは違った強みがあるのはなんとなくわかるが、そのポテンシャルをうまく引き出してあげられている自信がない」
といった際におすすめのツールがこちらの本です。
・クリフトンストレングス®(ストレングスファインダー®)とは、米国ギャラップ社の開発したオンライン「才能診断」ツールです。Webサイト上で177個の質問に答えることで、自分の才能(=強みの元)が導き出されます。
・クリフトンストレングス®(ストレングスファインダー®)では才能を34の資質(似たような才能の集まり)に分類しています。そして、その34資質のうち、最も特徴的(優先度の高い思考、感情、行動のパターン)な5つを診断結果として出します。
クリフトンストレングス®(ストレングスファインダー®)とは | クリフトンストレングス(ストレングスファインダー)で強みを活かす 株式会社ハート・ラボ・ジャパン
▼ストレングスファインダーで分類している34の資質
【思考力】
分析思考・原点思考・未来志向・着想・収集心・内省・学習欲・戦略性
【人間関係力】
適応性・運命思考・成長促進・共感性・調和性・包含・個別化・ポジティブ・親密性
【影響力】
活発性・指令性・コミュニケーション・競争性・最上志向・自己確信・自我・社交性
【実行力】
達成欲・アレンジ・信念・公平性・慎重さ・規律性・目標志向・責任感・回復志向
診断ツールが書籍に付属している形になっています。
自分含め、チームメンバー全員でこの診断を受け、「自分はどの資質が上位5つにきていたか」を提示し合うことで、お互いの理解を深めることができます。
また書籍には、「各資質の詳細な特徴」および「その資質を持っている人のパフォーマンスを最大化させるためにはどうすればいいのか」について解説が記載されているため、それをもとにメンバーに仕事を割り振っていく、ということもできます。
③研修デザインハンドブック
【本のタイトル】
研修デザインハンドブック―学習効果を飛躍的に高めるインストラクショナルデザイン入門
【目次】
- 第1章 なぜ、研修にインストラクショナルデザインが必要なのか?
- (研修の効果を高めるために必要なこと;インストラクショナルデザインの失敗例;インストラクショナルデザインの基本コンセプト)
- 第2章 インストラクショナルデザインの8つのステップ
- (ニーズを分析する;参加者を分析する;目的を設定する ほか)
- 第3章 インストラクショナルデザインの実践例
- (インストラクショナルデザインを実践する)
新卒社員や長期インターン生など、「0からスタート」というメンバーを育成する際には、どうしても「研修」といった、がっつりティーチングをする場が必要になってくると思っています。
この本は「ハンドブック」とだけあって、研修の適切な設計方法について細かく手順を解説してくれており、愚直にこれの通りに研修を行えば、研修で大失敗をすることはないと言えるためおすすめの本です。
④マネジャーのための人事評価で最高のチームをつくる方法
【本のタイトル】
マネジャーのための人事評価で最高のチームをつくる方法―「査定する場」から「共に成長する場」へ
【目次】
- 序章 今、人事評価に求められていること
- 第1章 評価者になったら知っておくべきこと
- [コラム]「ジョブ型雇用」になったらどうなる?
- 第2章 評価がうまくいく目標設定の方法とは?
- 第3章 納得感の高い評価のつけ方とは?
- 第4章 評価を伝えるうえで部下を理解するには?
- 第5章 成果と成長を促す評価の伝え方とは?
- [コラム]心理的安全性が注目される理由
- 付録1 目標の要素分解[事例集]
- 付録2 「表層深層フレーム」に基づく評価のすり合わせ[事例集]
上司になると、嫌でも部下の「評価」をつけなければいけないタイミングがやってきます。
この本では、部下を評価するとなった際に押さえておくべき
- そもそもどういう観点で評価をつければいいのか
- どのように部下と向き合い評価を伝えればいいのか
- 評価面談で意識しなければいけないポイントとは
といった基本的なことについて解説してくれている本です。
「確かに自分の時も、評価面談の際に上司からこういうふうに評価を言われて、あんまりいい気分がしなかったな」など思い出しながら読むことができ、
「適切な評価の付け方」「評価面談のやり方とは」について考えることができるためおすすめです。
3. 「チームのKPI達成のためにどう動けばいいのか」に関する基本の本

マネージャーはただ「雰囲気の良いチーム」を作れば良いわけではなりません。
その先で最終的に達成しなければいけない、会社から求められている数値的な成果というものがあるはずです。
以下では、「そもそもチームでKPIを達成するためにはどのように動くのが適切なのか」についてわかりやすくまとめられている本をご紹介します。
①鬼速PDCA
【本のタイトル】
鬼速PDCA
【目次】
- 1章 前進するフレームワークとしてのPDCA
- 2章 計画初級編:ギャップから導き出される「計画」
- 3章 計画応用編:仮説の精度を上げる「因数分解」
- 4章 実行初級編:確実にやり遂げる「行動力」
- 5章 実行応用編:鬼速で動くための「タイムマネジメント」
- 6章 検証:正しい計画と実行の上に成り立つ「振り返り」
- 7章 調整:検証結果を踏まえた「改善」と「伸長」
- 8章 チームで実践する鬼速PDCA
「PDCA」のフレームワークは非常に有名なため、どんなビジネスパーソンも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
ただ私の経験則上「PDCA」という言葉は、「まず一回やってみて、後々PDCA回していけばいいから」のように、「振り返り」くらいの言葉で使われてしまっていることが多く
PDCAのフレームワークに沿って厳密にプロジェクトを回している現場はあまりないように感じています。
この本では、
- そもそもPDCAとは何か
- 成果を達成するために、PDCAを高速で回すためにはどのように動けば良いのか
- PDCAをチームとして実践していくためには
といったPDCAの基本をしっかり学ぶことができる本です。
PDCAに関する本はこれだけ読んでおけば十分で、あとはチーム全体で実行していくのみ、と言える本です。
②最高の結果を出すKPIマネジメント
【本のタイトル】
最高の結果を出すKPIマネジメント
【目次】
- 第1章 KPIの基礎知識
- (KPIって何ですか?;ダメダメKPIの作り方でありがちなこと ほか)
- 第2章 KPIマネジメントを実践するコツ
- (ダメダメなKPIってどこで分かるの?;KPIは「信号」だから「1つ」 ほか)
- 第3章 KPIマネジメントを実践する前に知っておいてほしい3つのこと
- (会社の方向性を「構造」と「水準」でつかむ;ゴーイングコンサーンを実現させるKGI ほか)
- 第4章 さまざまなケースから学ぶKPI事例集
- (特定の営業活動を強化することで業績向上を目指す;エリアにフォーカスすることで業績を拡大する ほか)
- 第5章 KPIを作ってみよう
- (KPIステップの復習;KPIマネジメントを始めるための事前準備 ほか)
ビジネスパーソンとして働いていると「KPI」という単語を耳にすることも多いはずです。
しかし大抵の人は、会社から言い渡される「KPI」の数字に日々追われるだけで、「そもそもKPIとはなんなのか」について真剣に腰を据えて考えた経験がある、ということは少ないのではないでしょうか。
この本では、
- そもそもKPIとは
- 適切なKPIの設定方法とは
- KPI達成のためにはどのようにPDCAを回していくべきなのか
の基本について解説してくれています。
マネージャーになると、自分がKPIを設定する立場になるはずです。
その際に「なんとなくこれまで使われていた数字でKPIを設定する」のではなく、戦略達成のために適切なKPIを設定することができるよう、ぜひこの本は一読しておくと良いでしょう。
4. 最後に
以上、初心者におすすめのマネジメント本11選をご紹介しました。まとめると
となります。

新しい物事にチャレンジするのは、誰だって勇気がいることです。
自分の実体験が、少しでも皆さんの心を軽くしたり、背中をそっと押すものになることができたら嬉しいです。
このサイトでは、後輩を応援したいという気持ちで、これからもさまざまな記事を執筆していきますので、ぜひご覧ください。
 わたしたちについて
わたしたちについて
またこのブログでは、他にもキャリア・おすすめ本について記事を執筆していますので、ぜひ併せてご覧ください。