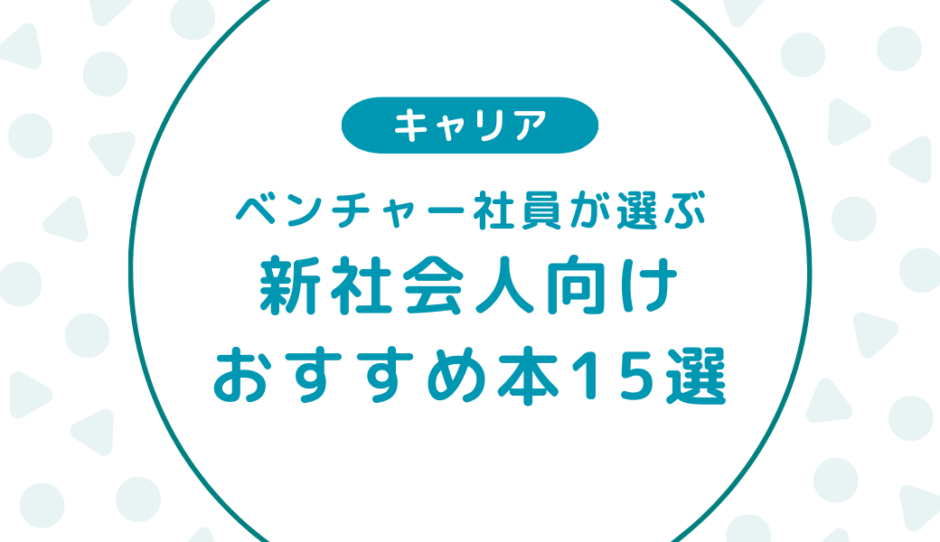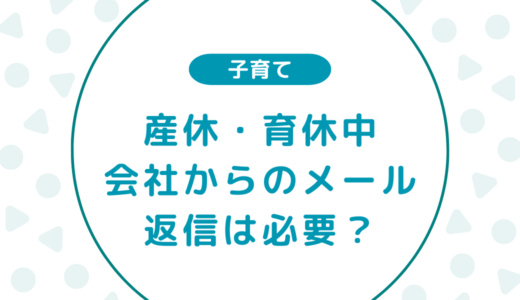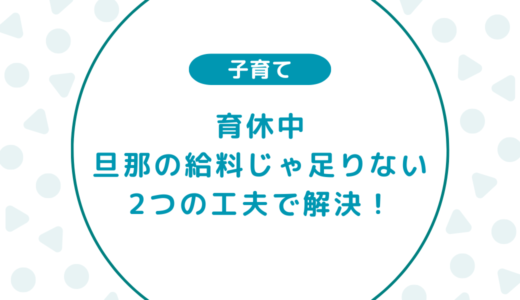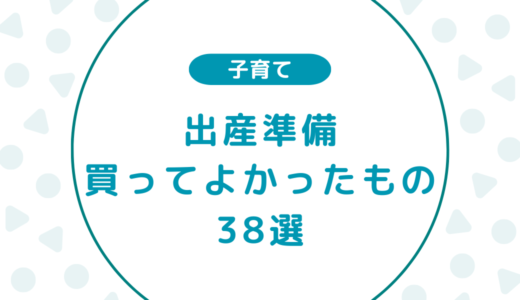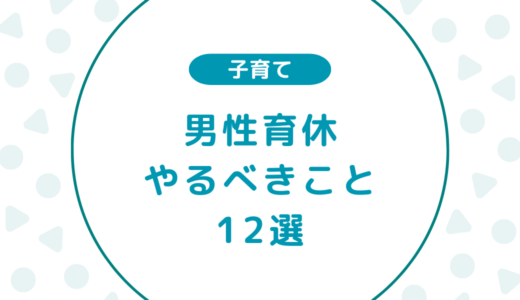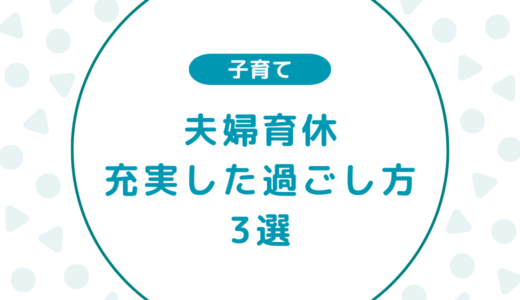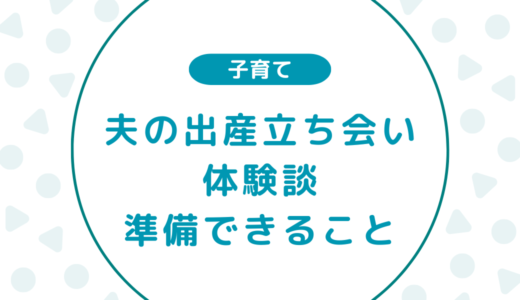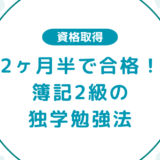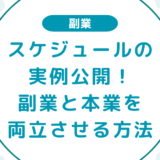この記事では、
- 新社会人になるにあたって、どんな本を読んでおけばいいのか知りたい
- 本を読むと言っても、どんなカテゴリーの本を読めばいいのかわからない
という方に向けて、
- ベンチャー企業に入社して、実際に役に立った本
- 周りの先輩に実際におすすめされた本
について、自分も同じように不安になったり挫折した経験を踏まえ、実体験ベースでお伝えします。

まるで1個上の先輩とサシ飲みに行ったかのように、「有益な情報が得られた」「心が少し軽くなった」「また明日から頑張ろう」、そんな気持ちになっていただけたら嬉しいです。
1. マインド編

仕事において大切なのは「高度なスキルを持っていること」よりも、「愚直に取り組む」という姿勢や、「自分はどういう人生を歩んでいきたいのか」「自分は何を成し遂げたいのか」という野心・マインドを持っていることです。
この章では「どんなマインドを持って働く必要があるのか」について知ることができるおすすめ本を紹介します。
①成長マインドセット
【本のタイトル】
成長マインドセットー心のブレーキの外し方
【目次】
- プロローグ
- 第1章 成長とは何か
- 第2章 成長を阻害する1つ目のブレーキ
- 第3章 成長を阻害する2つ目のブレーキ
- 第4章 成長を促進する1つ目のアクセル
- 第5章 成長を促進する2つ目のアクセル
- エピローグ
ストーリーベースで書かれているため、サクサク読みやすいです。本を読む習慣がないという方でも読みやすい本だと思い、1冊目にピックアップしました。
私が初めてこの本を読んだ際は「心にかかっているブレーキの存在を認知しよう」という内容に、目から鱗が落ちました。
実際私は、これまでの人生のさまざまな場面(部活・バイト・勉強等)で、「ブレーキをかけながらアクセルを踏む」ということを何度もしていたような人間でした。
なのでこの本を読んだことで、「社会人になるにあたって『ブレーキをかけながらアクセルを踏む』癖はなくそう。決めたところまではアクセル全開で進み続ける覚悟を持とう」と心構えを作ることができました。
②採用基準
【本のタイトル】
採用基準 地頭より論理的思考力より大切なもの
【目次】
- 序章 マッキンゼーの採用マネジャーとして
- 第1章 誤解される採用基準
- 第2章 採用したいのは将来のリーダー
- 第3章 さまざまな概念と混同されるリーダーシップ
- 第4章 リーダーがなすべき四つのタスク
- 第5章 マッキンゼー流リーダーシップの学び方
- 第6章 リーダー不足に関する認識不足
- 第7章 すべての人に求められるリーダーシップ
- 終章 リーダーシップで人生のコントロールを握る
私はこの本で「リーダーシップとは何か」を学びました。
新卒のうちは「自分はまだついていく側」「リーダーシップを発揮するのは、仕事に慣れてきて、中堅社員とかになってから」と無意識に思いがちではないでしょうか。
この本では、リーダーシップは、新卒のうちから発揮できる、発揮すべきものである、ということを教えてくれます。
またこの本で語られていた「思考力とは」という考え方も、個人的にとても印象に残っています。
思考力とは、以下3つの思考力の足し合わせのことを言う。
・思考スキル:フレームワークなど後から学べるもの。面接時になくても、学ぶ力があれば良い。
・思考意欲:考えることが好き。
・思考体力:長期間、睡眠不足の中などでも考え続けることができる。
「思考力をつけよう」と思うと、「思考スキル」にいきなり走ろうとしがちではないでしょうか。私はそうでした。
ですがこの本を読んで、「スキル・テクニックも大事だが、何より土台である『思考意欲』『思考体力』を伸ばすことが大事だ」と思わされ、
実際仕事をしていて、ちょっと頭が疲れたなと思った時でも、「いや、今こそ思考体力の伸ばしどき」と思って踏ん張る、ということができるようになりました。
③調理場という戦場
【本のタイトル】
調理場という戦場―「コート・ドール」斉須政雄の仕事論
【目次】
- フランス 一店目
- フランス 二店目
- フランス 三店目
- フランス 四店目
- フランス 五店目
- フランス 六店目
- 東京 コート・ドール
この本は「入社1年目の教科書」でおすすめされていた本です。
「おすすめされている本はとりあえず全部読もう」という何気ない気持ちで読んだこちらの本でしたが、学べることがとても多すぎて、消化不良になったのを覚えています。
この本は、著者が自身の料理人人生を振り返り、仕事論や料理に対する姿勢、若いシェフたちへの思いなどをまとめたものですが、
料理の世界にいる人に限らず、全ての仕事人に刺さる内容が多く盛り込まれています。
新卒の時に一度読むだけでなく、人生のあらゆる場面(仕事・プライベートに行き詰まった時、後輩を持った時、マネージャーになった時など)で何度も読み返したいなと思う本です。
学べることが多すぎて消化不良になりましたが、私は「入社1年目の教科書」で「何か1つに絞って学びを持ち帰る」という考え方を学んだので、
この本から持ち帰る内容として、ひとまず「整理整頓がなされていることは、仕事がきちんとなされるための基本」というのを持ち帰り、今でもそれは実践しています。
・大切なのは、簡潔であり、清潔であり、人間性があるということです。
調理場という戦場―「コート・ドール」斉須政雄の仕事論
・「整理整頓がなされていることは、仕事がきちんとなされるための基本なのだ」ということが、このお店に来てよくわかった。乱雑な厨房からは、乱雑な料理しか生まれない。大声でわめきたてる厨房からは、端正な料理は生まれない。
④7つの習慣
【本のタイトル】
完訳 7つの習慣 人格主義の回復: Powerful Lessons in Personal Change
【目次】
- 第一部 パラダイムと原則
- インサイド・アウト
- 7つの習慣とは
- 第二部 私的成功
- 第1の習慣 主体的である パーソナル・ビジョンの原則
- 第2の習慣 終わりを思い描くことから始める パーソナル・リーダーシップの原則
- 第3の習慣 最優先事項を優先する パーソナル・マネジメントの原則
- 第三部 公的成功
- 第4の習慣 Win-Winを考える 人間関係におけるリーダーシップの原則
- 第5の習慣 まず理解に徹し、そして理解される 共感によるコミュニケーションの原則
- 第6の習慣 シナジーを創り出す 創造的協力の原則
- 第四部 再新再生
- 第7の習慣 刃を研ぐ バランスのとれた再新再生の原則
- 再び、インサイド・アウト
- 私がよく受ける質問
言わずと知れた名著「7つの習慣」。こういった「名著」と呼ばれるものは、まずは一度読んでみるべきです。
私は特に「7つの習慣」の中の「第3の習慣」で解説されていた「時間管理のマトリクス」が印象に残っており、仕事をしている最中、またプライベートの中でもたびたび思い出すように心がけています。
第1領域(緊急かつ重要な「必須の領域」)
第2領域(緊急ではないが重要な「効果性の領域」)
第3領域(緊急だが重要ではない「錯覚の領域」)
第4領域(緊急でも重要でもない「浪費・過剰の領域」)
「私は今、仕事・人生で『第2領域』にどれくらい時間を割くことができているだろうか」
「何かを言い訳にして『第1領域』『第3領域』『第4領域』に逃げてしまっていないか」
という考え方を身につけることができたおかげで、仕事に忙殺される中でも、タスクの優先順位の付け方・時間の使い方について、常に一歩立ち止まって深く考えることができるようになったと思います。
2. スキル編

新卒のうちは、「相手が何を話しているのか正確に把握する」「自分の言いたいことを正確に伝える」ができて、周りとちゃんと意思疎通ができる人間になることができれば、極論それで十分だと思います。
そのために必要な力である「論理的思考」や「仮説思考」、「プレゼン資料の作り方」などについて、おすすめの本を紹介します。
①あなたの話はなぜ「通じない」のか
【本のタイトル】
あなたの話はなぜ「通じない」のか
【目次】
- 第1章 コミュニケーションのゴールとは?
- (通じ合えない痛み;自分のメディア力を高める ほか)
- 第2章 人を「説得」する技術
- (論理で通じ合う大原則とは?;考える方法を習ったことがありますか? ほか)
- 第3章 正論を言うとなぜ孤立するのか?
- (関係の中で変わる意味;正論はなぜ人を動かさないのか? ほか)
- 第4章 共感の方法
- (情報は配列が命;共感を入り口にする ほか)
- 第5章 信頼の条件
- (言葉が通じなくなるとき;はじめての人に自分をどう説明するか? ほか)
私はこの本で「メディア力」という考え方を学びました。
新卒のうちは、良かれと思って提案した意見や、頑張って作ったプレゼン案が、周りに「うん、まあそうだね〜」と軽く受け流されてしまうこともあるかもしれません。
それは、自分にまだ「メディア力」がないからだということが、本書を読むとわかります。
・私たちは、何かを伝えようとするとき、伝える内容の方に一生懸命になる。しかし、聞く方は予備知識も含め、あなたというメディア全体が放っているものと、発言の内容の「足し算」で聞いている。
あなたの話はなぜ「通じない」のか
・日頃の立居振る舞い・ファッション・表情。人への接し方、周囲への貢献度、実績。何を目指し、どう生きているか、それをどう伝えているか?それら全ての積み重ねが、周囲の人との中にあなたの印象を形作り、評判を作り、再び「メディア力」として、あなたに舞い戻ってくる。動きやすくするのも、動きにくくするのも自分次第だ。
新卒に限らず、新しいチームへの配属や転職した際なども同じだとは思いますが、
まずは自分が「信頼に足るメディア」になるために、日頃の仕事・立ち居振る舞い・人との接し方など、愚直に行っていくことから始める必要がある、というのを知っておくと、スムーズに仕事を進めることができるようになるはずです。
②ロジカル・プレゼンテーション
【本のタイトル】
ロジカル・プレゼンテーション―自分の考えを効果的に伝える戦略コンサルタントの「提案の技術」
【目次】
- 序章 新規事業立ち上げのストーリー
- 第1章 提案の技術とは
- 第2章 論理思考力―話をつなぐスキル
- 第3章 仮説検証力―疑問に答えるステップ
- 第4章 会議設計力―議論をまとめるスキル
- 第5章 資料作成力―紙に落とすステップ
- 第6章 最終章
この本では「適切に物事を考える(論理的思考力・仮説検証力)」「適切に相手に伝える(会議設計力・資料作成力)」というスキルについて、わかりやすく理論的にまとめられています。
私はこの本を読んで初めて、それまでよくわからなかった「論理的思考とは何か」「仮説とは何か」「示唆とは何か」などについて理解することができました。
ただ、仕事を初めて間もない段階で読んでも、理論的で抽象的な話が多いため、あまりピンとこない部分が多いかもしれません。
私自身、新卒入社で間もない時に読んだ際は、「日本語の意味はわかったような気がするが、あまり自分の身に落とし込めていないな、、」という状態でした。
おすすめは、仕事を初めてある程度時間が経った際に読んでみることです。私自身、仕事を初めて1年程度経った際にもう一度読んでみたら、
「自分がいつも思考をする際に混乱するのは、これが原因だったのか」
「上司が『仮説をもとに考えろ』とか『論点を整理しろ』とか言うのは、つまりこういうことか」
などより理解ができ、自分の身に落とし込むことができました。
「論理的思考」「仮説思考」などの一つ一つのスキルは話が奥深いので、まずはこの本でそれぞれのスキルの全体像や、どんな場面で使うことになるのかの流れを抑え、
深掘りしたいテーマについては、それについて詳しく書かれている本を読む、というのがわかりやすいのでは、と思います。
③仮説思考
【本のタイトル】
仮説思考 BCG流 問題発見・解決の発想法
【目次】
- 序章 仮説思考とは何か
- 第1章 まず、仮説ありき
- 第2章 仮説を使う
- 第3章 仮説を立てる
- 第4章 仮説を検証する
- 第5章 仮説思考力を高める
- 終章 本書のまとめ
「仮説とは何か」「仮説思考とは何か」「仮説を用いてどのように仕事を早く進めていくか」について、その重要さと具体的な方法について、詳しく書かれている本です。
何か重要な意思決定をする際、私たちはついつい、全ての情報を満足いくまで集めてから判断を下そうとしがちですが、そのやり方は時間的にも資源的にも厳しいです。
少ない情報しか集まっていない中で、仮説を持って素早く判断を下す力が必要になってきます。
仮説思考を持って働くというのは、すぐにできるようになるものではなく、日々鍛錬を積み重ねないとなかなかできないことだと感じます。実際私も、常に仮説を持って行動できているかと言われると、微妙なところがあります。
だからこそ、早くからこの本を読み仮説思考の重要性について知っておき、早くから少しずつ練習を積み重ねるのがおすすめです。
④論点思考
【本のタイトル】
論点思考 BCG流 問題設定の技術
【目次】
- 第1章 あなたは正しい問いを解いているか
- 第2章 論点候補を拾いだす―戦略思考の出発点
- 第3章 当たり・筋の善し悪しで絞り込む
- 第4章 全体像を確認し、論点を確定する
- 第5章 ケースで論点思考の流れをつかむ
- 第6章 論点思考力を高めるために
この本では「例えばこのシーンでは、何が論点となりうるか」などの具体例を用いながら、「論点とは何か」「論点の掴み方とは」についてわかりやすく解説してくれています。
「何が問われているのか」「答えるべき問いは何か」を間違えてしまうと、いくらその問いを必死に解いたところで、真の問題解決にはなりません。
「上司と論点の擦り合わせがうまくできていなかった結果、頑張って時間をかけて分析結果を出したのに、上司に微妙な反応をされてしまった」などということにならないよう、論点を抑える力をつけることはとても重要です。
⑤マーケット感覚を身につけよう
【本のタイトル】
マーケット感覚を身につけよう—「これから何が売れるのか?」わかる人になる5つの方法
【目次】
- 序 もうひとつの能力
- (ANAの競合を論理的に分析する;顧客の利用場面を想像する ほか)
- 1 市場と価値とマーケット感覚
- (市場を理解するための要素;価値とは何か? ほか)
- 2 市場化する社会
- (相対取引だった昔の就職活動;相対取引から市場取引へ ほか)
- 3 マーケット感覚で変わる世の中の見え方
- (これからは英語の時代ってホント?;市場の「入れ子構造」を理解しよう;NPOに負けているビジネス部門 ほか)
- 4 すべては「価値」から始まる
- (マーケティングとマーケット感覚;「価値」を見極める;非伝統的な価値の出現 ほか)
- 5 マーケット感覚を鍛える5つの方法
- (プライシング能力を身につける;インセンティブシステムを理解する ほか)
- 終 変わらなければ替えられる
- (「変」or「替」;市場が規制を変える ほか)
「マーケット感覚」とありますが、マーケティングに関わる人に限らず、広くおすすめな本です。
マーケット感覚とは
・その市場で取引されている価値が何なのか、感覚的に理解できる力
・顧客が、市場で価値を取引する場面を、直感的に思い浮かべられる力
・商品やサービスが売買されている現場の、リアルな状況を想像できる力
ビジネスの基本は「誰に」「どんな価値提供をするか」です。マーケターでも営業職でもどんな仕事でも、その基本は変わらないはずです。
なので「どんな人にとって、何が価値になるのか」を感覚的に掴む力は、仕事で成果を出すにあたって必須のスキルだと感じます。ぜひ多くの方に読んでいただきたい本です。
また個人的に、マーケット感覚の鍛え方として挙げられていた「プライシング能力を身につける」という考え方が、非常に参考になりました。
実際にこの本を読んでから「私にとって何が価値になるのか、それにどれくらいお金を払うことができるか」をたびたび考えるようになり、買い物も楽しくなったように思います。
⑥見やすい資料のデザイン図鑑
【本のタイトル】
シーンごとにマネして作るだけ! 見やすい資料のデザイン図鑑
【目次】
- Chapter1 見やすい資料を効率よく作る7つ道具
- Chapter2 見やすい資料のシーン別デザイン図鑑
- Chapter3 ワンランク上の資料にするデザインテクニック
- Chapter4 作業効率が劇的アップ! 便利なチートテクニック
- Appendix 見やすい資料に使える便利ツール
- 見やすい資料の配色早見表
本のタイトルにもあるとおり、シーンごとにさまざまなパワポのデザイン例が載せられています。
それらをマネして作るだけで、デザインセンスのある資料を最短で作ることができるため、とてもおすすめな本です。
新卒の際は「守破離」を意識して仕事をすることが大切です。
パワポのデザイン一つとっても、0から自分のセンスで作り始めようとするのではなく、すでにある良質なデザインを真似して作ることで、「見やすい資料とはどういうものなのか」を学んでいくことが大切です。
3. キャリア編

「今の働き方にモヤモヤする」「本当にこれがやりたかったことなんだろうか」と思うことは、働いていれば誰にでもあるはずです。
そんな時、自分のこれからのキャリアを思い描いていくのにおすすめな本を紹介します。
①組織にいながら、自由に働く。
【本のタイトル】
組織にいながら、自由に働く。 仕事の不安が「夢中」に変わる「加減乗除(+-×÷)の法則」
【目次】
- 1 +「加」―自由な働き方のOSをインストールする
- (最初から割り切ろうとしてはいけない;今、感じている「モヤモヤ」の正体を突き止める ほか)
- 2 -「減」―強みを磨く
- (これまで「常識」だと思っていたことを手放そう;「積みへらし」の作法―「他由」を捨てれば「自由」になる ほか)
- 3 ×「乗」―独創と共創 仲間と遊ぶ
- (「浮く」と、いいことが起きる;自分の強み同士を掛け算する―「タンポポの綿毛理論」 ほか)
- 4 ÷「除」―何にもしばられない自由な働き方
- (「乗」のワナを乗り越えろ;「一見関連のない複業が、すべてつながっている」ようにする ほか)
働き方には4つのステージ(加・減・乗・除)がある、ということが書かれている本です。
加(+)ステージ:できることを増やす、苦手なことをやる、量稽古。仕事の報酬は仕事
減(-)ステージ:好みでない作業を減らして、強みに集中する。仕事の報酬は強み
乗(×)ステージ:磨き上げた強みに、別の強みを掛け合わせる。仕事の報酬は仲間
除(÷)ステージ:因数分解して、ひとつの作業をしていると複数の仕事が進むようにする。仕事の報酬は自由
新卒のうちから、「苦手な仕事はやらず、やりたい仕事だけを選んでやる」という働き方を求めるのは違う、ということがこの本を読めばわかります。
「自分は今『加・減・乗・除』のどの段階にいるのか」「どういう働き方を今はする必要があるのか」を理解することがで、今の仕事への納得感を持つことができたり、今後のキャリアについて落ち着いて見通しを持つことができるため、おすすめです。
②世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方
【本のタイトル】
世界一やさしい「やりたいこと」の見つけ方 人生のモヤモヤから解放される自己理解メソッド
【目次】
- 1 「やりたいこと」探しを妨げる5つの間違い
- 2 なぜ「やりたいことが分からず迷い続けてしまう」のか?
- 3 「やりたいこと探しを最速で終わらせる公式」自己理解メソッド
- 4 人生を導くコンパス「大事なこと」を見つける
- 5 「得意なこと」さえ見つければ何でも仕事にできる
- 6 「好きなこと」を見つけて努力とサヨナラする
- 7 「本当にやりたいこと」を決めて「本当の自分」を生き始める
- 8 「人生を劇的に変える」自己理解の魔法
働いていると、「自分が本当にやりたいことってなんなんだろう」「今の仕事は、本当に自分がやりたかった仕事なんだろうか」と思うときがあると思います。
そんな時、自分の「やりたいこと」がなんなのかを見つけるのにおすすめなのがこの本です。
この本では、「好きなこと」×「得意なこと」が「やりたいこと」である、と書かれており、
自分の「好きなこと」「得意なこと」がなんなのかを炙り出すために、たくさんの質問が用意されているので、ワークとして進めていきやすいです。
一度、自分の「やりたいこと」「大切にしたい価値観」がなんなのかが明確に言語化できれば、日頃の仕事にも納得感や目的意識を持って取り組むことができるようになります。
③働くみんなの必修講義「転職学」
【本のタイトル】
働くみんなの必修講義 転職学 人生が豊かになる科学的なキャリア行動とは
【目次】
- オリエンテーション なぜ「転職学」が「人生の必修」なのか
- 第1講 まずは転職の方程式「D×E>R」を学ぼう
- 第2講 「自己認識」を高めれば転職力も高まる
- 第3講 孤独になるな!「転職相談」の大切さ
- 第4講 日本人と「大人の学び」の心理分析
- 第5講 地方転職から副業まで「流行りの転職」の虚実
- 特別集中講義 日本の転職の歴史学
- 第6講 新しい組織に馴染む科学的な方法
- 第7講 これだけは知りたい「ミドルの転職」
- 最終講 「辞めた会社」との付き合い方とは
「第二新卒」として転職する人も多くなっているこの時代、「転職とはどういうものなのか」について、あらかじめきちんと正しく知っておくことは大切だと思います。
この本は、「どういう時に人は転職をするのか」「最近の流行りの転職の実態」「転職後の、新しい組織への馴染み方」など
「転職とは」について、研究結果のデータをもとに理論的に書かれた本になります。
私はこの本の「マッチング思考ではなくラーニング思考」という考え方が非常に参考になりました。
この本を読んで、「会社を選び間違えた」「今の会社が全て悪いんだ」「転職していい会社に入れれば、今の状況は良くなるはず」という考えはずれている、ということに気づくことができました。
この本でそれを学べたからこそ、私は転職という甘い誘惑に流されず、今の会社でやれることをやりきろうと考え、仕事に真っ直ぐ向き合うことができるようになったと思います。
④科学的な適職
【本のタイトル】
科学的な適職―4021の研究データが導き出す最高の職業の選び方
【目次】
- 序章 最高の職業の選び方
- 1 幻想から覚める―仕事選びにおける7つの大罪
- 2 未来を広げる―仕事の幸福度を決める7つの徳目
- 3 悪を取り除く―最悪の職場に共通する8つの悪
- 4 歪みに気づく―バイアスを取り除くための4大技法
- 5 やりがいを再構築する―仕事の満足度を高める7つの計画
この本に書かれていた「人間の脳にはバグがある」という考えに非常に納得しました。
感情に流されるまま、なんとなくの自分の感覚で仕事や職場選びをするのではなく、自分を信じすぎず、理論的に自分に合った職を探す必要性を感じさせられた本です。
この本では「どういう職場は幸福度が高くて、どういう職場は幸福度が低いか」などについて詳しく解説をしてくれています。
「自分が今の仕事にモヤモヤしているのはこの要素が満たされないからだ」もしくは「今の仕事場は別にいうほど悪い職場に分類はされないのではないか」など、あらためて自分の置かれている環境を俯瞰して見ることができるため、おすすめの本です。
4. その他編

最後に、私が新卒研修で受けた中で、最も心に響いた教えをみなさんにもお伝えします。
個人的には、この部長から受けた研修が、これまで学んだどんなことよりも一番役に立っています。
①ワンピース(ONE PIECE)
私が新卒で入社した会社で、ある部長の方に「おすすめ本を教えてください」と聞いたところ、大真面目にワンピース(ONE PIECE)を紹介されました。
ワンピースも言わずと知れた名著で、ワンピースから学べる点は多くあると思いますが、その部長の方は、特に以下2点が参考になるとおっしゃっていました。
- 「海賊王に俺はなる」というルフィのマインド。ルフィは「海賊王」という夢が手に入りそうになってからいうのではなく、手に入る前から高らかに宣言をしている。
→ビジネスはマラソン。40年走ろうと思うと並大抵の気持ちではできない。「周囲の期待に応えたい」などの動機では弱すぎる。自分の中の「衝動」がないと、疲れてしまう。どれだけ野心を持って働けるかが大事。 - いいチームとは「多様性があるチーム」。「自分はここはできるけどここはできない」と認め合い、最終的に「ここはあなたの方ができる」と言えるようになるのがよい
自分は果たしてどれだけルフィのように野心を持って、冒険しながら働くことができているか。
自分の強み、チームメンバーの強みを理解し、助け合いながら働けているかなど、振り返ることができるためおすすめです。
仕事に忙殺されて、日常にワクワク感などを感じられなくなっているときなど、息抜きがてらにワンピースをもう一度読んでみるのはいかがでしょうか。
※スター・ウォーズ|STAR WARS
本ではありませんが、せっかくですので、前述の部長の方がおすすめしてくださったもう一つの作品、スターウォーズについてもご紹介させていただきます。
その部長は「スターウォーズ1~3は、人間を教えてくれる作品だ」とおっしゃっていました。
自分よりスキルが高い人は、この世にアホほど存在します。しかし最終的に評価されるのは、スキルがある人ではなく「マインド」がある人です。
そこで「自分の方があの人より仕事ができるのに…」と思ってしまう人ほど、ダークサイドに落ちてしまいます。
ビジネスは、スキルを競うものではありません。ビジネスのゴールはスキルにはありません。ビジネスは検定などの世界ではないのです。
「自分はスキルで人と競おうとしていないか」「これを成し遂げたいという野心を持って働くことができているか」を常に振り返ることが大切である、ということを新卒のうちに知ることで、
ダークサイド側に落ちてしまうことを防ぐことができるようになったのは、本当に大きかったなと思っています。
5. 最後に
以上、新卒・新社会人向けおすすめ本15選をご紹介しました。まとめると
となります。

新しい物事にチャレンジするのは、誰だって勇気がいることです。
自分の実体験が、少しでも皆さんの心を軽くしたり、背中をそっと押すものになることができたら嬉しいです。
このサイトでは、後輩を応援したいという気持ちで、これからもさまざまな記事を執筆していきますので、ぜひご覧ください。
 わたしたちについて
わたしたちについて
またこのブログでは、他にもキャリア・おすすめ本について記事を執筆していますので、ぜひ併せてご覧ください。