この記事では、
- 「産休に入ったので読書をしようと思っている」
- 「他の産休中の人がどんな本を読んでいるのか知りたい。おすすめ本を知りたい」
という方に向けて、
- Kindle Unlimitedで読める本の中で、私が産休中に読んでよかったと思う、カテゴリー別の本
について、実体験ベースでお伝えします。

まるで1個上の先輩とサシ飲みに行ったかのように、「有益な情報が得られた」「心が少し軽くなった」「また明日から頑張ろう」、そんな気持ちになっていただけたら嬉しいです。
(※Kindle Unlimitedのメリットについては、以下記事で別にまとめているため、ぜひ併せてご覧ください)
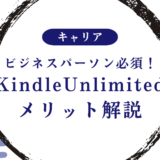 【Kindle Unlimited】ビジネスパーソンなら入れておくべき7つの理由
【Kindle Unlimited】ビジネスパーソンなら入れておくべき7つの理由
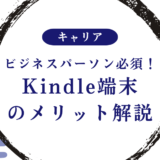 読書習慣が身に付く!ビジネスパーソンにKindle端末がおすすめな4つの理由
読書習慣が身に付く!ビジネスパーソンにKindle端末がおすすめな4つの理由
1. 「子育て」に関する本

まず何よりも、産休・育休というのは子育てのために休暇をいただいているわけなため、「子育て」の勉強をするために様々な本を読みました。
その中で、特に印象に残った本をご紹介いたします。
①はじめてママ&パパの育児
【本のタイトル】
はじめてママ&パパの育児
【目次】
- 第1章:月齢別(0カ月~3才)赤ちゃんの発育・発達、暮らし、気になることQ&A
- 第2章:毎日のお世話の基本
- 第3章:おっぱい・ミルクの基礎知識、気がかりQ&A
- 第4章:離乳食・幼児食の進め方
- 第5章:生活リズム
- 第6章:事故&ケガ対策と応急処置
- 第7章:知っておきたい予防接種
- 第8章:赤ちゃんがかかりやすい病気とホームケア
安定の「主婦の友社」が出版している雑誌です。
赤ちゃんが生まれた後の育て方について、網羅的に情報を記載してくれています。
「0ヶ月目の発達」から「離乳食」「ケガの応急処置」まで、気になるポイントを広く網羅的に取り扱ってくれているため、「最初の一冊」として適切な本だと考えています。
②子どもを伸ばす言葉 実は否定している言葉
【本のタイトル】
子どもを伸ばす言葉 実は否定している言葉
【目次】
- 第1章 子どもの視点に立ってみる言葉
- (子どもの自己肯定感は、親の言葉かけで決まる?;「やりたくない!」と言われたら、そのまま受け入れたほうがいい? ほか)
- 第2章 子どもが自分で考え始める言葉
- (宿題や習い事の練習をやりたがらないとき、どんな言葉が効果的?;「自分で考えなさい」と言えば本当に考える子になる? ほか)
- 第3章 子どもの力を認めて伸ばす言葉
- (気づけばいつもぐちゃぐちゃ…片付け上手に育てたいのに;子どもの習い事選びで失敗したくない! ほか)
- 第4章 子育ての不安が消える言葉
- (小学校入学までにできるようにしておくたった一つのことは?;「赤ちゃんはどこから生まれてくるの?」の質問にはどう答える? ほか)
こちらは、「赤ちゃんの育て方」というよりは、子供が産まれて数年経った後の子育てについて書いている本になります。
まだ先のことではありますが、この本を読むと、「子供が幼稚園生〜小学生くらいの年齢になってくると、こういう困難が待ち受けているのか」と未来のことを見通すことができるようになり
「自分は〇〇のように子供と接することができるような親になりたいな」と今後の子育てについて思いを馳せることができるため、おすすめです。
所々に四コマ漫画も挿入されており、非常に読みやすい点もおすすめポイントになります。
③犯罪心理学者は見た危ない子育て
【本のタイトル】
犯罪心理学者は見た危ない子育て
【目次】
- 序章 子育ては4タイプ
- 第1章 自分で決められない子―過保護型の身近な危険
- 第2章 自分で考えて動けない子―高圧型の身近な危険
- 第3章 人の気持ちがわからない子―甘やかし型の身近な危険
- 第4章 愛に飢えて暴走する子―無関心型の身近な危険
- 付録 子育て4タイプのチェックリスト
- 終章 親が気づけば子どもも変わる
こちらは、少年鑑別所・拘置所に勤務し1万人以上の非行少年・犯罪者の心理分析をしてきた著者が、
「こんな育てられ方をした子供は、このような犯罪者になる傾向がある」ということについて具体例を挙げながら説明している本です。
他の子育て本とは違った切り口で子育てについて書かれている本になります。
子育てには「過保護型」「高圧型」「甘やかし型」「無関心型」の4タイプがある、という分類が非常にわかりやすく
「自分はどのタイプに当てはまっているだろうか」と自分を客観視したり、家庭内で子育ての方針について話し合う・見直す際に参考にできる本だと感じました。
2. 「保活」に関する本

私は、育休が終わった後にまた会社に復帰する予定だったため、保育園探しについても早いうちから情報収集をしなければと思い、数冊本を読みました。
その中で、特にわかりやすかった本を以下でご紹介いたします。
①保育園選びのお悩み一気に解決!保育士ママ直伝 保活虎の巻
【本のタイトル】
保育園選びのお悩み一気に解決!保育士ママ直伝 保活虎の巻
【目次】
- 第一章:保育園ってどんなところ?
- 1. 保育園、幼稚園、認定こども園の違いは?
- 2. 1号、2号、3号認定って何?
- 3. 保育園あれこれ
- 4. 0歳児が一番預けやすいってほんと?理由を解説!
- 5. 0〜2歳で預けるってかわいそう?私なりに思うこと
- 第二章:保活の進め方
- 1. 一番大切!気持ちの確認
- 2. 保活の流れをおさえよう!
- 3. 申込み後すること
- 第三章:園見学でのポイント
- 1. 家や職場からのアクセスの良さ
- 2. 園や先生方の雰囲気
- 3. 保育内容
- 4. 持ち物の量
- 5. 行事や保護者会のこと
- 第四章:こんな時どうする?〜保活のイレギュラーあれこれ〜
- 1. 産休明けで入園したい
- 2. きょうだい同時に入園したい
- 3. 妊娠を機に退職…それでも入れる?
そもそも保育園ってどんなところなのか、よく聞く「認可外保育園」とはなんなのか、など保活の基本について網羅的に抑えてくれている本です。
保活について勉強する際の「最初の1冊」としておすすめです。
②保育園に受かるための 7原則:保活サイト運営者が送るどこよりもわかりやすい保活の実用書
【本のタイトル】
保育園に受かるための 7原則:保活サイト運営者が送るどこよりもわかりやすい保活の実用書
【目次】
- 1. 敵を知る
- 保活はなぜ難しいのか
- 2. スケジュールを知る
- 入園の期限を知る
- 自分の子が入園しやすい月を知る
- 申込の期限を知る
- 申込前のタスク計画を立てる
- 3. 入園確率を把握せよ・できれば上げよ
- エリアによる入園確率
- 世帯条件による入園確率
- 自分の家庭の指数(保育園の入りやすさ)の確認方法
- 指数・優先度は上げられる!?
- 4. 候補園リストを作成せよ
- 候補園の効率的な洗い出し方
- リストの作り方(フォーマットあり)
- 候補園の絞り込み方
- 5. まずは1園抑えよ
- 認可外保育園は事前予約が可能な場合あり
- 認可外保育園のデメリットは克服可能
- 6. 落とし穴に注意せよ
- 引越しリスクと対策
- 転職のリスクと対策
- 復帰後時短切り替えのリスクと対策
- 7. フルタイム共働き・3児ママ直伝!仕事と家庭の両立手段
- 家事育児の外注手段を知る
- 子供の体調不良、急なお休みに備える三つの根回し
- 補助金を活用する
保活の基本的な進め方・スケジュールについて体系だってまとめてくれているだけでなく
「引っ越しリスク」「転職リスク」「復帰後時短切り替えリスク」など、「そんなところにも落とし穴があるの!?」という、自分だけではキャッチアップできていなかったであろう点についても解説をしてくれており、
保活を計画的に進めるにあたって非常に参考になった本のため、おすすめです。
3. 「自分の心をコントロールすること」に関する本

私は「どんな親になりたいか」を考えたときにまず「イライラしている親にはなりたくない」という思いがありました。
そこで、少しでも自分の心をコントロールする術を身につけるべく「アンガーマネジメント」や「自分の心を満たす方法」について知識を得るために、いくらか本を読みました。
以下では、特に印象に残った本についてご紹介いたします。
①怒りが消える心のトレーニング―図解アンガーマネジメント超入門
【本のタイトル】
怒りが消える心のトレーニング―図解アンガーマネジメント超入門
【目次】
- はじめに 怒りに振り回されない生活を送るために
- 第1章 とっさの怒りを切り抜ける7つの対症療法―「怒り」への対処はアレルギーと同じ!?
- 第2章 怒らない自分をつくる9つの習慣―他人ではなく自分を変えよう
- 第3章 ムダに怒らない人になる10の心の持ち方―ムダに怒らない人になろう
- 第4章 上手な怒り方7つのルール―怒ることはタブーではない
- 付録 実生活に役立てるアンガーマネジメント
- おわりに 「心を整える」とチャンスが巡ってくる
この本では「まず、とっさの怒りに対してどう対応するかを習得する」「その後、そもそも怒りにくい性格に自分を持っていく」という流れで解説がされており、事例も具体的でわかりやすく読みやすい本でした。
また「怒ることは決して悪ではない」「判断基準は、怒った後に後悔するかしないか」という考え方が非常に参考になりました。
②最高の体調 進化医学のアプローチで、過去最高のコンディションを実現する方法
【本のタイトル】
最高の体調 進化医学のアプローチで、過去最高のコンディションを実現する方法
【目次】
- 第1章 文明病
- 古代ではあり得ない「肥満」という現象
- 豊かになればなるほど鬱病が増えるのはなぜ?
- 「炎症」と「不安」─現代人の不調の原因を取除く ほか
- 第2章 炎症と不安
- 炎症編
・長寿な人の共通点は、体の「炎症レベル」が低い
・内臓脂肪が減らない限り、体は燃え続ける ほか - 不安編
・不安は記憶力、判断力を奪い、死期を早める
・危険を知らせるアラームとしての役割 ほか
- 炎症編
- 第3章 腸
- 現代人の腸はバリアがどんどん破れている
- 衛生的な生活が免疫システムを狂わせる
- 食生活を「再野生化」して腸を守る ほか
- 第4章 環境
- 「偽物の自然」にもリラックス効果がある
- 人間の脳は人間関係をつくることが苦手
- 「時間」をかけて脅威システムをオフにする ほか
- 第5章 ストレス
- 過剰なストレスが全身を壊していく
- ハマるとやめられない「超正常刺激」の正体
- スマホの使用時間が長い人ほど不安が大きい ほか
- 第6章 価値
- ぼんやりした不安を解消するたった1つの方法
- 「価値」と「目標」はどこが違うのか?
- 幸福感が高まるのは「貢献した」とき ほか
- 第7章 死
- 死の不安に対して原始仏教が示した解決策
- 畏敬の念をもつと体内の炎症レベルが下がる
- 自然、アート、偉人、感嘆するのはどれ? ほか
- 第8章 遊び
- もし「遊び」を奪われたら人はどうなる?
- 娯楽があふれているのに楽しくない
- メタ認知を使ったフィードバック ほか
この本では、「そもそもなぜ現代人は、疲れやすく集中力が続きにくく、イライラしやすい状況に置かれているのか」ということについて理論的に解説がされており
「だから自分はこれまでこういう場面で不調を感じていたのか」と適宜納得しながら本を読むことができました。
私はこの本を読んでから、日常生活に「自然」を取り入れることや、一つ一つの作業について「ながら」で行うのではなくマインドフルネスを意識しながら集中して行うということをするようになり、
結果少しずつ心のスッキリさを感じられるようになりました。
③感性のある人が習慣にしていること
【本のタイトル】
感性のある人が習慣にしていること
【目次】
- 序章 感性を養う「5つの習慣」
- 第1章 感性を養う「観察する習慣」
- 第2章 感性を養う「整える習慣」
- 第3章 感性を養う「視点を変える習慣」
- 第4章 感性を養う「好奇心を持つ習慣」
- 第5章 感性を養う「決める習慣」
「アーティストと呼ばれる人は、こういう思考でこのように感性を磨きながら生きているのか」と気づきを得られた本でした。
特に印象的だったのが「毎朝起きた際に、その日の気温を肌の感覚で当ててみる」というものでした。
「日頃の何気ない小さな一瞬をどう拾い上げて感じていくか」について様々な例を挙げられており、確かにそういう習慣を続けていったら感性の豊かな人になることができそうだな、と視野が広げられた本です。
4. 「自己分析」に関する本

私の性格上、おそらく育休から復帰した後には、「こんなに子育てと仕事を頑張って、自分はどうなりたいのか」とある時急にプツンときてしまうということが起こるのではないかと考えています。
そこであらかじめ「自分の人生の指針・軸」をブレずに定めておくことで、上記の状態になった際にメンタルが落ち込みすぎることを予防しておこうと思い、自己分析に関する本を数冊読みました。
以下では、その中で特に印象に残った本についてご紹介いたします。
①物語思考
【本のタイトル】
物語思考―「やりたいこと」が見つからなくて悩む人のキャリア設計術
【目次】
- オープニング 「物語思考」とはなにか?
- ステップ1 頭の枷を外しながら、なりたい状態を考える
- ステップ2 「キャラ」の作り方
- ステップ3 「キャラ」に行動させよう
- ステップ4 キャラが最高に活きる環境を作ろう
- ステップ5 物語を転がそう
- エンディング 物語にゴールはない
多くの自己分析本は、「過去を振り返ることで自分の性格や得意なことについて分析をする」というやり方をするように思いますが、
こちらの本は過去を振り返ることはせず、「将来の自分はどうなっていたいか」を0ベースで発想させ、そのためにはどう行動をしていけばいいかを考えていく、というやり方で自己分析をする本になっています。
自分を「キャラ」に見立てて、「こういうキャラの人はこういう場面でどう行動するのか」を考えてそれに則って動く、という考え方が新鮮で、個人的に非常に参考になった本です。
②世界一やさしい「才能」の見つけ方
【本のタイトル】
世界一やさしい「才能」の見つけ方
【目次】
- 1 なぜ、才能に気づける人と気づけない人がいるのか?
- (見つけ方を学んだことがないから、才能が見つからない;才能を見つけると、生き方が180度変わってしまう ほか)
- 2 学ぶと世界の見え方が一変する「才能の公式」
- (公式を知らないまま、才能について考えてはいけない;「なんでできないの?」と思ったら才能を見つけるチャンス ほか)
- 3 自分の中に眠る宝物を掘り起こす「才能を見つける技術」
- (「自分には才能がない」。その考えは間違っている;「これが私の才能だ!」と揺るがない自信を持つには? ほか)
- 4 あなたらしく輝けるようになる「才能を活かす技術」
- (「自分を受け入れられた」で満足してはいけない;グングン前に進む人が実践している「ヨットの法則」 ほか)
- 5 誰も真似のできない強みを手に入れる「才能を育てる技術」
- (あなたはまだ自分の可能性の10%しかつかっていない;仕事とは「当たり前」と「ありがとう」の交換 ほか)
自分の得意・不得意がわかっていると、不得意な分野について適切に周りに助けを求めることができるようになったり、得意を伸ばして日々をイキイキと過ごしていくということがしやすくなると考えています。
この本ではその名の通り、自分の「才能」の見つけ方についてワークを用意してくれており、この本のワークを愚直にこなしていけば自分の「才能」が定義できるようになっています。
この本で自分の「才能」を定義してみて、それを夫などに共有することで、家庭内での役割分担や今後のキャリアについての話し合いに繋げることができると感じるため、おすすめな本です。
③ソース―あなたの人生の源はワクワクすることにある。
【本のタイトル】
ソース―あなたの人生の源はワクワクすることにある。
【目次】
- 第1部 あなたのワクワクに宿る奇跡の力
- 第2部 誰もが信じているウソ
- 第3部 ソースを実行するための、六つの方法論
- 第4部 人生の方向性と仕事とお金
- 第5部 ワクワク人生を生み出す四つの条件
- 第6部 ソースの車輪
この本の特徴的なところは、「やりたいと思うことは『全て』やれ」ということを説いているところだと考えています。
これまでの自分は、やりたいと思うことがあったとしても、無意識に子育てや仕事などに囚われ、それを言い訳にして諦める理由を探しがちになっていたように思います。
しかしこの本を読んで、「自分が本当にやりたいことはなんなのか」「それを実現するためにはどう行動していけばいいのか」について真剣に腰を据えて考えることができるようになったため、おすすめな本です。
5. 最後に
以上、産休中に読んでよかった本11選をご紹介しました。まとめると
- 【「子育て」に関する本】
①はじめてママ&パパの育児
②子どもを伸ばす言葉 実は否定している言葉
③犯罪心理学者は見た危ない子育て - 【「保活」に関する本】
①保育園選びのお悩み一気に解決!保育士ママ直伝 保活虎の巻
②保育園に受かるための 7原則:保活サイト運営者が送るどこよりもわかりやすい保活の実用書 - 【「自分の心をコントロールすること」に関する本】
①怒りが消える心のトレーニング―図解アンガーマネジメント超入門
②最高の体調 進化医学のアプローチで、過去最高のコンディションを実現する方法
③感性のある人が習慣にしていること - 【「自己分析」に関する本】
①物語思考
②世界一やさしい「才能」の見つけ方
③ソース―あなたの人生の源はワクワクすることにある。
となります。

新しい物事にチャレンジするのは、誰だって勇気がいることです。
自分の実体験が、少しでも皆さんの心を軽くしたり、背中をそっと押すものになることができたら嬉しいです。
このサイトでは、後輩を応援したいという気持ちで、これからもさまざまな記事を執筆していきますので、ぜひご覧ください。
 わたしたちについて
わたしたちについて
またこのブログでは、他にも子育てについて記事を執筆していますので、ぜひ併せてご覧ください。










