この記事では、
- 「妻から育休を取得してほしいと言われたけど、男性育休って何をするの?」
- 「育休を取得する予定だけど、具体的に何をすればいい?」
という方に向けて、
- 男性が育休を取得した方が良い理由
- 育休期間中に具体的にやること
について、自分が育休を半年取得した経験を踏まえ、実体験ベースでお伝えします。
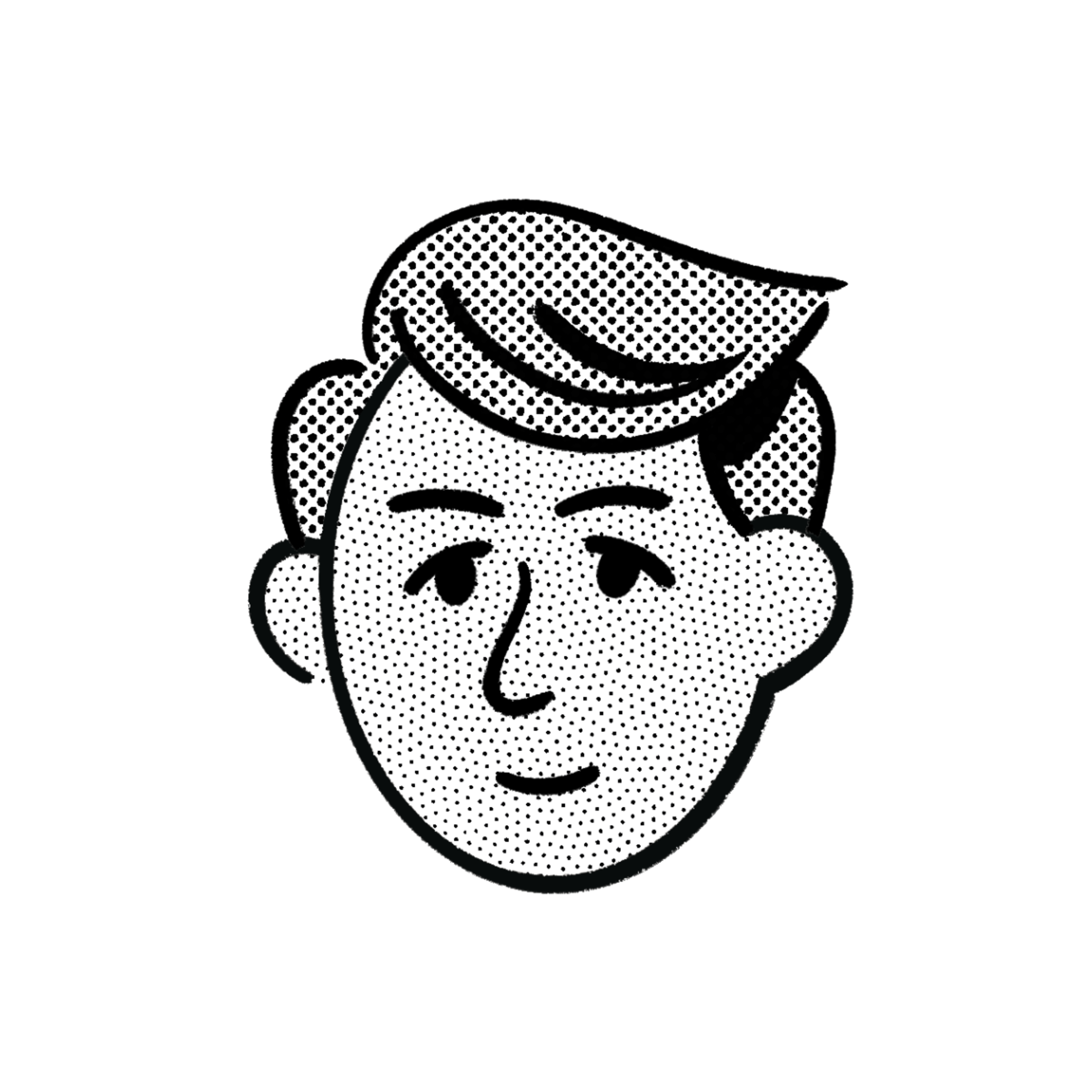
まるで1個上の先輩とサシ飲みに行ったかのように、「有益な情報が得られた」「心が少し軽くなった」「また明日から頑張ろう」、そんな気持ちになっていただけたら嬉しいです。
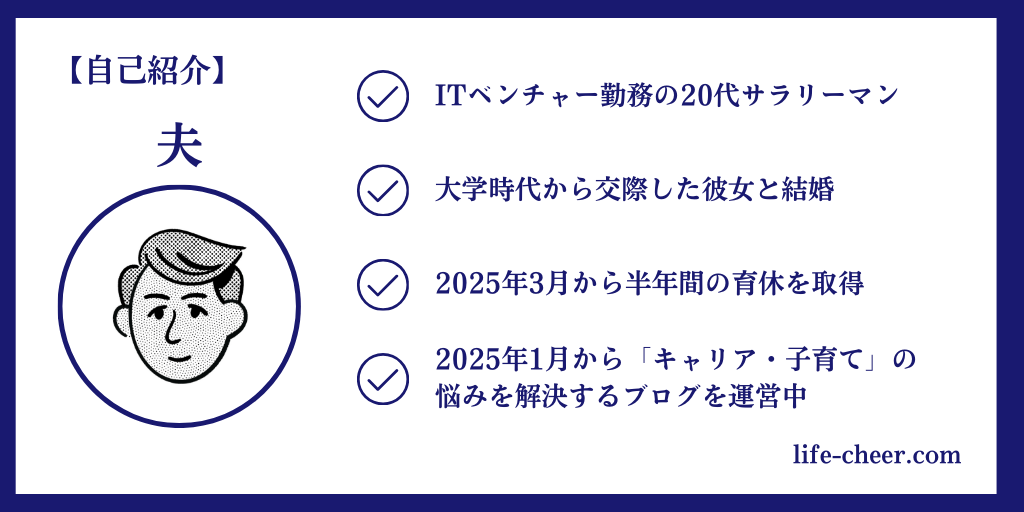
1. 育休制度についてわかりやすく解説
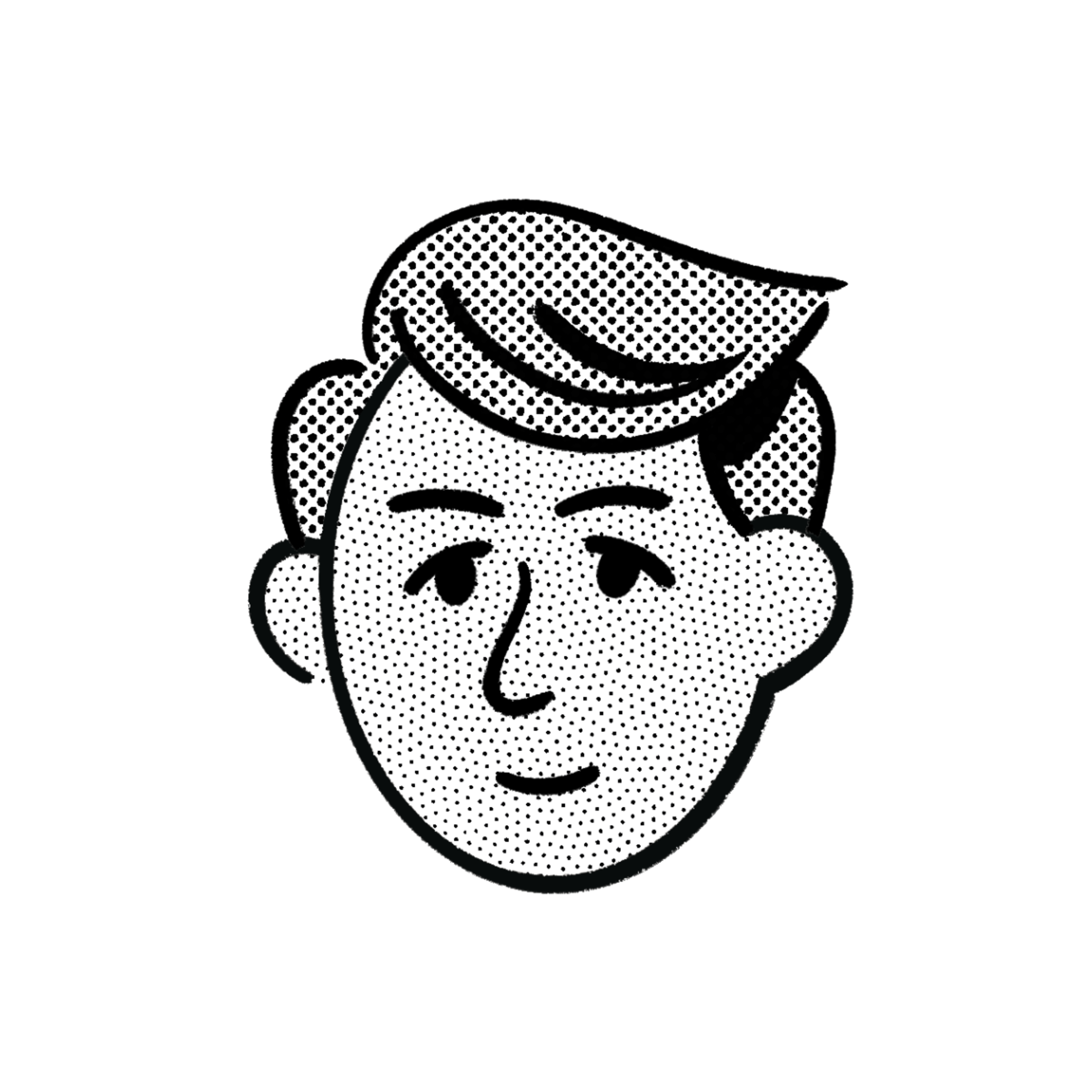
まずは育休制度について、わかりやすいように一問一答形式で解説します!
ここでは、わかりやすく伝えることを重視しているので、
より詳しく知りたいという方はは、厚生労働省の情報を参照してください。
そもそも育休ってなに?
- なんで育休を取得する必要があるの?
- 出産は身体的な負荷が大きく、産後の女性は安静にして体力回復に努める必要があります!
女性の子育てや生活の負担を減らすためにも、男性の育休は必要だと考えられており、国も男性の育児休業の取得を推進しています。
- 休んでいる間の収入が心配なんだけど…
- 雇用保険制度で、育児休業給付金と出生後休業支援給付金がもらえるから安心してください!
最初の28日間は、今の手取りと変わらないくらい給付金がもらえます!
- どのくらいの期間休めるの?
- 原則は、子どもが生まれてから1年間、育休を取得することができます!
自分は半年間取得しました!
詳しい内容は、厚生労働省が育児・介護休業法に関する動画を作成しているので、
こちらをご覧ください!
2. 押さえておきたい!会社への伝え方
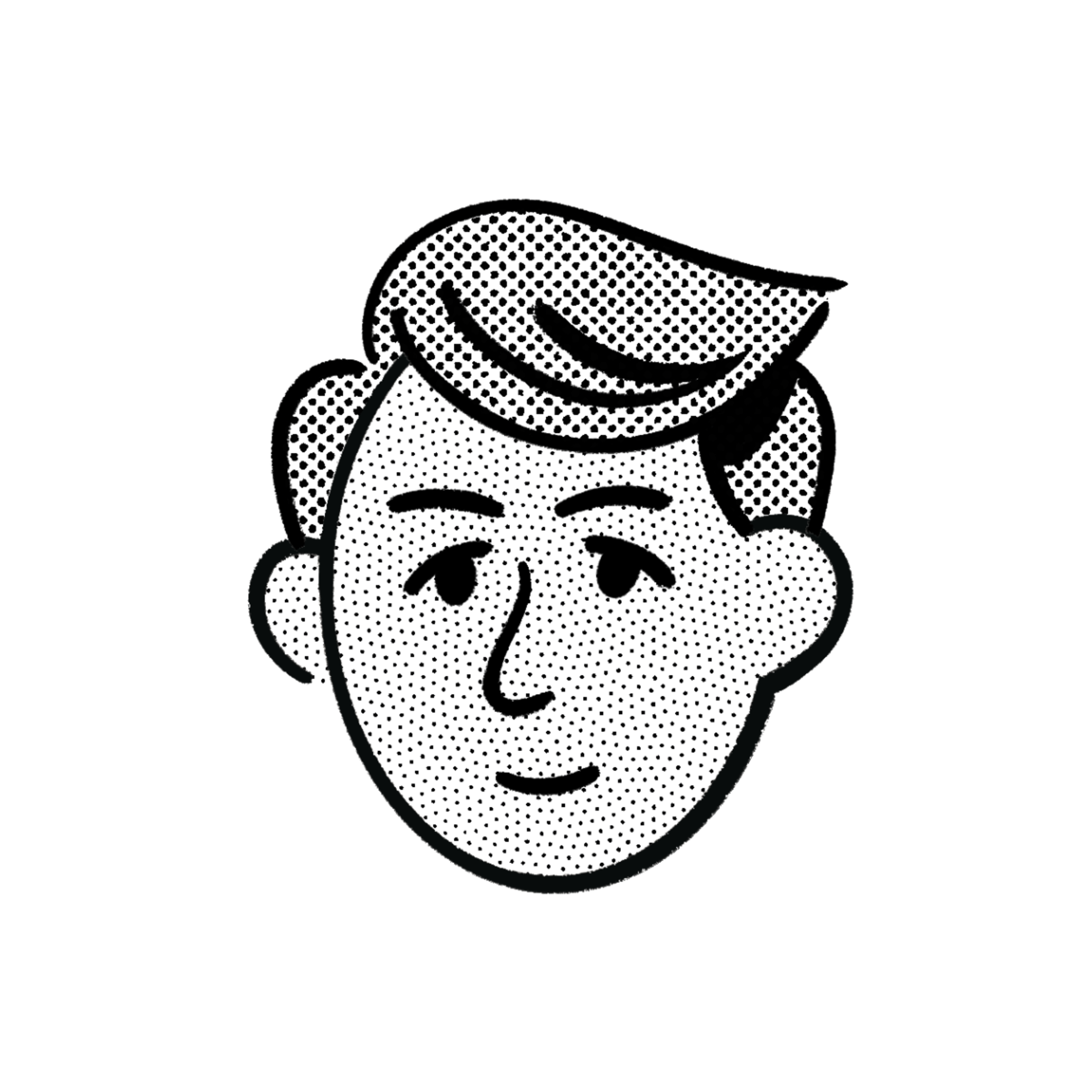
育休の概要を理解したら、育休を取得する旨を会社に伝える必要があります。
育休の取得について、会社へ伝えるときのポイントをお伝えしますので、確認してください!
いつ伝えるのがいい?会社へ伝えるタイミング
妊娠12週以降の早いタイミングがおすすめ!
妊娠が発覚しても焦らずに、会社や周囲へ伝えるタイミングを妻と話し合うことが重要です。
伝え方に関するポイントは以下の記事にまとめているので、ぜひこちらも合わせて読んでみてください!
周囲への感謝の気持ちを忘れずに
育休を取得することは、取得する人にとってはメリットが大きいですが、
会社にとっては、他の人が業務を引き継ぐ必要があります。
業務の調整や業務量の増加など、周囲のサポートがあって、成り立っているので、
感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。
社内の人への挨拶の仕方やメールの例文についても、他の記事で紹介しているので、参考にしてみてください。
3. 男性育休でやるべきこと【12個】
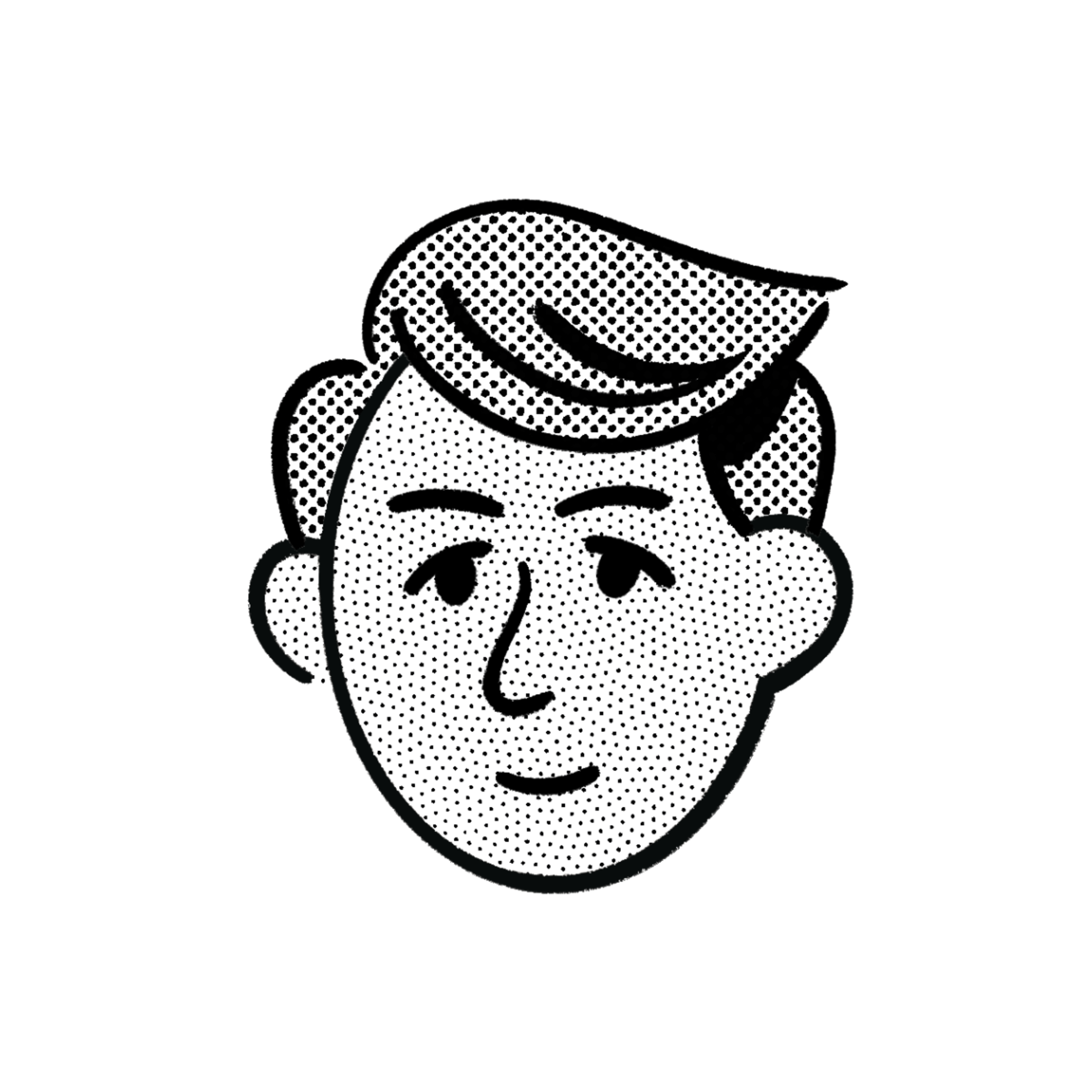
育休はただの休みではありません!
育休期間中にやるべきことをまとめたので、確認してみてください!
家事・育児編【6個】
出産後1〜2ヶ月は、自分が家事を全て行うという気持ちでいましょう。
妻は出産による傷を治すために、安静にしていることが重要です。
育休期間だけでなく、育休前から家事を積極的に行うことで、育休に向けた練習と妊娠中の妻のサポートになります。
自分は普段から家事を行なっていたため、育休を開始した時にもスムーズに生活していくことができました。
普段、あまり家事をやらないという方向けに、自分が家事で意識していることをお伝えするので、
ぜひ参考にして、今日から実践してみてください!
普段、妻が家事をしているという場合は、スムーズに家事をこなせるように、工夫をしている場合があります。
特に、料理や洗濯などはこだわりがある可能性が高いので、注意が必要です。
そのため、妻が工夫しているポイントを確認しつつ、まずは手伝いやすいところから始めていきましょう。
家事にかかる時間を把握することで、同時並行で効率的に作業を進めることができるようになります。
まずは、以下のような時間を把握しましょう。
- 洗濯には何分かかる?
- 洗濯物を干すのには何分かかる?
- 洗濯物を畳むには何分かかる?
- ご飯が炊けるには何分かかる?
- お風呂を掃除するのには何分かかる?
- 食器を洗って片付けるのには何分かかる?
- 部屋の掃除には何分かかる?
- 買い物に行って帰ってくるのには何分かかる?
これらを把握することで、
「ご飯が炊けるのには、約1時間かかるから、その間に20分で洗濯物を干して、20分でお風呂掃除をしよう。
余った時間は、ご飯の準備を手伝おうかな」
といったように、家事を効率的に進められるようになります。
授乳以外に関しては、妻がいなくても、できるようにしましょう。
妻と一緒に子育てをしていくことで、お互いの負担を下げ、子育ての苦労や楽しみを分かち合うことができます。
- ミルクをあげる(授乳の場合は妻)
- 哺乳瓶を洗う
- おむつを替える
- 沐浴をする
- あやして寝かしつけをする
- 育児グッズを買い揃える・買い足す
- 離乳食をつくる(生後5〜6ヶ月頃から)
- 子どもの成長について調べる
これらの日常的な育児に加えて、以下のようなイベントごともあります。
- 内祝い(親戚への出産報告)
- お七夜
- 命名式
- お宮参り
- お食い初め
- ハーフバースデー
- 初節句
これらのイベントは人によっては、行わないなどの意向もあるかもしれませんが、
実施の有無について、妻と話し合っておくと安心です。
家事・育児でやることが多くて、不安に感じた方は、自分たちの育休生活のタイムスケジュールを
以下の記事で公開しているので、こちらも読んでみてください。
家事・育児をすることは、妻の行動を最小限に抑えるためのサポートになります。
しかし、家事・育児をするだけではなく、妻の精神的な面のサポートをする必要があります。
- 産後の痛みはいつまで続くんだろう?
- なんだか心が暗くなってくる。なかなか眠れない。
- 食欲が湧かない。
- 赤ちゃんが泣き止まないけど、大丈夫かな?
- 赤ちゃんのこの症状はなんだろう?大丈夫なのかな?
出産を経験している人は、自分の身体の変化や赤ちゃんのことについて、覚えている感覚もあるかもしれませんが、
初めての場合は、わからないことばかりで不安になることも多くあります。
そんな時に、一緒に悩みに寄り添ったり、時には安心感を感じさせられるような存在になったりすることで、
妻が精神的に落ち込まないようにサポートすることが重要です。
産後は、ホルモンバランスの変化の影響もあり、メンタルが落ち込む人もいます。いわゆる産後うつと言うやつですね。
妻の変化を常に気にしながら、声掛けをすることで、少しでも違和感を感じた時に、
相談してもらえるような関係性を築いていきましょう。
出産では、さまざまな申請が必要となります。中には給付金がもらえるものもあるため、しっかりと確認しておきましょう。
- 出産・子育て応援交付金
- 出産育児一時金
- 出産手当金 ※夫ではなく、妻が妻の勤める会社とやりとりをするもの
- 育児休業給付金・出生後休業支援給付金
- 出生届
- 児童手当
- 市町村独自の制度など
以下でそれぞれの制度について、簡単に説明します。
妊娠届出の面談を実施と出産後の赤ちゃん訪問を条件に申請することが可能になります。
それぞれ5万円ずつ、計10万円を受け取ることができます。
各市区町村のHPから「出産・子育て応援交付金」について調べることで、申請方法が出てきますので、確認をしましょう。
予約をすることで、面談がスムーズに実施できるので、
日程を調整して、妻と一緒に参加できるようにしましょう。
出産にかかる費用を50万円支給してくれる制度になります。
医療機関等への直接支払制度を利用することで、出産時に大きな出費をしなくて済むようになるため、
産院が確定したら、医療機関の窓口に出産育児一時金の申請・受取の代理契約を結びたい旨を申し出ましょう。
妻の産休中にもらえる手当です。
以下のサイトで出産手当金がいくらもらえるのか、計算できるので、
気になる方は試してみてください。
https://keisan.casio.jp/exec/system/1528684593
また、出産手当金は、産休(出産日の翌日から56日間)が終わった後に申請をして、それから1ヶ月後くらいにもらえるものになるので、出産してから約3ヶ月くらいかかることを認識しておきましょう。
出産手当金を早く受け取りたいという方は、分割して申請する方法もあるので、
以下のサイトを読んでみてください。
https://manekomi.tmn-anshin.co.jp/shigoto/17600971
出産手当金の申請方法については、妻から妻の会社へ確認しておいてもらうようにしましょう。
育児休業期間中にもらえる給付金です。
出生後休業支援給付金は、2025年4月から新しく創設される制度です。
両親ともに育休を14日以上取得することで、最大28日間分は育児休業給付金と合わせて、
手取りが100%相当になるように給付金を受け取ることができます。
育児休業給付金の支給額は、育休取得開始から180日間は67%、180日以降は50%分の給付率です。
より詳しく知りたい方は、以下の厚生労働省のHPを確認してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000135090_00001.html
生まれてから14日以内に市区町村へ提出する必要があります。
住んでいる地域、子どもが生まれた地域、自分たちの本籍がある地域のどこかに、
「出生届、母子健康手帳、届出人の本人確認書類」を持っていきましょう。
出生届の提出と合わせて、児童手当の申請もすることができます。
マイナンバーカードもしくは健康保険証、振込先の口座情報が確認できるもの(キャッシュカードなど)を持っていきましょう。
0歳から3歳までは月額15,000円、高校卒業まで月額10,000円の手当を受け取ることが可能です。
振り込みは、2ヶ月分まとめてになるので、認識しておきましょう。
市区町村独自の制度については、各市区町村のHPを確認してください。
子どもの成長は思っている以上に、早いです。
日頃から子どもの写真や動画をたくさん撮影しておくことで、
振り返った時に、成長を実感できるようになります。
自分は、子育てをしている様子も記録できるように、以下の三脚を購入しました。
自分が住んでいる地域の保育園事情がどうなっているかを調べておきましょう。
妻が産休中に子育てや保育園に関する本を読んで、記事にまとめているので、
以下の記事も参考にしてみてください。
ライフプランニング編【4個】
これまでライフプランを作ったことがない人は、このタイミングで妻とライフプランを作りましょう。
これまでに作ったことのある人は、これを機に、見直しをしてみることをおすすめします。
以下のような要素を時間軸で可視化していくことで、将来の設計に役立てるものです。
- 家族の年齢
- ライフイベント(住宅の購入、子どもの出産、子どもの入学・卒業、転職など)
- 想定支出(固定費、基本生活費、ライフイベントにかかる支出など)
- 想定収入(家族の給与収入など)
- 想定資産
これらの要素を可視化することで、
「このタイミングは家計が赤字になりそうだな。」
「もっと節約しないと、養育費が賄えなくなるかもしれない」
「本業だけでは、収入が足りないから、副業を始めた方が良さそう」
などのイメージが具体的になってきます。
もちろん、すべての要素が明確にわかるわけではないので、
大体どのくらいかなという想定の数字を入れてみる形でも構いません。
まずはライフプランを作ることで、将来のイメージを想像することが重要です。
日本FP協会がライフプランを作るためのテンプレートを公開しているので、ぜひ参考にしてみてください。
https://www.jafp.or.jp/know/fp/sheet
ライフプランを作っていくと、「自分の人生でやりたいことは何か」を考えるようになります。
例えば、以下のようなことを考えてみるとどうでしょうか?
- 子どもは何人欲しいか?
- 家は持ち家か?賃貸か?
- 車は欲しいか?必要か?
- 将来どこに住みたいか?
- どんな働き方をしたいか?
自分がどんな人生を歩みたいと思っているのかを明確にすることで、ライフプランの精度も上がります。
ライフプランは、最初はざっくりでいいとお伝えしましたが、妻と一緒に自己分析をすることで、
ライフプランが明確になり、将来のことを考えやすくなります。
育休というまとまった時間が取れる機会に、改めて自己分析をしてみることをおすすめします。
妻が産休中に自己分析のワークをやってみた体験談を記事にしているので、ぜひ参考にしてみてください。
ライフプランを作ることで、自分のお金の使い方を把握できるようになります。
自分が何にいくらお金を使っていて、その支出は本当に必要なのかを見直しましょう。
特に、固定費や支出が大きいところから見直しをすることをおすすめします。
日頃の小さな節約よりも、まずは大きな毎月の出費を抑えるようにしましょう。
- スマホの通信費
- 光熱費
- 保険
育休期間を踏まえて、育休復帰後にどんなライフスタイルにするのかを話し合っておきましょう。
仕事に復帰すると、話し合う時間を作ることが難しくなるので、
時間があるうちにある程度想定をしておくことが重要です。
キャリア形成編【2個】
普段、仕事をしている時には、仕事を振り返って、
自分のキャリアを棚卸しする機会を持てている人は少ないのではないでしょうか。
育休期間で、キャリアの棚卸しをして、自分のキャリアと向き合うことで、
今後どんなキャリアを歩んでいきたいのかを考えることが大切です。
ライフプランを考えたり、キャリアプランを考えていくと、
今の自分よりもさらに成長したいという気持ちや豊かな生活を送りたいという気持ちになることが多いと思います。
子育てには、これから多くのお金がかかることを考えると、
副業や資格勉強をすることで、収入アップに繋げていけると、安心感にもつながります。
なんの副業を始めたらいいのか、わからないという方にはブログがおすすめです。
妻がその理由をまとめてくれているので、ぜひこちらもご覧ください。
副業の始め方については、他の記事でまとめていますので、参考にしてみてください。
資格取得については、妻がFP3級を取得した体験談と、簿記2級を取得した体験談をまとめていますので、
ぜひこちらを参考にしてみてください。
4. 最後に
男性育休でやるべきことをまとめると
となります。
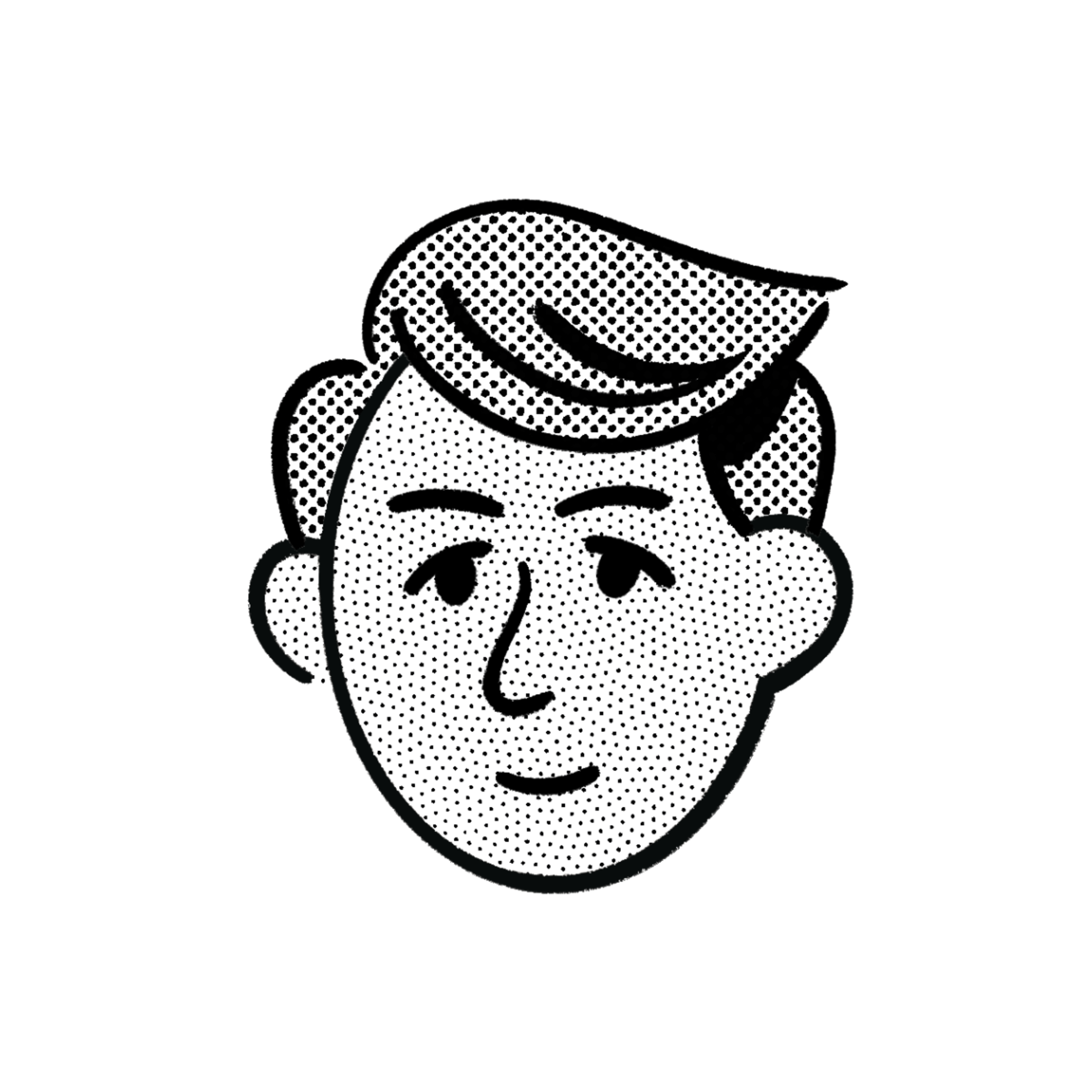
新しい物事にチャレンジするのは、誰だって勇気がいることです。
自分の実体験が、少しでも皆さんの心を軽くしたり、背中をそっと押すものになることができたら嬉しいです。
このサイトでは、後輩を応援したいという気持ちで、これからもさまざまな記事を執筆していきますので、ぜひご覧ください。
 わたしたちについて
わたしたちについて
またこのブログでは、他にも子育てについて記事を執筆していますので、ぜひ併せてご覧ください。

















