この記事では、
- 「生後0ヶ月の赤ちゃんとの生活ってどんな感じ?」
- 「男性が育休を取得してやることって何?」
という方に向けて、
- 生後0ヶ月の1ヶ月間の生活
- とある1日のタイムスケジュール
- ルーティン以外でやること
- 生後0ヶ月の新生児を育てた感想
について、自分が育休を取得した経験を踏まえ、実体験ベースでお伝えします。
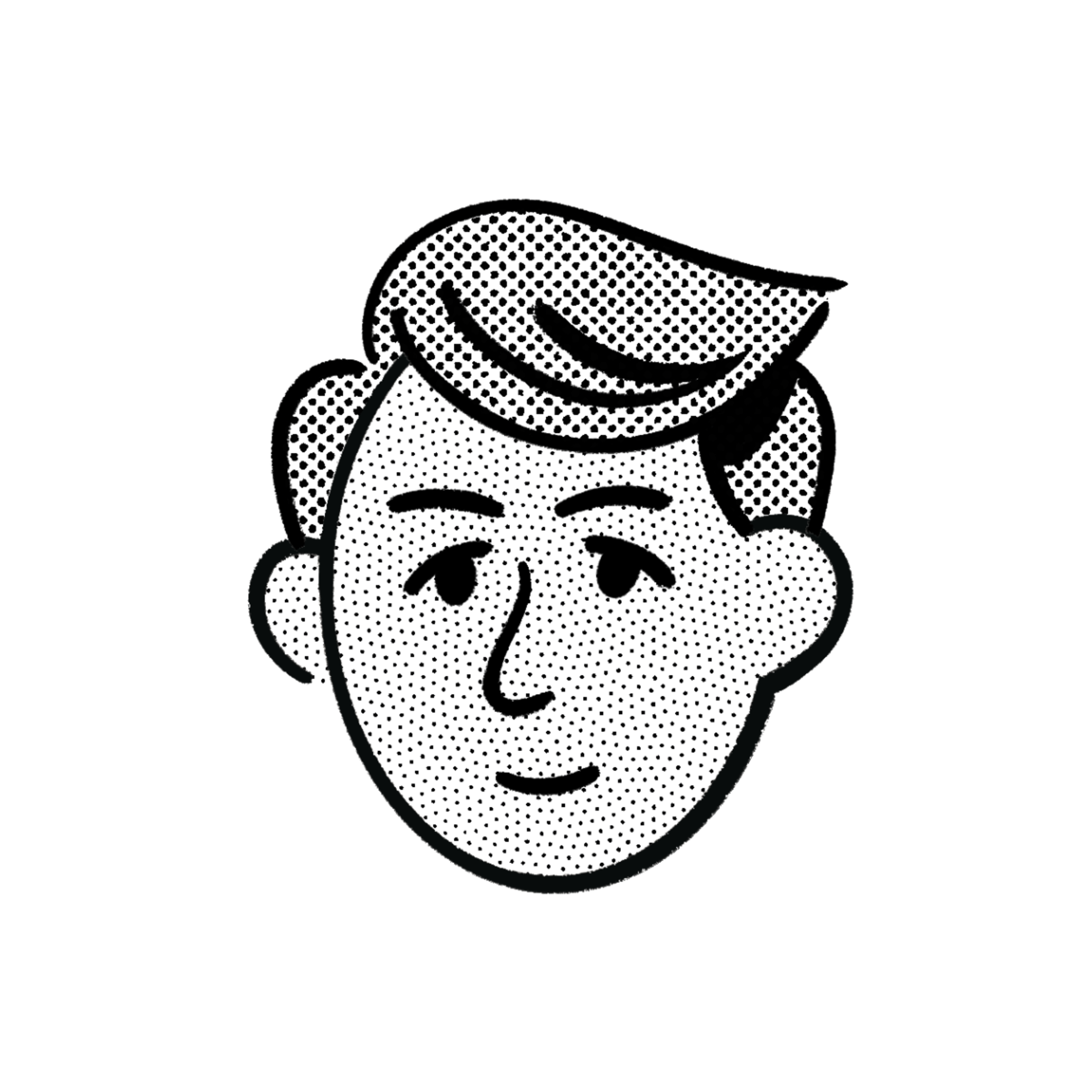
まるで1個上の先輩とサシ飲みに行ったかのように、「有益な情報が得られた」「心が少し軽くなった」「また明日から頑張ろう」、そんな気持ちになっていただけたら嬉しいです。
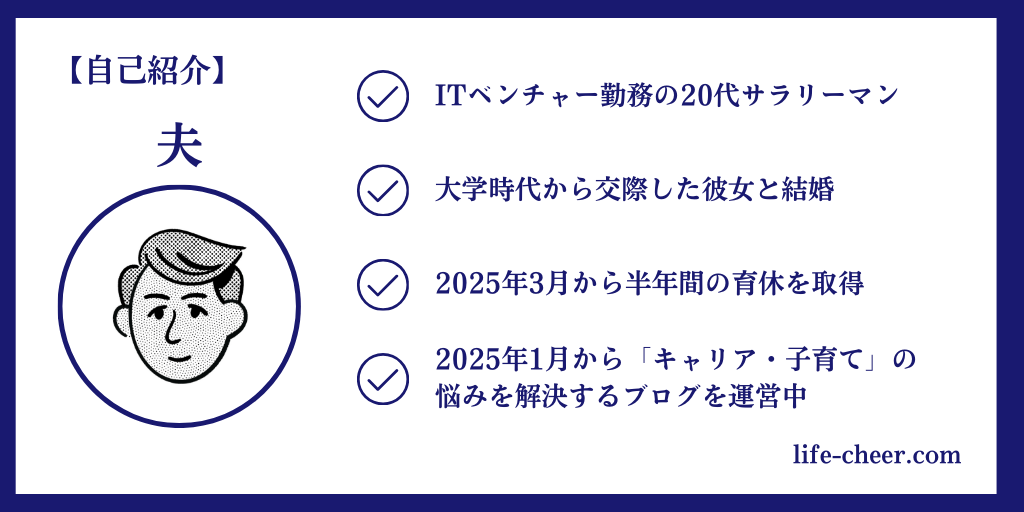
1. 前提となる情報
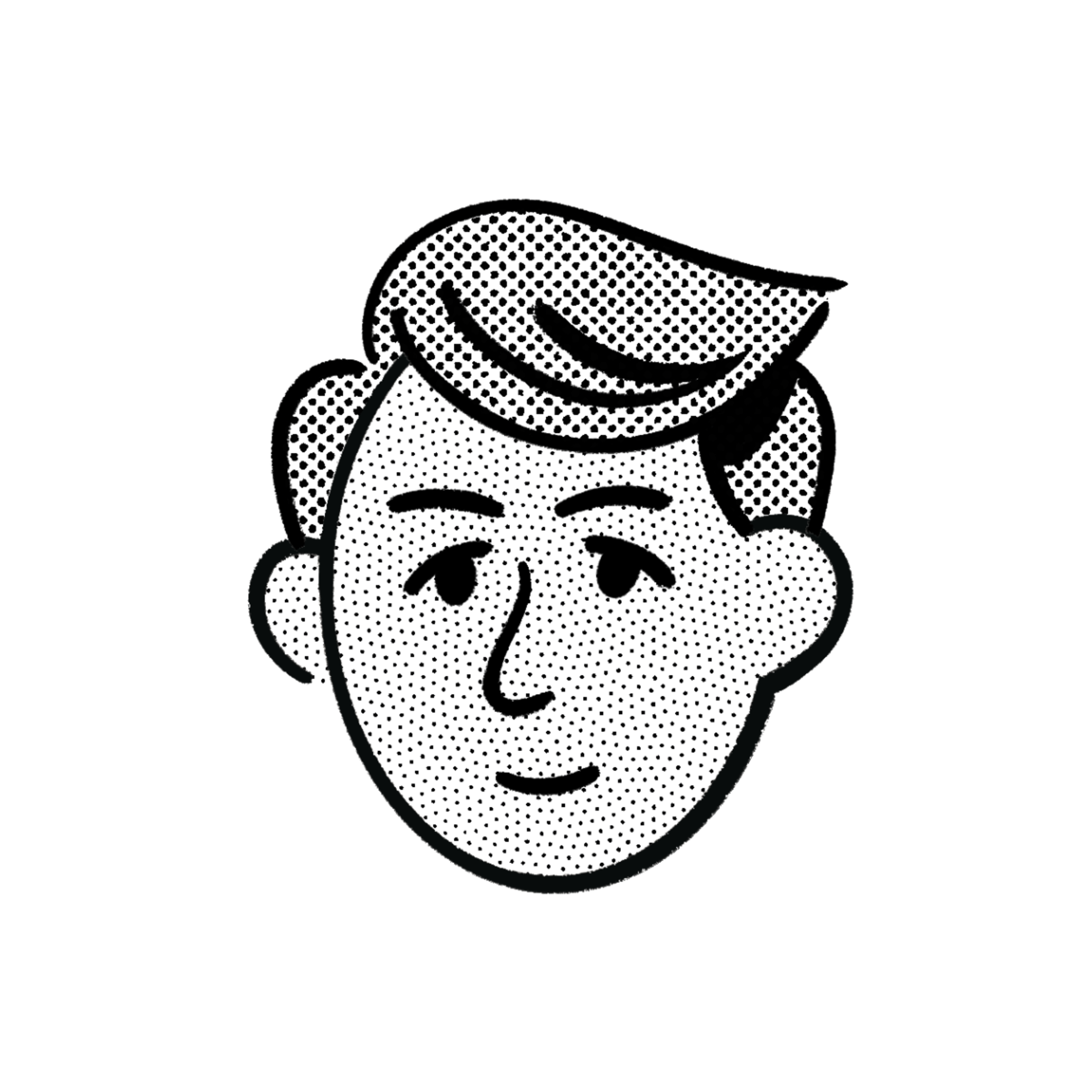
実際のお話を進める前に、自分たちについてお伝えできればと思います。
家族構成
夫(自分)、妻、子(男)の3人家族です。
- 20代
- 都内のITベンチャーに勤務
- 新規事業や企業間のアライアンスを担当
- 約半年前から育休については会社へ相談済み
- 出産予定日(2月22日)から半年間の育休を取得予定
- 20代
- 都内の教育ベンチャーに勤務
- 運営サービスのWebマーケティングを担当
- 約3〜4ヶ月前から産休・育休については会社へ相談済み
- 有給を消化して産前休暇の約2ヶ月前(11月14日)から産休を取得開始
※本来の産前休暇開始は1月12日
- 出産予定日:2月22日
- 実際に生まれた日:3月4日
出産のタイミングで夫(自分)の実家へ引っ越し
- 出産をした病院:これまで社会人になってから住んでいた場所の近郊の病院
- 出産後の生活拠点:夫(自分)の実家 ※出産をした病院から車で片道2時間30分程度離れた場所
- 夫の育休復帰(半年)後:仕事の都合で引っ越し予定
なぜ出産のタイミングで自分の実家へ引っ越しをしたのか、理由についてお話します。
- 自分の母が2年前に末期がんとなり、容態があまり良くないこと
- 昔から自分の母は、「孫を見てから死にたい」と何度も口にしていたこと
※自分は学生時代、恋愛に縁がなかった
母が亡くなってから、「もっと孫の顔を見せてあげれば良かったな」と後悔したくないという思いから、
妻へ相談して、自分が育休復帰をするまで、自分の実家に住むことを合意してくれました。
ちなみに、自分の実家には妻は何度も来ていて、過去には1週間の宿泊などもしていたことがあるため、
自分の両親と全く関わりを持っていないという状態ではありませんでした。
半年間、賃貸を契約したまま空けておくということも考えましたが、
お金がもったいないので、賃貸も解約して完全に引っ越しとしました。
母乳とミルクの割合
最初は3時間おきに、母乳とミルクをあげていましたが、
赤ちゃんの成長が著しく、助産師さんからミルクの量を減らしても良いと言われたので、
生後3週目の段階で、以下のようなやり方に落ち着きました。
- 母乳をあげられる時は、母乳をあげる。足りなさそうだったら、ミルクを追加。
- 妻が眠い時は、ミルクのみで対応。
2. 生後0ヶ月の1ヶ月間の生活
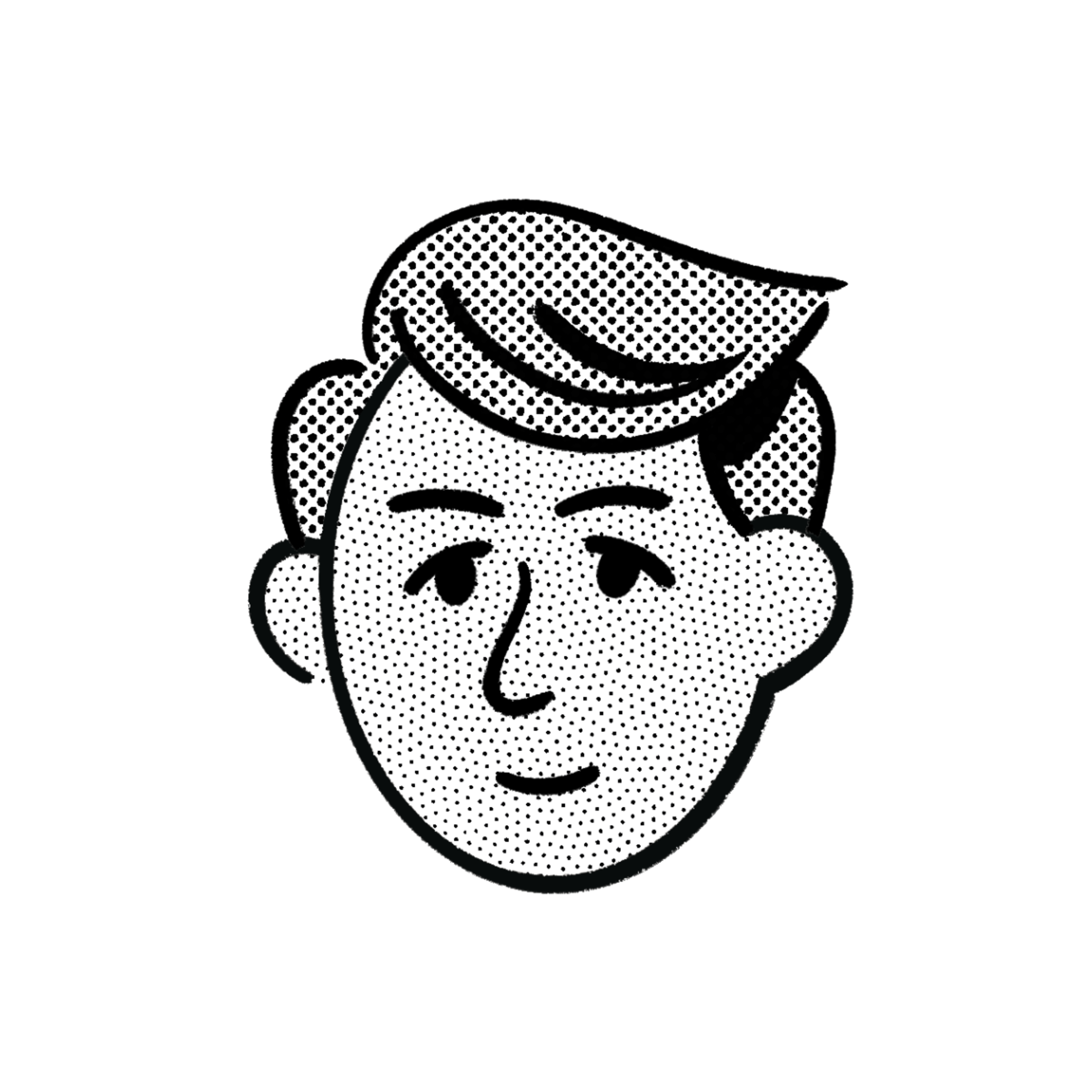
前提でお伝えしたように、出産と引っ越しのタイミングを被せたことにより、
一般的なスケジュールよりもバタバタしたスケジュールになっているかと思います。
生後1週目
- 退院まで(生後3日目まで)
- 出産の立ち会い
- 引っ越し作業・退去の立ち会いなど
- 引っ越しの荷解き・実家の生活空間の整理
- 育児グッズの買い足し・赤ちゃんの服の水通し
- 産後の面会
- 退院後(生後4日目以降)
- 家事全般(買い物・食事の準備と片付け・食事の作り置き・洗濯など)※お風呂掃除は母がやってくれていました
- ミルク、哺乳瓶洗い、オムツ替え、沐浴の準備、沐浴、赤ちゃんの寝かしつけ(沐浴は共同作業)
- 育児グッズの買い足し
- 転出・転入・出産届の提出(@市役所)
- 赤ちゃんに関して情報収集
- 生後3日目までは病院で生活
- 生後4日目から夫の実家で生活
- 授乳を1日に10回以上、ミルク、哺乳瓶洗い、おむつ替え、沐浴、赤ちゃんの寝かしつけ(沐浴は共同作業)
- 赤ちゃんに関して情報収集
妻は、産後の身体の痛みもあるため、基本的に家事全般は全て自分が行っていました。
生後2週目
- 実家の生活空間の整理
- 家事全般(買い物・食事の準備と片付け・食事の作り置き・洗濯など)※お風呂掃除は母がやってくれていました
- ミルク、哺乳瓶洗い、オムツ替え、沐浴の準備、沐浴、赤ちゃんの寝かしつけ(沐浴は共同作業)
- 育児グッズの買い足し
- 免許証の住所変更
- 各種契約中のサービスの住所変更
- 赤ちゃんに関して情報収集
- 会社へ出産報告(手続き関連)
- 授乳を1日に10回以上、ミルク、哺乳瓶洗いおむつ替え、沐浴、赤ちゃんの寝かしつけを主に担当(沐浴は共同作業)
- 生活空間の整理
- 各種契約中のサービスの住所変更
- 赤ちゃんに関して情報収集
この辺りで、生活リズムもだんだんと慣れてきました。
しかし、赤ちゃんについてもいろいろと不安な部分が出てきはじめる頃でもあり、
妻と2人で調べたり、話したりしながら乗り越えました。
生後3週目
- 家事全般(買い物・食事の準備と片付け・食事の作り置き・洗濯など)※お風呂掃除は母がやってくれていました
- ミルク、哺乳瓶洗い、オムツ替え、沐浴の準備、沐浴、赤ちゃんの寝かしつけ(沐浴は共同作業)
- 育児グッズの買い足し
- 赤ちゃんに関して情報収集
- 授乳を1日に10回以上、ミルク、哺乳瓶洗いおむつ替え、沐浴、赤ちゃんの寝かしつけを主に担当(沐浴は共同作業)
- 生活空間の整理
- 赤ちゃんに関して情報収集
新たな生活環境にもひと段落してきて、1日の生活の中で数時間の余裕を感じることができるようになりました。
赤ちゃんが生まれると、毎日が同じ生活リズムになるため、
2週目から3週目あたりで曜日感覚がなくなってきたと感じました。
育休期間を充実させるための過ごし方についても、以下の記事にまとめているので、ぜひ参考にしてみてください!
3. 1日のタイムスケジュール
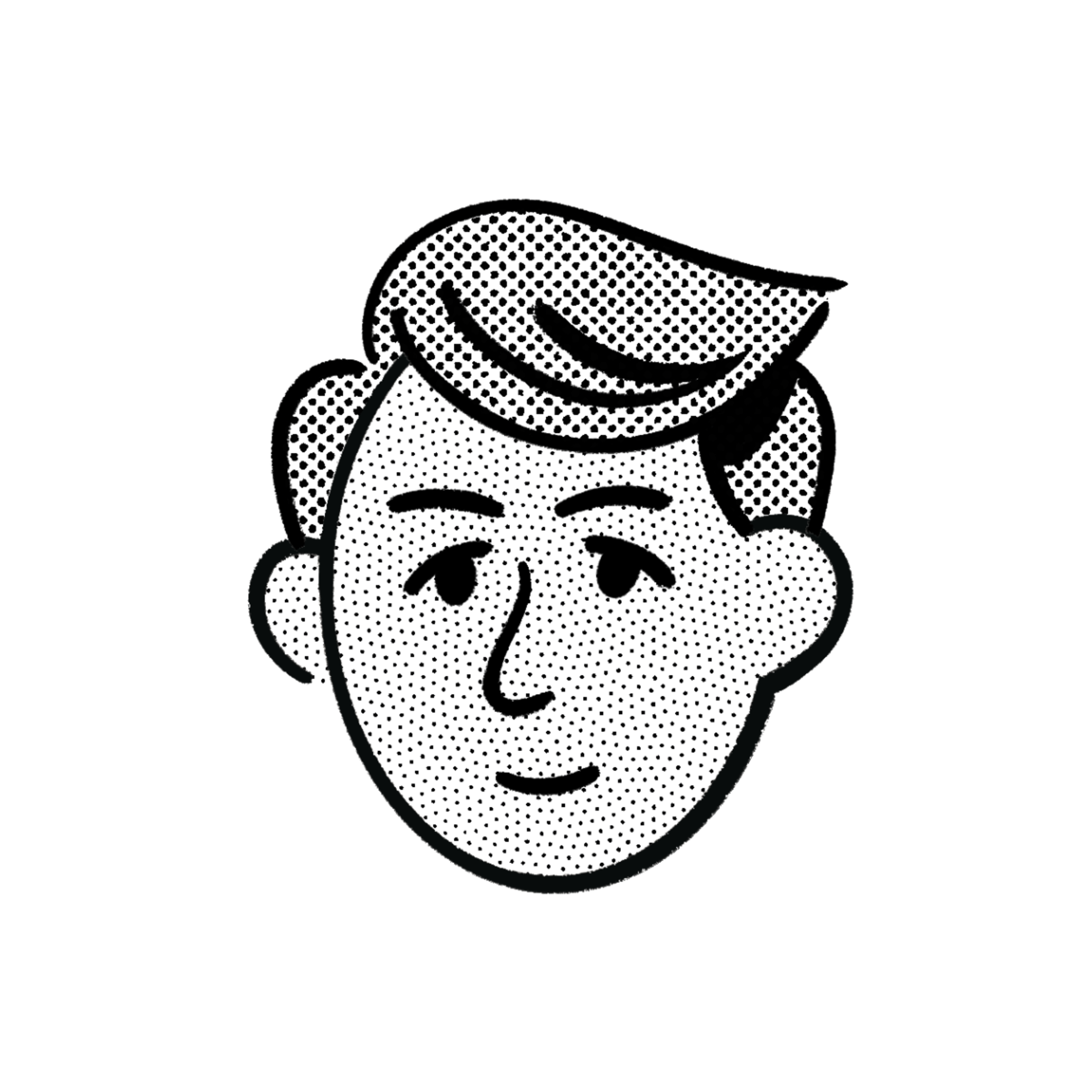
比較的イレギュラーの少ない1日のタイムスケジュールをご紹介します。
このタイムスケジュールをベースとして、その他のやることを調整しています。
0時:睡眠
7時:朝ご飯の準備
8時:朝ご飯 + 赤ちゃんの抱っこ、おむつ替え
8時30分:朝ご飯の片付け
9時:赤ちゃんの抱っこ、おむつ替え
10時:買い物
11時:買い物から帰宅、お昼ご飯の準備
12時:お昼ご飯
12時30分:お昼ご飯の片付け
13時:洗濯、赤ちゃんの抱っこ、おむつ替え、ミルク
14時:洗濯物干し(次の日に畳む)、おむつ替え
14時30分:休憩もしくは食事の作り置き
17時:お風呂(夫)
17時15分:赤ちゃんの抱っこ、おむつ替え、夜ご飯の準備
18時:夜ご飯
18時30分:自分の親に赤ちゃんを見せる
18時45分:沐浴、沐浴の片付け
19時10分:ミルク、寝かしつけ
19時30分:夜ご飯の片付け
20時:休憩、仮眠
22時30分:ミルク、寝かしつけ
23時:哺乳瓶洗い
23時30分:就寝
隙間時間や休憩の時間は、以下のようなことをしています。
- ブログ運営
- SNS
- 読書や勉強
- 映画鑑賞
0時〜1時:睡眠
1時:おむつ替え、授乳、ミルク、寝かしつけ
2時:睡眠
4時:おむつ替え、授乳、ミルク、寝かしつけ、哺乳瓶洗い
5時30分:睡眠
7時:おむつ替え、寝かしつけ
8時:授乳、朝ご飯
8時30分:休息
10時:おむつ替え、授乳
10時30分:休息
12時:お昼ご飯、授乳、おむつ替え
13時:仮眠
15時:休息
17時:授乳
17時20分:お風呂(妻)
18時:夜ご飯、授乳
18時45分:沐浴
19時10分:授乳
19時30分:休息
20時:就寝
休息の間は、以下のようなことをしているようです。
- kindleで子育て本を読む
- アプリで子育てに関する情報収集をする
- 赤ちゃんの写真を見て癒される
4. 子育てのルーティン以外でやること
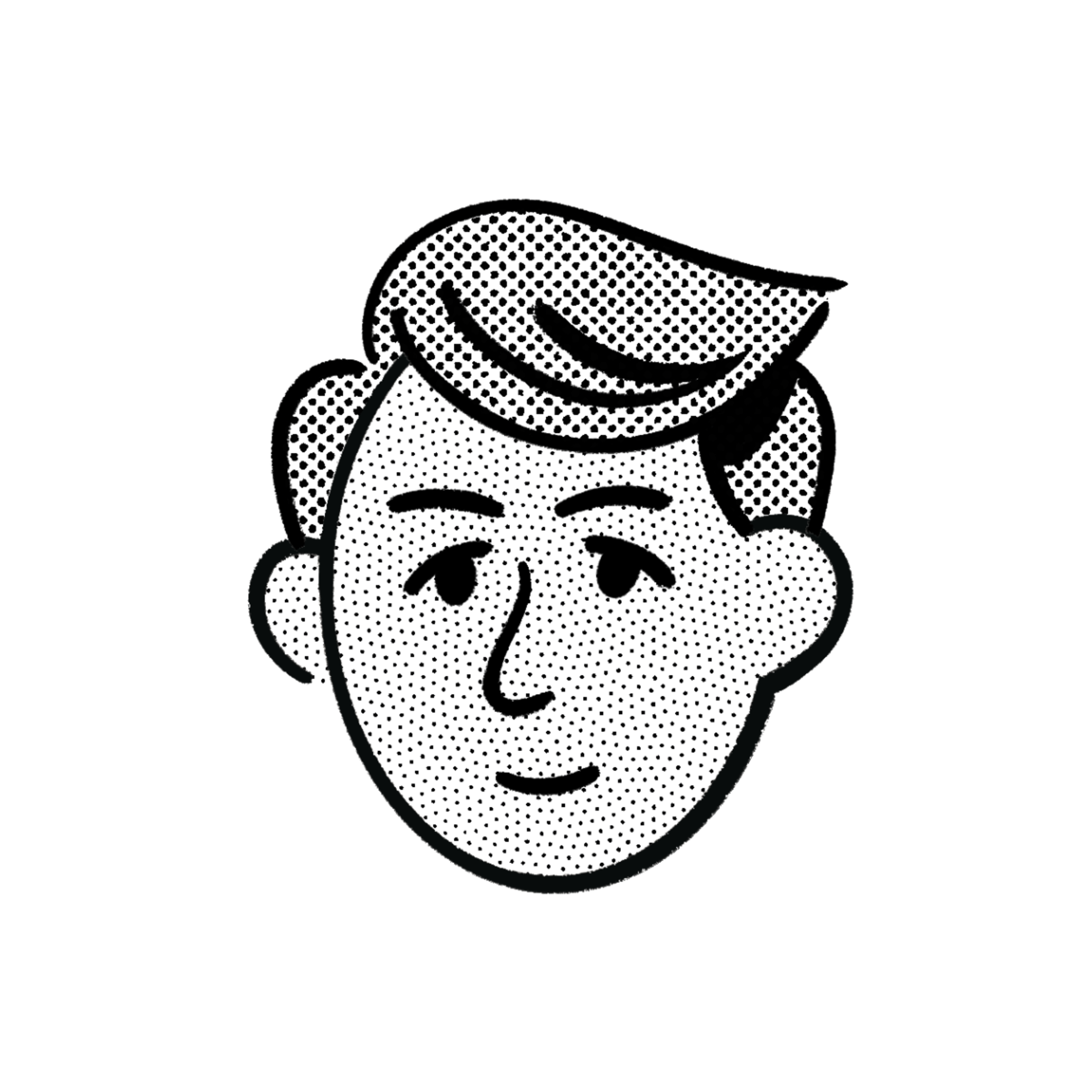
赤ちゃんの「授乳、ミルク、おむつ替え、寝かしつけ、沐浴」以外で、
子育てについてやっていることをご紹介します。
行政からもらった書類の確認
出産届を提出したときに、行政から子育てに関する書類をもらったので、その書類の確認をしました。
以下のような書類を行政から受け取りました。
- 予防接種に関する情報
- 子育て支援金の申請に関する情報
- 子育て支援制度(育児相談的なもの)に関する情報
- 本を数冊、無料で配布する取り組み(図書館に本を受け取りに行く)
- 図書館で行われている読み聞かせの情報
育児休業に関する会社の手続き
以下のような書類の提出を求められたので、対応しました。
- 育児休業申請書
- 届出日
- 部署名
- 社員番号
- 氏名
- 子供の氏名(ふりがな)
- 子供の生年月日
- 子供について提出者本人との続柄
- 休業期間(分けて取得する場合は、分けて記載する)
- 職場復帰予定日
- 休職中の連絡先
- 母子手帳の写し(出生日の証明があるページ)
- 給付金の振込口座の通帳コピー
- 育児休業給付金手続き関する同意書
- 記載内容に同意する旨をチェックする
- 被保険者番号(人事が記載する)
- 被保険者氏名
- 押印
- 夫婦共同扶養収入額確認表
- 健康保険番号、記号
- 育休前の会社からの給与支給額
- 育休取得期間
- 受給する育児休業給付金の概算額
- その他
- 人事労務サービスへ子の情報を追加
- 勤怠申請での育児休業申請
子や妻の体調に関する情報収集
赤ちゃんの変化や妻の産後の変化に対応できるように、情報収集をしました。
- 赤ちゃんについて
- 皮膚が剥がれてきてるけど、乾燥しているのかな? →「新生児落屑」と言うのがあるんだな
- 赤ちゃんのお尻が赤くなっている → これが「おむつかぶれ」かな
- 赤ちゃんが泣き止まない時はどうしたらいいんだろう
→ 基本的な空腹や排泄を確認して、その他は自分を追い込まないことが大事だな
- 妻について
- 痛み止めの「ロキソニン」が無くなってしまった → 同じ効能の市販薬で次の診察日まで耐えられそうかな
- 悪いことした覚えないけど、なんか怒ってる?
→「ホルモンバランスの変化で、メンタルも不安定になりやすい」だろうから、しっかり話を聞いて寄り添おう - 花粉症がひどい → 「クラリチン」と「アレグラ」なら授乳中でも大丈夫そう
また、子育てという観点では、出産前におむつの替え方や沐浴の仕方について、
動画や講義などで勉強をしておいたのはとても役に立ちました。
このように、何かあったときには慌てずに、調べて妻と話し合うことで解決していくことができています。
5. 生後0ヶ月の新生児を育てた感想・学び
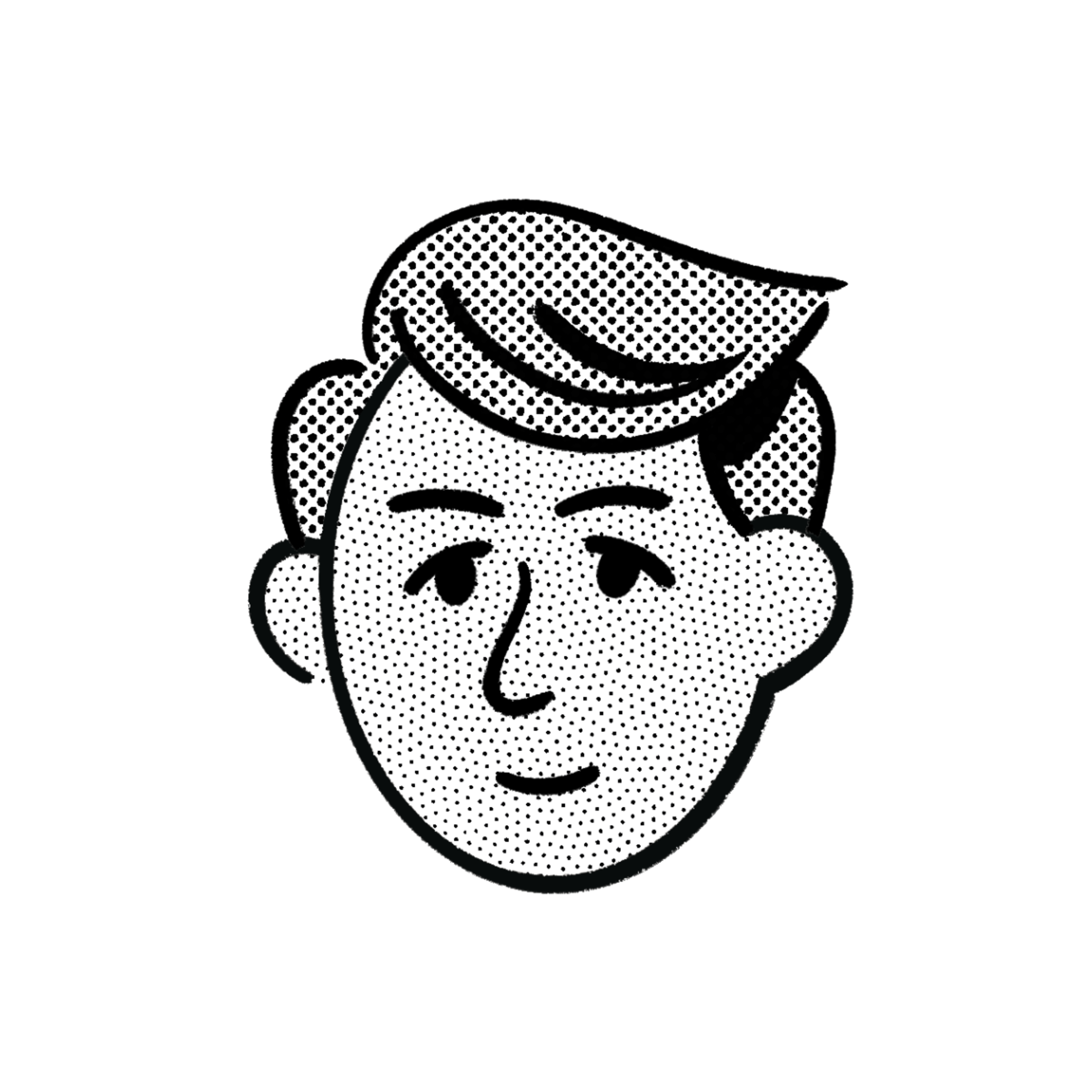
生後0ヶ月は赤ちゃんがいなかった生活から、赤ちゃんがいる生活に大きく変化するタイミングです。
自分が思っているよりも上手くいかなかったり、赤ちゃんから驚かされることばかりですが、
とても楽しい生活を送れているなと感じています。
赤ちゃんは可愛い
これは、子供が生まれた人の多くが口にすると思いますが、
本当に赤ちゃんは可愛いなというのが第一の感想です。
「手を握る」「あくびをする」「手足をバタバタする」「オギャーと泣く」
これらの全てが可愛いなという印象です。
あっという間に成長する赤ちゃん
3週目頃には、生まれた時よりもぷっくらとしていて、早くも「大きくなったな!」と感じました。
たった1ヶ月で大きく変化する赤ちゃんを見ると、育児休業を取得して、
赤ちゃんと過ごす時間はとても貴重な時間だと感じました。
休みの日という感覚がない
前述しましたが、平日と土日で生活リズムが変わらないため、稼働する日と休みの日という感覚がなくなります。
そのため、体力的にも精神的にも少し疲れたなと思っても、休むことで育児休業を取得しているのに、
ダラダラとしてしまっているという罪悪感のようなものを感じてしまい、
上手く休むことができないという状態になりました。
育児のために仕事を休むのが育児休業だとしても、常に気を張り続けていると疲れてしまうので、
睡眠時間はしっかりと確保し、夫婦で自由時間を決めて、
決めた時間はお互いに好きなように過ごすというような形にすることをおすすめします。
妻をいかに休ませられるか
自分は妻の出産に立ち会いをしたときに、
「自分は一生をかけても、こんなに大変な思いをすることはできないだろう」と思いました。
そして、産後にも傷の痛みを感じている様子を見ると、
妻の身体的な負担をいかに下げられるかという気持ちになりました。
そのため、夫は育児休業を取得することで、妻を支えていくことが重要だと思います。
6. 最後に
男性育休の1日のタイムスケジュールをまとめると
- 実際のスケジュールはこちら
- 産後の妻は、基本的に授乳以外で動けないと思った方が良い
- 授乳以外は、自分の仕事だと思って家事全般をしっかりとやること
まだ出産前の方は、今から始めることをおすすめします。 - 夫婦ともに、睡眠時間をしっかり確保することを意識しよう
- わからないことや不安なことがあったら、調べて夫婦で話し合おう
となります。
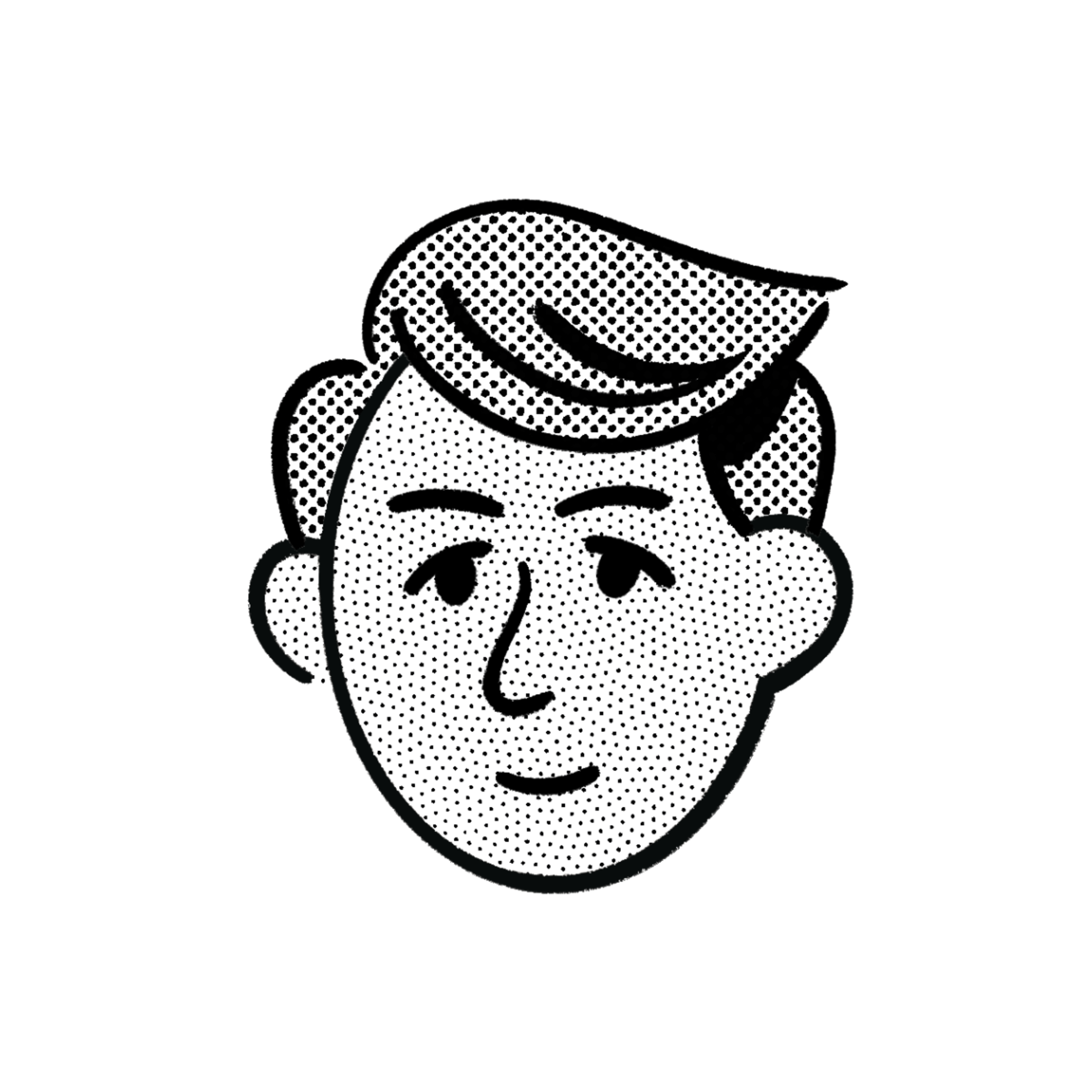
新しい物事にチャレンジするのは、誰だって勇気がいることです。
自分の実体験が、少しでも皆さんの心を軽くしたり、背中をそっと押すものになることができたら嬉しいです。
このサイトでは、後輩を応援したいという気持ちで、これからもさまざまな記事を執筆していきますので、ぜひご覧ください。
 わたしたちについて
わたしたちについて
またこのブログでは、他にも子育てについて記事を執筆していますので、ぜひ併せてご覧ください。










