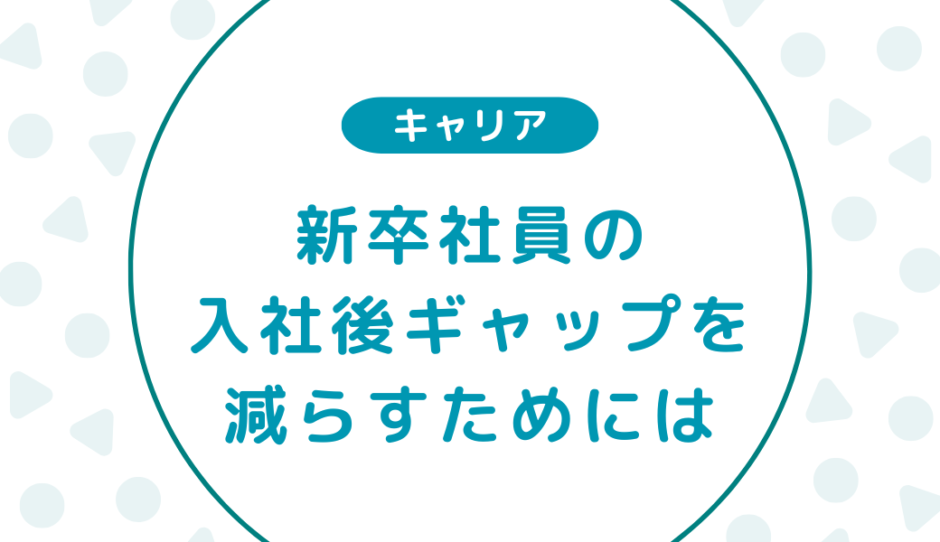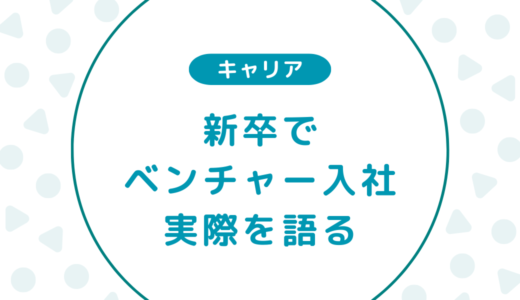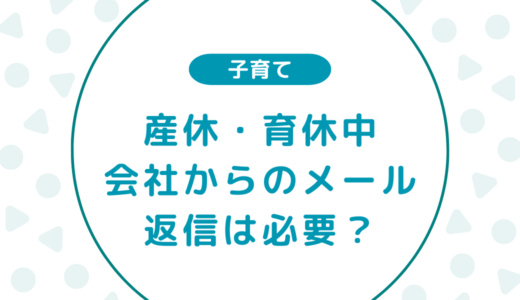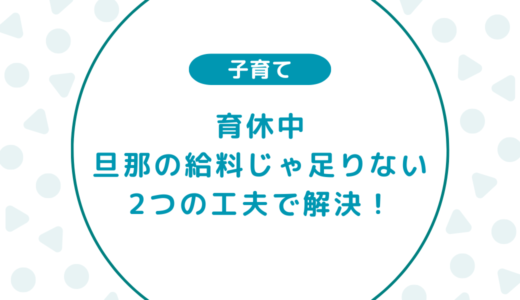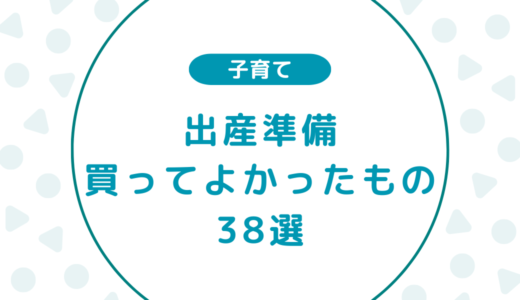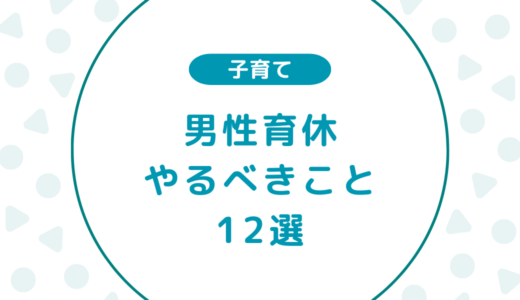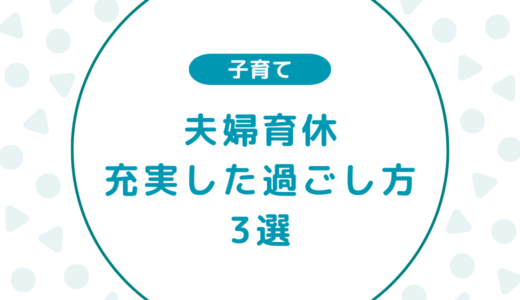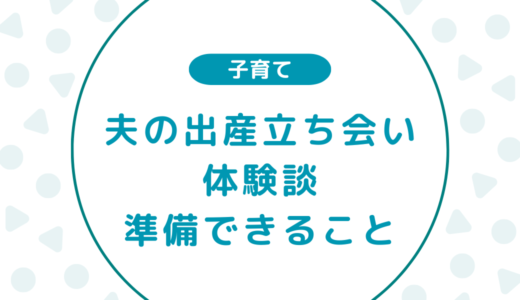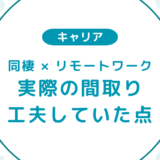この記事では、
- 「これから就活を進めるにあたって、会社選びの際に心構えておいた方が良いことを知りたい」
- 「就活の成功・失敗体験談をたくさん知りたい」
という方に向けて、
- 私の就活・入社後体験談
- 就活時に抱いていた理想と、実際の入社後のギャップが少しでも小さくなるように、今から心構えておくべきこと
について、実体験ベースでお伝えします。

まるで1個上の先輩とサシ飲みに行ったかのように、「有益な情報が得られた」「心が少し軽くなった」「また明日から頑張ろう」、そんな気持ちになっていただけたら嬉しいです。
1. 新卒で入社後、私の身に起こったこと

記事タイトルの通り、私は新卒で入社した数ヶ月後に適応障害になりました。
まずは、実際に私が入社後どのような状態になってしまったのか、事例をお伝えします。
新卒で入社後、最初の1ヶ月は何事もなかったものの、GW明けから急に身体面・精神面で異変が生じ始めました。
- 仕事中、常に不安な気持ちに駆られ、なかなか頭が働かない
- 少しでも気を緩めればいつでも泣ける状態
- というか、出社・リモート問わず、無言で涙を流しながら仕事をしていたことがしょっちゅう。
- 笑顔を作ることができなくなる。ずっと無表情。
- 朝はギリギリまで布団から出られない。
- 休みの日に布団から全く出られなくなった。ずっと布団の中でスマホをダラダラみている状態で、家事も全く出来ず。
- 電車を待つとき、列の一番前に立つことができない。
- 1日に1回は、これまでの人生であった嫌な出来事などがフラッシュバックして「死にたいな」と思っていた
- 度々破壊衝動に襲われそうになる。家の中にあるものを全て投げ散らかしたい、等。
- 当時、新規事業の立ち上げの仕事をさせられていたこともあり、「普段自分が使っているサービスは全て、このようなしんどい仕事から生まれていたのか」と思ってしまい、
日常で何かを使う時(ベッド・机・スマホなど日用品から、水道水・電気等のインフラまで、とにかく生活していて触れるもの全てに対して)、毎回しんどい気持ちになる。
結果、大学時代から同棲を続けていた同居人(現在の夫)に、
- 流石に大学時代の時と比べて、明らかに精神状態が異常になっていると思う
- そんな会社早く辞めて転職してほしい
- 会社員がきついならひとまずアルバイトとかでもいいと思うから
と毎日言われていました。
しかし「転職しなよ」と言われても、仕事そのもの自体が嫌になっていたため、転職活動をするのも億劫で「生きるか死ぬかの2択」というぐらいの気持ちでした。
そこで同居人に「流石に精神科に行こう」と言われ、精神科に行ったところ医者の方に「鬱の一歩手前ですね〜、症状名で言うと適応障害ですね」と診断された次第です。
ちなみに、診断をもらうまでに精神科には2回行っており、1回目(新卒1年目の7月頃)は精神科の長い待ち時間(1時間程度)に耐えることができず「もういいです」と言ってキャンセルして出てきてしまうという有り様でした。
(今思うと、病院で1時間くらい待たされることなんてよくあることで、何もおかしくないことだなと思えるんですけどね。)
数ヶ月後(新卒1年目の11月頃)、再度同居人に「お願いだから精神科に行ってほしい」と懇願され、もう1回精神科にチャレンジしたところ、その時は運良く待ち時間がそこまで長くなく、そのまま診察を受けられたという流れです。
2. 適応障害のその後の経過

前述の通り、当時の状況はひどいものでしたが、今はある程度回復しています。
精神科で診断を受けた後のその後の流れを軽くお伝えします。
適応障害の診断を受けた後、勇気を出して部長に面談で「こういう状況です」ということを伝えた結果、部署・仕事内容を一時的に変えてもらうことができました。
数ヶ月後にはまたすぐに元の部署・上長のもとに戻されましたが、この一件で上長は「どうやらこの指導の仕方は不味かったらしい」と学んでくれたらしく、これ以降対応を少し優しめなものに変えてくれたため、だいぶ過ごしやすくなりました。
そこから数年を経て現在に至りますが、今は前述していたような症状はほとんど治まっている状況です。
休みの日はちゃんと外に出れるようになりましたし、家事もできるようになりました。
ただ未だに「笑顔を作ることができない」「電車が怖い」というのは継続しています。
3. なぜ私は適応障害になってしまったのか、分析してみる

当時から数年の時を経て、気持ちも落ち着いたことですし、「なぜ私は適応障害になってしまったのか」「今後同じことを繰り返さないためにはどうしたらいいのか」を真剣に分析したいと思います。
私が適応障害になってしまった要因として、以下5つが挙げられると考えています。
- 【就活時】
- ①「会社で働く」ということへの期待値が異常に高くなっていた
- ②社会・会社に過剰に適応しようと、「自分はバリバリ働きたいんだ」と思い込もうとしていた
- 【入社後】
- ③会社に対して求めていたことと、実際の社風のずれ
- ④会社に対して求めていなかったことを、これがよくてうちに入ったんだよね?と与えられ続ける
- ⑤そもそも「社会人になる」という環境の変化から来る体への負荷
以下、一つずつ解説をしていきます。
①【就活時】「会社で働く」ということへの期待値が異常に高くなっていた
今の会社から「内定を承諾していただくにあたって、弊社に入社したい理由を改めて文章で提出してください」と言われた際に、私が作成していた文章がPCに残っていたため、恥を偲んで掲載します。
1、就職活動に対する思い
私は就活を、「内定や会社名というブランド品を手に入れるゲーム」ではなく、「仲間・家族探しの旅」のようにとらえています。
大手就活エージェントでは、「9月~12月に第3志望群のベンチャーの内定をとり、1月~3月で第2志望群のベンチャーの内定をとり、4月~6月で第1志望群の大手の内定をとるのが理想的な就活である」と説明がされています。また、世の中には「内定をとりやすいESの書き方・面接の受け答えの仕方」のようなものがありふれています。身近な「〇〇大学(私の出身大学名)」の先輩・同期でも、「入社する気はないけど、とりあえず内定とって『自分のすごさを示す材料』『精神安定の材料』を作るために受ける」という人が多くいました。入社する企業の選び方も、この会社は「大手」だから、親・友人・先輩・エージェント等が「すごい」と言ってる有名な会社だから、という理由で選ぶ就活生を多く見かけます。
しかし、それでよいのでしょうか。私はそもそも「仕事をする」ということを「より多くのお金を得るためのゲーム・自分を誇示するためのゲーム」ではなく「社会をよりよくするための活動」と捉えています。この国・世界を引っ張っていく存在になる可能性を多く持つ「高学歴」の人々の働く理由が、結局のところ、ブランド品を身に付けたいから、という理由に大きくまとまってしまっていることが、日本に世界を引っ張っていくような会社が少ない原因となっているのではないでしょうか。
私は、「社会をよりよくする活動」として仕事をするためには、「仕事をする目的が一緒であるか」という観点以外にも、この会社に「自分の熱い気持ち・本音を語り合いたいと思える仲間がいるか」「目的を一緒に果たしたいと思える仲間がいるか」「なにかしらの困難に直面したとき「会社に頼る」ではなく、自分がこの人たちのことを支えたい、この人たちと一緒に困難に立ち向かいたいと思えるのか」、そのような観点が大切になってくると考えています。一日の中で、家族よりも長い時間一緒にいることになる会社の仲間。だからこそ私は就職活動を、「仲間・家族探し」と捉えています。
私の志は「子供たちが自己肯定感をもって、自分自身の道を歩み、社会に貢献する人財となれるよう、環境を整えること」です。そしてそれが、私がどのように社会をよりよくしたいのか、についての今時点での答えです。
2、「〇〇(会社名)」を選んだ理由
一言でいえば、上記で述べた観点に、「〇〇(会社名)」がぴったりと一致していたからです。
私は「〇〇(会社名)」の理念を初めてインターンで聞いたとき、私の気持ちをそのまま代弁してくれているかのような気持ちになりました。また、懇親会でお話した社員の方からは、内にある教育への熱い思い、そして誠実さが伝わってきました。人事の方の就活生と向き合う姿勢からは、きっと他の仕事でも誠実に人・社会・仕事と向き合っているのだろう、と感じられました。
この人たちとなら、思いを語り合えるし、目的に向かって一緒に嬉しいことも苦しいことも共有して前に進みたいと思うし、この人たちのために身をつくして働きたいとも思えました。社員の探求心の強さについてのお話からも、私はここでなら地(知)に足つけて自分らしく一歩一歩生きていける、と確信を得られました。社会人になることを楽しみに待ち遠しく思える会社です。
私は「〇〇(会社名)」に入社して、「〇〇(会社名)」として国・世界を引っ張っていけるようになるのみならず、「〇〇(会社名)」によって国・世界を引っ張っていけるような人材を増やしたいなと思っています。これからも何卒、よろしくお願いします。
非常に痛い文章すぎます。とても直視できません。
「自分は痛い文章を書いている」という自覚があって、わざとこの文章を書いていたならまだ救いようがあったかもしれませんが、当時の私は、本当に心からこう思い込んで本気でこの文章を書いてしまっていました。
当時の私は、そもそも「就活・会社」への期待が大きすぎたのだと思います。
- 就活で選んだちゃんとした会社であれば、サービスは世のため人のためになっており、日々社会貢献ができて、自分の存在価値を感じられるものだ
- 就活で選んだちゃんとした会社であれば、「数字・売上」に追われることはなく、一人一人のお客さんと誠実に向き合って働くことができる
- 就活で選んだちゃんとした会社であれば、周りの社員とは、親友・家族くらい仲良くなれるものだ
- 就活で選んだちゃんとした会社であれば、毎日文化祭のようにワイワイ盛り上がりながら楽しく仕事ができるものだ
- 就活で選んだちゃんとした会社であれば、全社員みな熱意を持ってイキイキとしながら働いているものだ
実際はそんなことはないはずで、むしろ「うちの会社は全て当てはまっている」と自信満々に言ってくる会社があれば、それは危ないカルトか宗教チックな会社だと思います。
現実は、
- サービスの内容は競合と似たり寄ったりのもので、そこまで独自性があるわけではない。このサービスがなくても社会は回っていくということがほとんど。大きな思想を持って売っていても、実際その思想に基づいて使ってくれているユーザーはそういない
- 会社はボランティアではないため、利益を上げる必要がある。確かに「数字は後からついてくるもの」ではあるが、数字のことを全く考えなくて良いわけではない
- 職場の全ての人と性格が合う、ということは基本ない。どの職場にも、あまり性格が合わない人というのは必ずいるもの
- 仕事の全てが楽しいものであることはない。時には辛いこと苦しいこともある。
といったことであることがほとんどです。
が、当時の私はそれをわかっておらず、就活支援団体・新卒エージェント・新卒採用人事のキラキラ感溢れるトークにまんまと乗せられ、「会社で働く」ということに対して、ものすごい高い期待値を持ってしまっていました。
今の会社に対しても「この就活は、100点満点中200点満点のものだ」くらいの気持ちで入社してしまっており、ゆえに入社した後の落差が一層大きいものになってしまっていたのだと考えています。
これが、のちの「③【入社後】会社に対して求めていたことと、実際の社風のずれ」に繋がります。
②【就活時】社会・会社に過剰に適応しようと、「自分はバリバリ働きたいんだ」と思い込もうとしていた
そもそも私にはキャリア志向がなかったと思っています。
まず前提として、私の就活の流れがどのようなものだったかを改めてご紹介します。
・元々「就活は怖いもの・恐ろしいものだ」と子供の頃から思っていたため(第一志望でもないのに第一志望と嘘をつかなければいけない、圧迫面接がある等のイメージを持っていたため)、「就活はしたくない、将来は公務員とかになりたい」と思っていた
・大学3年生になり、友人から就活支援団体の面談に一緒に行かないかと誘われる
・就活支援団体の面談を受けてみて、「就活って意外と難しくなさそうかも。私にもできるかも」と思い始め、民間の就活に乗り出す
・大学3年の夏のインターンで、1dayのものにいくつか参加。その中で、本選考を9月から開始するという会社がいくつかあったため、それらに応募をする
・大学3年の1月に今の会社から初内定をいただく。他にも選考に進んでいる会社はあったが、ここで就活を完全に終了させる。
自分にキャリア志向がなかったことがわかる要素は以下の通りです。
- そもそも、公務員(静かに穏やかに働くことができそうなイメージ)になりたいと思っていた
- 初内定をもらった瞬間に即就活を終えている
- あれだけ熱意を込めて書いていた内定承諾の文章に「成長」のせの字も入っていない
今振り返って思うと、当時の深層心理は以下のようなものだったなと思います。
- 自分に大手は無理だと端から諦めていた。ベンチャーとか小さい会社なら簡単に入れそうだからそういうところを狙おうと思っていた。
- 「大手に入って年収何千万稼ぎたい」などの野心が特になかった。自分の進路・キャリア・ライフプランにあまり興味を持っていなかった。
- 「就活を早く終わらせている人ほど優秀」というイメージを勝手に持ってしまっていた
- 「早く就活を終わらせて大学生活(教育実習・卒論・サークル等)に集中したい」という気持ちが強かった
このように、私にはキャリア志向がなかったにもかかわらず、
しかし、いち早く内定を得て就活を終わらせるためにも、ベンチャー企業の面接を受ける際は
- 「とにかくたくさん働きたい」
- 「スピード感持って成長したい」
- 「会社が潰れたときに困らないよう、自分で事業など立ち上げられる人材になりたい」
とベンチャー企業が喜びそうなことを積極的に発信し、過剰に適応しようとしてしまっていました。
さらに私は、前述の通り就活・会社への期待値が異常に高く、「就活において嘘はつきたくない」という変に真面目な気持ちを持っていたため、
「自分にはキャリア志向はない」という本音には気づいていないふりをし、本当に心から「自分には成長意欲がある」と思い込みながら就活を続けていってしまいました。
これが、のちの「④【入社後】会社に対して求めていなかったことを、これがよくてうちに入ったんだよね?と与えられ続ける」に繋がります。
③【入社後】会社に対して求めていたことと、実際の社風のずれ
新卒採用の人事と、実際に一緒に働くことになる上司・同僚は全く違います。
入社前に感じていた「会社の雰囲気」と実際に配属された部署の雰囲気が、思っていたものと全く違ったということはよくあることなのではないでしょうか。
例に漏れず、私もその1人でした。
私が会社に求めていたのは、前述の通り「誠実さ」や「信頼・安心できる人間関係」、また「チームで働くこと」でした。
しかし実際のところ入社してみると、配属先の部署では以下のような状況でした。
- 上長の性格がキツめ。
- 話を途中で遮る
- 鼻で笑ってくる
- 他の社員がいる前で永遠にダメ出しを続ける
- 部長の発言に、誠実さを感じられないような発言が多かった。雑談でポロッと出てくるとかではなく、部署の社員全員が参加している正式なミーティングの場で堂々と発言している状態。
- あいつらなんて全員発達障害
- ようやくあいつが会社を辞めてくれた
- ついてこれないようなやつはとっとと辞めればいい
- あいつには採用時にB-の評価つけてたんだよね
- あいつは全然プロモーションのことをわかってない。まだまだ使えないな。
- つわりで仕事を休まれるとか最悪
- 結果、部署内は人の入れ替わりが激しく、大量採用・大量離職のような状態。
上記のような状況では、とても組織に対して「安心感・信頼感」を持つことはできませんでした。
ちなみに、私のことを採用してくださったキラキラ人事の方も、同じく新卒でこの会社に入社していたのですが(配属先は別部署)、入社後に同じように心療内科に通う羽目になっていたそうです。
その方は、私が入社後数ヶ月してご退職されました。
④【入社後】会社に対して求めていなかったことを、これがよくてうちに入ったんだよね?と与えられ続ける
「成長したくてベンチャー企業に入ったんだよね?」「じゃあこの仕事やって」と部長・上長に振られた仕事が、以下のようなものでした。
- 研修期間はなし。入社翌日から実業務開始。
- いきなりパニックゾーンの仕事(新規事業立ち上げ)を振られる
- チームメンバーなしの一人きりでの仕事
- ティーチングなしにいきなりコーチング
- 新規事業を立ち上げるにあたっての、必要最低限の研修(部署内の既存のオペレーションがどう回っているのかの説明等)や教育(新規事業の立ち上げはこういう流れで行うもの等)は一切なし。
上長からは「そこらへんのメールボックスとか見れば自分でキャッチアップできるでしょ」「ググればわかるでしょ」と指示をいただいていました。 - それにより私が、オペレーションの解釈を一部間違えてフローを作成してしまった結果、一般職の方(オペレーションの現場の方)から袋叩きにされる
- お客様から電話で「責任者を出せ」とクレームをいただいた際には、私(新卒入社数ヶ月程度)が「私が最高責任者です」と矢面に立つ。
(※実際に私が新卒1年目〜3年目の間に行った業務内容については、以下記事に別でまとめています。ぜひ併せてご覧ください)
最初のうちは私も「自分は成長をしたくてベンチャー企業に入ったんだから」と思い込んでいたので、必死に食らいつこうとしていましたが、
前述の通り本心ではキャリア志向なんてなかったため、すぐに限界が来てしまい、耐えることができなくなっていきました。
「自分には成長意欲なんてなかった」と認めることの辛さも、ストレスに繋がっていたように思います。
⑤【入社後】そもそも「社会人になる」という環境の変化から来る体への負荷
大学生の頃の私は、以下のような生活を送っていました。
- 大学周辺に住んでおり、自転車で通学
- 特に大学4年生の頃は授業がなかったため、平日・土日の曜日感覚がなかった
- 「自由な時間に起き、ご飯を食べ、卒論等を書き、寝る」というような生活で、時間に縛られる・追われるという感覚が少なかった。休憩時間も自分で自由に設定して取ることができていた。
- 住んでいた場所は自然豊かな環境で、人混みによる混雑などがなかった
恥ずかしながら、かなり怠惰な生活を送っていたと思っています。
一方社会人になってからは、
- 朝決まった時間に早起きし、満員電車に乗って都内に通勤
- 1日8時間以上、ずっと椅子に座って作業し続ける。それを週5日連続で行う。
と環境がガラッと変わりました。
会社は都心に位置していたため、通勤・退勤時は人混みをかき分けながら歩く必要があり、今思うと、人混みが苦手だった私はそれだけでも地味にストレスを受けていたように思います。
またデスクワークのため、社会人になってから一気に体力は減り、これまでの人生で感じたことがなかったような、目の疲れ・肩こり・首こりなどの症状が出るようになりました。
これも、地味にストレスとなっていたように思います。
4. なぜ私は適応障害から回復することができたのか、分析してみる

適応障害から回復することができた理由を探ることで、「適応障害になることを予防するためにはどう心構えておくのが良いか」を考えることに繋げたいと思います。
①支えてくれる人がいた
まず何よりも、同居人(現在の夫)がいたことが大きいと考えています。
私が家事を全くできなくなっていた間、夫は全ての家事(掃除・洗濯・料理等)を1人で引き受けてくれました。
夫がいなければ、私は毎日の生活ができておらず、食事なども取れておらず、本当に生きていなかったのではないかと思っています。
②会社側が素直に育成方針を変えてくれた
部長に面談で自分の適応障害の症状について伝えた後、上長が素直に態度を変えてくれ、きついダメ出しを私にしてくることがほとんどなくなったことも大きいと考えています。
部長・上長ともに、新卒社員を育てるのは初めてのことだったらしく、今回の一件で、「どうやらいきなり新卒に新規事業立ち上げを丸投げするのは無理なことらしい」と学んでくださったようです。
部長の「誠実さのない発言」は未だ続いていますが、だいぶ会社での過ごしやすさは変わりました。
③自分自身にスキルがついた
なんだかんだ自分自身にスキルがついたことで、全てを自責思考で捉えてしまうのではなく、会社の悪いところを明確に心の中で指摘できるようになったことも大きいと思っています。
新卒で入社したての時は「こういうものなのかな」「できない自分が悪いのかな」と全てを受け入れてしまっていましたが、
業務の中でマネジメントの本などを読んでさまざまに勉強した結果、「いや、この会社・あの人のこういう態度は、人を育てるにあたって明らかによくないやり方だ」など論理的に心の中で指摘できるようになり、
全てを自分で背負い込んでしまうということがなくなりました。
④吹っ切れた
「100点満点の会社・職場なんてない」という現実を受け入れることができるようになり、そんな現実の中でも強く生きていこうという気持ちを持つことができるようになった、というのも大きいと思っています。
就活生時代のような「脳内お花畑状態」ではなくなり、会社にそこまで期待しなくなり、冷静に「この会社の良い点・悪い点」を見つめた上で、自分はその中でどう生きるかを考えることができるようになりました。
5. 入社後ギャップを減らすために、新卒が入社前に心構えておいた方が良いと思うこと

最後に、これから社会人になる方に向けて、「入社後ギャップ」を減らすためにあらかじめできることを、私なりにお伝えしたいと思います。
①新卒選考の際に会っていた人と一緒に働くことになる人は全然違う、と心得ておく
新卒採用の人事の方がどれだけ良い人だったとしても、あなたが入社後に人事部門に配属されない限りは、その方と一緒に働くことはありません。
またそもそも、キラキラしているように見える新卒採用の人事の方も、実際のところは自身の採用KPIを達成するために本音を押し殺して無理やり会社をよく見せようとしている、というケースは多いにあり得ます。
また、カジュアル面談なども要注意です。
カジュアル面談などで登場する社員も、基本的に会社が「この人ならキラキラしていて就活生ウケが良いだろう」という人が差し出されるようになっています。
「今の会社に不満を持っています」「私の元にきた部下は全員数ヶ月以内に退職しています」という問題ある人が採用時のカジュアル面談に出てくることはないのです。
また採用サイトなども要注意です。
会社側も、新しく人を採りたくて採用活動をしているわけなので、馬鹿真面目に採用サイトに「この会社に入ってこのように後悔した人がいる」「このように病気になった人がいる」などと書くことはしません。
基本的に採用サイトには、会社の良い点や、ごく一部の社員の声しか掲載されないようになっています。
またそもそも、転職をすることが当たり前になっている時代、「この人と一緒に働きたいと思ったから入社する」というのはかなり危ない考え方だと思っています。その人が数ヶ月後に転職してしまう可能性は多いにあります。
- 新卒採用の選考時に、会社側から言われることや採用サイトに書いてあることを鵜呑みにしない
- 実際に働くことになる人は、採用サイトに乗っているようなキラキラしている人ではない可能性が多いにある。というかむしろその可能性の方が高い
就活の際は、以上を心構えておく必要があると考えています。
②基本どの職場も職場の雰囲気は悪いものだと覚悟した上で、会社選びをする
「じゃあ実際に一緒に働くことになる社員の雰囲気は、就活時にどう見極めればいいのか」「完全に運に任せるしかないのか」と思われる方もいらっしゃるかもしれません。
その点について私としては、「そもそも職場に『人間関係の良さ』を求めない」のが良いのではと考えています。
そもそも「仕事が大好きでたまらない」という社会人は本当にごく一部です。どれだけ綺麗事を言っていても、基本は「日曜の夜が憂鬱」「もう仕事するの疲れた」という人がほとんどです。
会社とは、そういった人たちで構成されている団体です。そんな団体の雰囲気が良いなんてこと、基本的にありません。
またどんな職場でも、「その職場に満足していない人」「この人のせいで何人も人が辞めている」「ちょっとキツイお局」といった人は一定数存在します。
なので基本は、「どの職場に行こうが、職場の雰囲気は悪いものだ」と覚悟しておいた上で、「それでもこの会社のこの点が良さそうだからこの会社にする」という選び方をすることで、少しでも入社後のガッカリ感を軽減することができるのではと考えています。
③心から信頼できる、頼れる人を社外にあらかじめ作っておく
友人、先輩、恋人、家族など関係性はなんでも良いです。
「自分の話を否定せず静かに聞いてくれて、必要に応じて助け舟を出してくれる」、そんな関係性の人が1人いるだけで、心はかなり救われます。
またできることなら、「社会人になって即一人暮らしデビューをする」というのは避けておいた方が良いとも思っています。
実家が都心近くでない限りほぼ一人暮らしにならざるを得ないとは思いますが、その際はシェアハウスなども検討の余地ありだと思っています。
ただでさえ、大学生から社会人への移行にあたって環境の変化が大きい中で、さらに一人暮らしで慣れない家事をしなければいけないという状況は、かなり負荷が大きいと考えられます。
また一人暮らしは、思っているよりも孤独感が募ります。
一人暮らしを始めるのは、社会人生活に慣れてきてからがおすすめです。
5. 最後に
新卒の入社後ギャップを少しでも減らすために心構えておいた方が良いことをまとめると
- ①新卒選考の際に会っていた人と一緒に働くことになる人は全然違う、と心得ておく
- ②基本どの職場も職場の雰囲気は悪いものだと覚悟した上で、会社選びをする
- ③心から信頼できる、頼れる人を社外にあらかじめ作っておく
となります。

新しい物事にチャレンジするのは、誰だって勇気がいることです。
自分の実体験が、少しでも皆さんの心を軽くしたり、背中をそっと押すものになることができたら嬉しいです。
このサイトでは、後輩を応援したいという気持ちで、これからもさまざまな記事を執筆していきますので、ぜひご覧ください。
 わたしたちについて
わたしたちについて
またこのブログでは、他にもキャリア・就活について記事を執筆していますので、ぜひ併せてご覧ください。