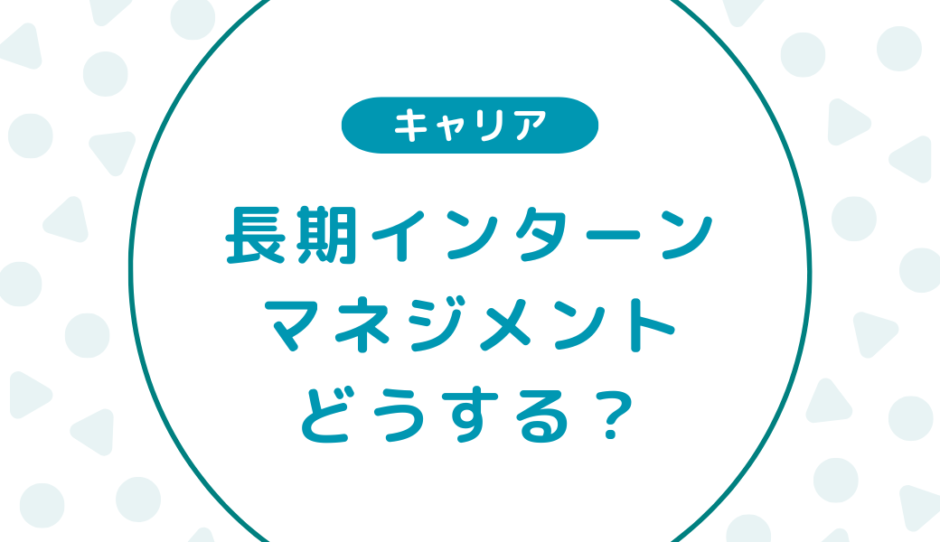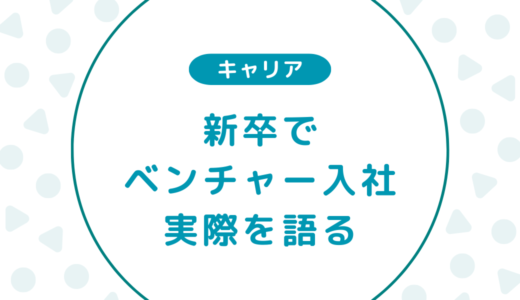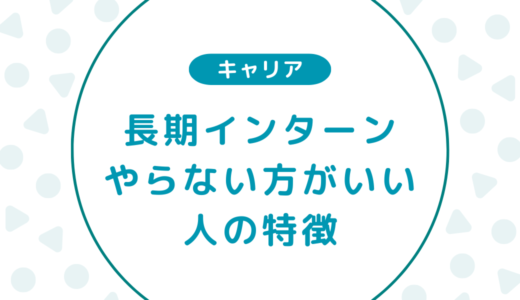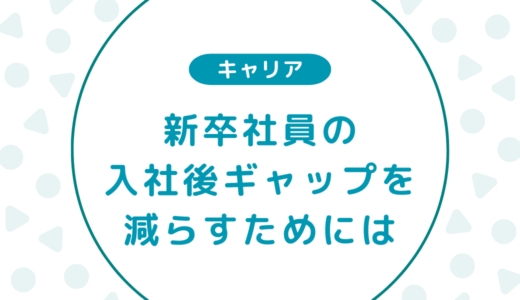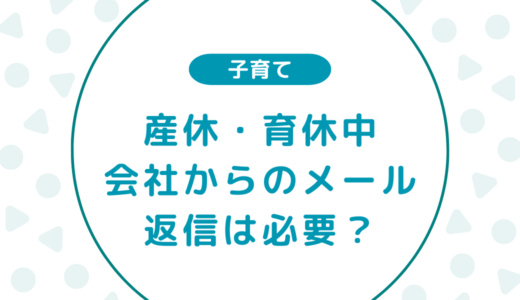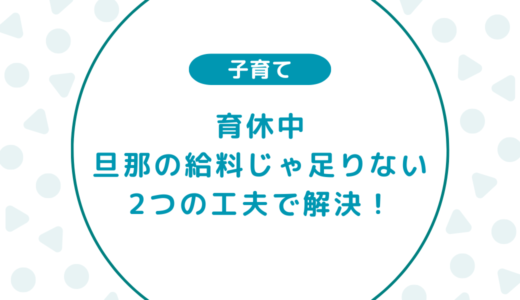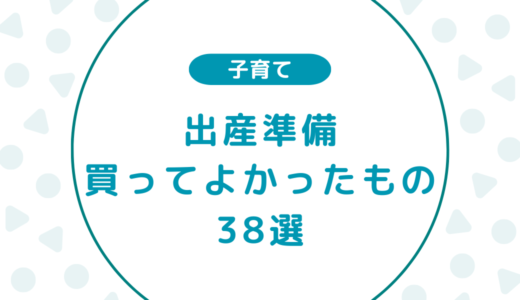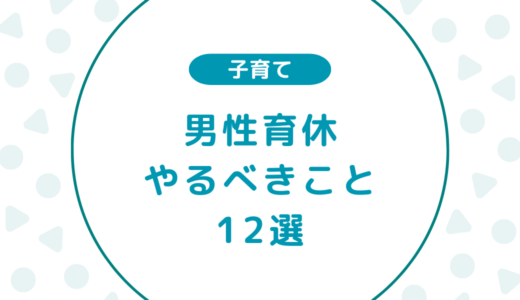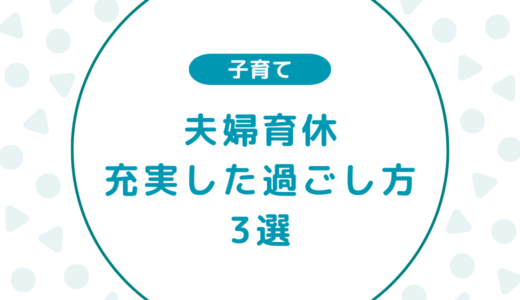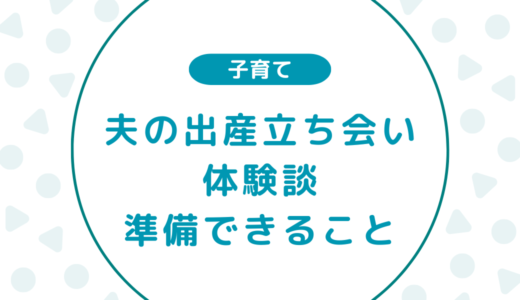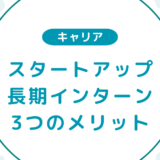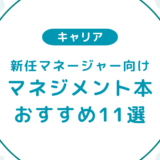この記事では、
- 「長期インターン生のマネジメントを行うことになったが、初めてのマネジメントのためどのように行えば良いのかわからない」
- 「まだ新卒数年目なのに、自分にマネジメントなんて務まるのだろうかと不安」
という方に向けて、
- 長期インターン生をマネジメントする際の具体的な方法
- 新卒社員が長期インターン生をマネジメントすることになった際の適切な心構え
について、自分も同じように不安になったり挫折した経験を踏まえ、実体験ベースでお伝えします。

まるで1個上の先輩とサシ飲みに行ったかのように、「有益な情報が得られた」「心が少し軽くなった」「また明日から頑張ろう」、そんな気持ちになっていただけたら嬉しいです。
1. 前提:私の会社の特徴、私の長期インターン生マネジメント経験

私は「長期インターンをしていた大学生」側ではなく、「長期インターン生をマネジメントしていた担当社員」側の人間になります。
以下、私の勤めている会社、および私の長期インターン生のマネジメント経験の前提についてお伝えします。
私の会社の特徴
私が勤めている会社は、数十年前に社長が「学生起業」で立ち上げた会社になっています。
そのため、現役大学生を巻き込み一緒にビジネスを作り上げていくという「文化」が根付いている会社でした。
最近では「長期インターン」という言葉も一般的なものになってきましたが、
私の会社では、「長期インターン」という言葉がまだ一般的ではなかった頃から、少なくとも10年以上前からは、長期インターン生の受け入れを行っていました。
実際に長期インターン生はどれくらいの戦力になるのか
社員数が少ない会社ということもあり、私の会社では長期インターン生にはかなりの裁量権を持たせ、社員並みに稼働をしてもらっている状況でした。
例えば
- 年間数億売上げているサービスのリスティング広告の運用を全て任せる
- サービスサイトのコンテンツSEOの戦略・戦術作成、実行を全て任せる
- X(旧Twitter)・InstagramなどのSNSマーケティングの戦略・戦術作成、実行を全て任せる
といったことを実際に長期インターン生に任せてきて、それでサービスの売上・会社が成り立っていた状況でした。
社員は「経営戦略」「事業戦略」の作成に集中し、「機能戦略」以降は長期インターン生にほぼ丸投げというイメージです。
【参考】
・第31回 経営戦略の3つのレベルを認識する | 日本能率協会コンサルティング
最近になって長期インターン生の事情が変わってきた
が、そんな私の会社も、今後は長期インターン生の採用を見送る方針で動きつつあります。
理由は以下の通りです。
- 「長期インターン生の質が下がっている」こと。
- 長期インターン生を受け入れていたのは、「学生起業」の流れを汲んだただの「文化」であって、そこに明確なビジネス的なメリットが何もないこと
まず、会社が長期インターン生を採用する理由には、以下のようなものがあると考えられます。
- ①扱っているサービスが大学生向けのものであるため、学生内のコネクションや知恵を借りたい(就活サービス系等)
- ②「学生運営」を打ち出すことで共感や同情を誘うことができそうな商材を扱っている(地方創生系等)
- ③長期インターンから新卒採用に繋げたい
- ④販管費の削減
私の会社が長期インターン生を受け入れていたのは、「学生起業」の流れを汲んだただの「文化」であったため、上記①〜③のどの理由にも当てはまっていない状態でした。
せっかく手間暇かけて学生を育てたとしても、4年経ったら学生は卒業してしまい、会社には何も残らないため、本当に「慈善活動」のような形になっていました。
強いて言うなら「④販管費の削減」のメリットが享受できていたくらいです。
それでもやはり、「手間暇かけて育てた学生が、一人前のビジネスパーソンとして成長し、社会に羽ばたいていく姿を見れる」ということに、一定の「エモさ」を感じられるため、
ここまで「長期インターン生を受け入れる」という「文化」が継続されてきていました。
しかしそれも、最近になって事情が変わってきました。
経営陣・マネジメント社員が口を揃えていっているのが「長期インターン生の質が下がった」ということです。
「ビジネスの現場で実践経験を積みたい」という明確な意志を持って長期インターンに臨んでいる学生が減り
- 周りの友人が長期インターンをし始めたから、自分もなんとなく
- 長期インターンをしている方が就活に有利になると聞いた
といった、ふわふわな理由で長期インターンを始める人が増え、
そういった人は「長期インターンに参加することがゴール」になっているため、もちろん業務で大した成果を出すこともなく、
結果ただチームのお荷物になっているだけ、マネジメントの工数が無駄に増える、という状況が度々見られるようにました。
- 長期インターン生を受け入れることにビジネス的なメリットがなく
- 且つ長期インターン生の質もそこまで高くなく、マネジメントの工数を無駄に増やしているだけ
ともなれば、「長期インターン生の受け入れはもうやめようか」となるのは必然の話です。
私の長期インターン生のマネジメント経験
とは言いつつ、これまで十数年続いていた「長期インターン生と共にビジネスを作り上げていく文化」を、いきなり数日で断ち切れるわけでもないため、
新たな人材の確保方法を検討し、実行に移すまでの数年間の間は、私の会社でも引き続き「長期インターン生」の受け入れを続けていくことになります。
私はちょうどその「過渡期」の時期に、長期インターン生のマネジメントを数年間担当することになりました。
私が担当していた長期インターン生の状況は、以下の通りです。
- 【長期インターン生に任せていた仕事】
・SEOライティング、SEO戦略・戦術の作成
・Webサイトの数値分析
・後輩のマネジメント - 【勤務条件】
・月50時間以上働くことが必須
・卒業まで働くことが必須
・大学1・2年生からの入社が必須。大学3年生以降の入社は受け付けない。
・フルリモート - 【私がマネジメントしていた長期インターン生の在籍大学】
・東大生・京大生・慶應生・東工大生・その他複数大学
私は新卒3年目の頃から長期インターン生のマネジメントを担当するようになったのですが、私が長期インターン生のマネジメントを先輩社員から引き継いだ際には、
- 卒業までの勤務を前提に契約を結んでいたにもかかわらず、途中で退職をする長期インターン生が毎年2〜3割程度いる
- 月平均50時間以上安定して勤務できているのは、全体の1〜2割程度
- 戦略・戦術に則って実行するという体制が破綻しており、各々が好きなブログ記事を好きなタイミングで誰の最終確認を経ることもなくリリースしており、その数値成果の分析も全くされていない状況
という、一言で言うと壊滅的な状況でした。
長期インターン生のマネジメント方法は各担当者に完全に一任されていたため、
私はそこから、後述するマネジメント手法を用いて、以下成果を出しました。
- 長期インターン生に、当初の契約通りに働ききってもらう(卒業までの在籍率100%、月平均50時間の勤務の達成)
- 戦略・戦術を作成し、そのスケジュール通りに実行していく体制を整える
- サービスサイトのCVRを改善。CV数を前年比140%増加させた
「長期インターン生に契約通りの稼働をしてもらう」「戦略・戦術に基づいた実行体制」などというのは、かなり当たり前すぎる話なのですが、
それでも、荒地から更生させた私なりの経験をもとに、長期インターン生のマネジメントについて少しは語れることがあるように思っています。
(※私が新卒で入社してから携わった業務内容の詳細については、以下記事に別でまとめているため、ぜひ併せてご覧ください)
以上の前提をもとに、以降では私のマネジメントの実体験をもとに「長期インターン生はこういうふうにマネジメントすると良い」という考えについて、述べていきたいと思います。
2. 長期インターン生のマネジメントは「難しい」ものだと心得よう

まず前提として、長期インターン生のマネジメントは一筋縄でいくものではなく、片手間でやろうとすると思ったよりも工数がかかり苦労することになります。
まずは長期インターン生をマネジメントすることの何が難しいことなのか、その特性を理解するようにしましょう。
長期インターン生のマネジメントは、社員のマネジメントよりも難しいと言われている
私の会社で共通認識になっていたのは、「長期インターン生のマネジメントは、社員のマネジメントよりも難しい」ということです。
理由は大きく三つあると考えています。
- ビジネスマナー・スキルが身についていない学生を「0」から「即戦力」に育てる大変さ
- 長期インターン生には「逃げ道」が豊富にある
- 必ず「卒業」していくため、優秀な長期インターン生が抜けるとそれまでの文化が一気に途絶えることがある
以下、それぞれ解説いたします。
ビジネスマナー・スキルが身についていない学生を「0」から「即戦力」に育てる大変さ
大学1年生の春から長期インターンを始めるような学生だと特に、この前まで高校3年生だったわけですから、
- アルバイトすらしたことがないため、敬語含め基本的なビジネスマナーが全くついていない
- サークル等で役職について、先輩に揉まれた経験があるわけでもない
- もちろん就活も経ていないので、ビジネスパーソンと関わる経験や、面接で相手の目線に立って自分の意見を順序立てて述べる経験、グルディス等でファシリをしてチームを即興でまとめ上げる経験を積んでいるわけでもない
という状態になります。そういった学生を
- 1年、どれだけ遅くても2年程度で、「一人前の社会人」に育て上げ、会社の売上に貢献してもらう。イメージとしては、新卒2〜3年目レベルと同等の働きぶり・自走をしてもらう。
必要があります。
「ここから教える必要があるのか」という基本のキからスタートすることになりながら、新卒社員を育てる時以上のスピード感で成長をさせ、自走できるところまで育成しなければいけないわけです。
またそうすると当然、長期インターン生側もその過酷さに悲鳴をあげたりします。
長期インターン生のメンタル・キャパシティと、会社が求めるレベルのバランスをうまくとりながらマネジメントする必要があるのです。
長期インターン生には「逃げ道」が豊富にある
且つ長期インターン生はあくまで「大学生」であるため
- 学業に集中したい
- サークルの代表になったからそちらに集中したい
- 留学をしたいと思うようになった
- 将来は教員になると決意したため、民間企業で長期インターンをするのではなく、教育に関するコミュニティに身をおくようにしたい
- 何も大学生のうちから生き急いでここまでビジネスにガッツリ浸かる必要もないかもと思うようになった
など、こちらが何も言えなくなるような、さまざまな「長期インターンを辞めるにふさわしい、正当化できる理由」を持っています。
また長期インターンを辞めるまではなくても、
- 私は長期インターン以外にもこんなにやらなければいけないことがあって忙しいんです。だから長期インターンで成果が出せなくてもしょうがないですよね
という、成果を出せないことを正当化させようとする、逃げのスタンスの学生も一定数出てきます。
必ず「卒業」していくため、優秀な長期インターン生が抜けるとそれまでの文化が一気に途絶えることがある
長期インターン生がうまく卒業までやる気高くしっかり働いてくれたとしても、
次に問題になるのが「優秀な長期インターン生が卒業した際に、それまでの文化が一気に途絶えてしまうことがある」というものです。
どれだけうまく長期インターン生をマネジメントしても、チーム内の全員が120%のパフォーマンスを発揮して働けている、という状況になるのは稀で
「2:6:2」の法則にあるように、優秀な長期インターン生数名がチームをバリバリに引っ張っていき、他のメンバーはそれに感化されてついていく、というバランスの形でうまく成果を出しているというケースが非常に多いです。
実際私の会社でも、「社員と同等レベルで成果を出せる逸材の長期インターン生というのは、1〜2年に1人現れる程度だよね」という認識でした。
なのでチームを牽引するような、要となるようなインターン生が卒業してしまうと、途端に稼働力を失ってしまう、ということがよく発生します。
またさらにひどいパターンが、「それまでの長期インターン生のリーダーが優秀だったあまり、メンバーのマネジメントを全てそのリーダーに移管してしまっており、社員は中身を細かく把握しておらず、結果リーダーが抜けた瞬間にマネジメント体制が崩壊する」というものです。
私が受け持つことになったチームは、まさにこれが原因で破滅していた状況でした。
3. 実際に私が長期インターン生をマネジメントする際に行っていたこと

ではどのようにして、長期インターン生をスピーディーに「0」から「即戦力」に育成すれば良いのでしょうか。
以下では、実際に私が長期インターン生をマネジメントする際に行っていたこと、意識していたことについてご紹介します。
①ジョブディスクリプションの作成
よく採用周りの場面で言われるのが、「ビジョナリー・カンパニー2」の「誰をバスに乗せるか」というものです。
その言葉の通り、組織づくりにおいては、まず何よりも「誰を採用するか」という「採用」の部分が非常に大事になってきます。
そこで私は、
- まず募集をかける前に「今のチームにはどんな人を採用すべきなのか」ということを徹底的に言語化し整理すること
- および面接時に徹底的に人を見極め選別するようにすること
を意識するようにしていました。
具体的にはまず募集をかける際に、
- どんな業務を、どんなスピード感・ステップで任せていくことを予定しているのか
- 学生にとっては、この長期インターンに参加することで、どんなスキル・経験を得られるというメリットがあるのか。
社員が長期インターン生に約束すること。 - どんな心構えの人に入社してもらいたいと思っているか
といったことを徹底的に言語化し、ジョブディスクリプションを作成するようにしていました。
長期インターン生への約束というのは、具体的に私の場合だと
- この長期インターンに参加した学生には、責任持って以下2点を約束する
- どこに出ても恥ずかしくない、一人前の社会人としてのビジネスマナー・スキルを身につけさせること
- 一人前のWebマーケターに育てること
といったことを長期インターン生に約束するようにしていました。
また募集要項の時点で、
- 決して楽なものではないこと
- 「なんとなく就活に役立たせたい」というレベルの意志ではおそらくついていけないであろうこと。
「自分の人生・キャリアをこういうふうに進めていきたいため、長期インターンという場でこういうスキル・経験を得たい」という明確な目的を持っている人を採用したいこと
を明確に打ち出し、できる限り、真にやる気のある学生のみが応募してこれるようにしていました。
またジョブディスクリプションを作成する際は、「これまでの過去の長期インターン生の中で、どんな人は成果を出していてどんな人は成果を出すことができていなかったのか」をあらかじめ整理するようにし、
それをもとに採用要件を組立るようにしていました。
(※私が過去に担当した長期インターン生で、成果を出すことができていた人、成果を出せていなかった人の特徴については、以下記事で別にまとめているため、ぜひ併せてご覧ください)
②面接
有名大学に在籍している地頭の良い学生であれば、面接の受け答えの準備をきちんとしてきていることが多く、
ある程度の王道質問に対しては、スラスラと回答が返ってくることがほとんどです。
そこで私は面接の際
- 「志望理由を教えてください」といった明らかな王道質問に対してすら、受け答えがスラスラできていない人は、よほどのことがない限りその時点で落とす
- これまで自分が頑張ってきたエピソードを一つ述べさせ、「なぜそのように考えたのか、そのような行動をとったのか」の深掘りを3〜5回ほど深掘りし、思考の一貫性、その人の本来の性格がどのようなものなのかを確認する
ということを意識して面接を行っていました。
また大抵の学生だと、これまでに頑張ってきたこととして「大学受験」のエピソードを挙げてくることがほとんどのため、「大学受験」以外のエピソード、例えば中高時代の部活動の経験などについてあえて聞くようにしていました。
③入社後のフォローアップ(社員から)
入社後に「なんだ、長期インターンなんてこんなものか」と思われてしまうと、その後にその子のやる気を軌道に乗せ直すのには、なかなか時間がかかってしまいます。
「入社時がやる気のピーク」となってしまわないよう、入社後の数ヶ月間は特に手厚く様子を見て、その長期インターン生がうまく軌道に乗れるようフォローをしていました。
具体的には
- 「チームで達成したいKPIはこれで、あなたに任せたいKDIはこれ」というのを繰り返し伝える
- 「まずはこの時期までにこれができるようになっていよう。それができたら今度はこういうこともどんどん任せていきたいな」と、求める成長の過程・スピードを繰り返し伝える
- 「一社会人として働く際に求められる姿勢・マインドというのはこのようなものだよ」というのを適宜フィードバックしていき、姿勢をシャキッとさせる
などを行っていました。
「ワクワクできる未来を常に見据えさせる」というのが特に意識していたポイントです。
④入社後のフォローアップ(学生の先輩から)
学生は、社員が言うことよりも先輩が言うことの方を頼りにしたり、社員の背中よりも先輩の背中を追ったりする傾向があります。
社員からのフィードバックよりも、「まだ大学生なのにテキパキ仕事ができる憧れの先輩」からのフィードバックの方が納得してすんなり受け入れられる、というのはよくある話です。
また「立場が人を作る」というのは本当にその通りで、
それまで鳴りを潜めていた長期インターン生が「自分は先輩になったんだ」「自分がチームを引っ張っていかなければいけないんだ」と意識した瞬間、途端に化けるように活躍し出すということもよくあります。
そこで私は、「先輩・後輩の関わり」をうまく活用するというのを意識していました。
具体的には、新人1人に対してメンターという形で先輩を1人つけ、細かい業務のやり方・チームのルールなどは、基本的に社員からではなく先輩のメンターから教えさせるようにしていました。
⑤適宜、業務へのフィードバック
長期インターン生には、Web記事の作成など、担当のタスクが終わった際に、必ず社員にチャットでフィードバック依頼を出してもらうようにしていました。
長期インターン生からフィードバック依頼が来た際は、「成果物に妥協はしない」という姿勢を貫き、徹底的なフィードバックを行うことを意識していました。
数千文字に渡るフィードバックが何往復も行われるということが、ザラにあったような状態です。
ここで社員が「まあこれくらいでいっか」と妥協してしまったら、長期インターン生がそれを上回るクオリティを目指すことは基本的になくなると思っているため、
常に社員として、長期インターン生の一歩先の目線に立ち、長期インターン生を上回る熱量を持ち、その姿勢を示していく、ということを意識していました。
⑥フェーズに合わせて研修を実施
基本的に新しい仕事を振る際は、丸投げ・放置で振るのではなく、その仕事のやり方・全体像についてまずは一通りこちらからレクチャーを行う場を設けるようにしていました。
例えば「Web記事を一人前に書き上げることができるようになってきたから、次はサイトの数値分析ができるようになろうか」となったら、
「数値分析について自分で調べてね」と放置するのではなく、数値分析の基本的なやり方に関する研修の場を必ず設定するようにしています。
過去に一回行った研修があれば、その動画を録画しておき、新しいメンバーにはその録画をみて学んでもらうようにしていました。
⑦毎週のミーティングでチーム全体の成果・各メンバーの進捗確認
毎週の長期インターン生とのチームミーティングでは、以下のことを行っていました。
- ①チーム全体の成果確認
- サイトの数値状況(CV数・SS数等)確認
- 問い合わせ内容(CVの中身)確認
- ②業界の最新情報の共有
- ③戦術実行状況(各メンバーのタスク進捗状況)確認
特に意識していたのが「①チームの成果確認」にて、
- 「このチームが達成しなければいけない数値・KPIはなんなのか」
- 「そのために何を行うべきなのか」
を毎週繰り返し確認し、メンバーに問いかけ、チームの方向性を揃えられるようにしていたことです。
具体的に「①チームの成果確認」では、以下のように今月の目標と現時点での達成率を確認していました。
- まず社員が、Webサイト全体の数値状況、サービスの問い合わせ状況を共有
- その後、各長期インターン生に各セグメントごとに数値分析結果(CV好不調の原因の仮説、および改善のためのアクション案)を報告してもらう。
(メンバーにはあらかじめ、担当セグメントを割り振っておく)
社員はその報告を聞き、フィードバックを返す
また「③戦術実行状況(各メンバーのタスク進捗状況)確認」では、各メンバーにその週の進捗を以下のように報告してもらっていました。
- 今受け持っている業務の目的・ゴール・内容
- 今週の進捗
- このミーティングの場で議論・相談したい点
- ネクスト
この「③戦術実行状況(各メンバーのタスク進捗状況)確認」では特に、社員からではなく、リーダー・先輩からフィードバックをしてもらうことを心がけていました。
細かい業務内容レベルについてのフィードバック・アドバイスであれば、長期インターン生同士でも十分アドバイスし合い、解決できることが多いからです。
またここで「先輩・後輩」の絡みを作ることで、
- 新人:「自分も先輩のようになりたい」という「先輩への憧れ感」を持たせる
- 先輩:「自分が先輩としてチームを引っ張っていかなきゃいけないんだ」という「自分の立場の自覚」「責任感」を持たせる
を同時に行うことを意識していました。
⑧隔週の1on1で毎月の目標設定・振り返り
長期インターン生とは隔週で1on1を実施し、以下を行っていました。
- 月初の1on1:前月の目標の振り返り、今月の目標の設定
- 月の中旬の1on1:今月の目標の進捗状況
特にここで意識していたのが、「常にストレッチゾーンで目標設定をさせる」ことです。
基本的に、成長に関する環境は3つに分類されると言われています。
- 【コンフォートゾーン】
苦労や努力なしに簡単に達成できる水準のこと。そのため、成長は見込めない。 - 【ストレッチゾーン】
今の状態では背伸びしてやっと届くか届かないかの水準、つまり簡単には達成できない水準のこと。
背伸びして挑戦することになるので、目標に対して不安やストレスを感じる。そのため快適で居心地がいいというわけにはいかない。
しかし成長にはつながる。 - 【パニックゾーン】
不安やストレスを過度に感じるほどの水準。
パニックになってしまうほどに高い水準では、目標に向かった挑戦ができなくなってしまうので、成長は望めなくなる。
【参考】
・ストレッチゾーン?パニックゾーン? | 『日本の人事部』プロフェッショナルコラム
大抵の長期インターン生であれば、長期インターンを始めて数ヶ月・数年経ってくると、どこかでダレ始めてきて、自然とコンフォートゾーンに身を置くようになるものです。
そこで毎月の目標設定の場で、「長期インターンの経験を通して、どんな自分になりたいのか」を再確認させ、
常にその人の「ストレッチゾーン」に値する目標を設定させることを心がけていました。
⑨半年ごとの評価面談
私の会社では、半年に一度長期インターン生の評価・昇給を行うという決まりがありました。
そこで私が評価面談の際に意識をしていたのは、つけた評価を厳密に細かく伝えることではなく
- 長期インターンの経験を通して、どんな自分になりたいのか。長期インターン生として働く目的は。
- この半年で、自分はどんな点が成長できたと思うか。当初の目的・理想の通りに働くことができていたか。
- 次の評価面談までに、どんな自分になっていたか
- 卒業時点では、どんな自分になっていたいか
といった「未来の自分」「なりたい姿」を一緒に考えることに重きをおくということです。
ここでもとにかく「ワクワクできる未来を一緒に見据える」ということを意識しました。
また私が評価面談において特に意識しているのは「人事評価で最高のチームをつくる方法」という本に書かれていた、
「信頼関係が構築できていない上司から評価面談の場で何を言われようが、聞く気にならない」というものです。
評価面談をその単発の場だけで考えず、その前後含めて長期インターン生をフォローする、という姿勢で取り組むようにしていました。
⑩リーダーの育成
前述の通り学生は、社員が言うことよりも先輩が言うことの方を頼りにしたり、社員の背中よりも先輩の背中を追ったりする傾向があります。
また自分の「分身」となるような「リーダー」を育てられると、自分は「事業戦略作成」といった一つ上の業務に集中することができるようになります。
そのため最終的には、ここまでの①〜⑨の業務について、社員はあまり手を出さず、長期インターン生内で完結できるようにするというのが理想型になります。
実際にリーダーを育てるために私が毎年行っていたこととしては
- 誰を数年後の「チームリーダー」にするかを早いうちから検討し始める
具体的には、新しい長期インターン生のメンバーが入ってきた時点で、「この子は将来のリーダー候補になりそうか」を検討するようにする - 将来のリーダー候補となる子に対して、早いうちから少しずつ「リーダーシップをとる経験」を積ませる。
- リーダー候補の子と1on1をする際には、「このチームが達成しなければいけない目標は何か」「今のチームに足りていない点はどんなところだと思うか」などについて適宜ディスカッションする場を設けるようにし、視座を少しずつ上げさせていく
- 代替わりの際には、旧リーダーから新リーダーに対して「自分はどんな価値観でこのチームをマネジメントしてきたか」「どんな心構えでマネジメントするべきか」について、何回もかけて「引き継ぎ」をさせる。
またその引き継ぎには必ず社員も参加する
となります。
特に、前述の通り長期インターン生は必ず「卒業」していくため、「優秀な長期インターン生が卒業した瞬間チームの稼働力が落ちる」ということがないよう、
「引き継ぎ」を「これでもか」というほど時間をかけて行わせる、というのは意識して行っていました。
4. 新卒社員が長期インターン生をマネジメントする際の心構え

長期インターン生をマネジメントすることになる社員は、往々にして新卒数年目くらいの社員であることが多いのではないでしょうか。
新卒数年目だと「自分を成長させることで精一杯で、且つマネジメントについての知識も一切ないのに、どうやってマネジメントをすればいいのか」と途方に暮れてしまうことも多いと思います。
そこで以下では、実際に私が新卒3年目で長期インターン生を担当することになった際に、どのような心構えでマネジメントをしていたか、についてご紹介します。
前述の通り「長期インターン生のマネジメントは、社員のマネジメントよりも難しい」にもかかわらず、
実際はそれをわかっておらず「会社に新しく入ってきた新入社員を育成・マネジメントするのであればともかく、大学生の長期インターン生くらいであれば、そこらへんの新人社員にでもマネジメントを任せておけばいっか」と考えている会社は、結構多いと思っています。
そこでここからは、「新卒数年目の社員=ビジネスパーソンとしてもまだ未熟、且つマネジメント初心者」が長期インターン生をマネジメントすることになってしまった際には、どのような心構えで取り組むのが良いのかについて、個人的に思うことを述べたいと思います。
「馴れ合い」はNG
まず「新卒数年目の社員=ビジネスパーソンとしてもまだ未熟、且つマネジメント初心者」がやりがちなのが、
「自分もわからないので一緒に頑張りましょう」「むしろ皆さんから教わりたいくらいです」といった、馴れ合いをするような接し方ではないでしょうか。
個人的には、このやり方はあまりよろしくないと考えています。
最近は「長期インターン」という言葉も少しずつ世に知れ渡ってきていますが、それでも実際に長期インターンをしている学生は全体の数%と、まだまだ少数派です。
「長期インターンでビジネススキルを得たい」というくらい意欲の高い学生なわけですから、前述のような「馴れ合い」の姿勢で臨んでしまうと
- 「この組織・社員から、本当に自分は学びを得られるのか」
- 「こんなナヨナヨしたぬるい組織にいて、自分の求めていた成長は本当にできるのか」
と長期インターン生を不安・ガッカリさせてしまい、
最終的には長期インターン生もその「馴れ合い」「ぬるさ」に慣れて甘んじるようになり、本来持っていたポテンシャルを100%出し切るということもできなくなり
組織としても停滞していく、というのがオチだと考えています。
個人的には「リーダーの仮面」という本に書かれている考え方の一つ、「部下とは迷わず距離を置く」というのを非常に参考にしています。
あくまで「上司と部下」という関係性であるということを意識し、適切な距離感で関係性を構築するのが良いのではと考えています。
圧倒的な「学びの量」で尊敬の念を抱かせる
しかし、自分自身がまだビジネスパーソンとして未熟であり、人に指導できるほどその分野・スキルに特化しているわけでもないというのは事実なわけです。
そうであるなら、どうやって長期インターン生に示しをつければ良いのでしょうか。
考えた末に実際私が行ったことは、「圧倒的な学びの量で尊敬の念を獲得しにいく」ということです。具体的には
- 毎朝、業務に関する記事(私の場合はWebマーケティングに関する記事)を1本読み、長期インターン生も見れるチャットに、「記事の要約」「記事から得られる学び」「施策に活かすためのアイデア」を投稿する
- 毎週、業務に関する書籍を1冊読み、毎週の長期インターン生とのミーティングで、「書籍の要約」「書籍から得られた学び」「施策に活かすためのアイデア」をスライドにまとめて5分〜10分程度で共有
といったことを行っていました。
単純に自分の成長にも繋がりますし、実際に努力している姿・背中を生で見せることで、
「この人についていきたい」「この人になら安心してついていける」という感覚を得てもらえるようになったと感じています。
また、人に指導できるほどその分野・スキルにはまだ特化できていないとしても、
- 基本的なビジネスマナー(基本的な言葉遣い、連絡には即レス等)
- 社会人としてあるべき姿。どのようなマインドで働くべきか
などについては、パッと示すことができるはずです。
実際私は、そういったマインド・姿勢面のところで、長期インターン生に気付きや学びを提供するということを積極的に行っていき、上司・部下としての適切な関係性を構築するようにしていました。
マネジメントについて勉強する時間を必ず確保する
また、長期インターン生でもアルバイトでも後輩でも部下でも、誰かしらをマネジメントすることになったのであれば、必ずマネジメントに関する勉強は行うようにしましょう。
私の経験上、長期インターン生のマネジメントを任された新人社員は、大抵以下のような状況になりがちです。
- ただでさえ、自分が会社についていくための必要最低限の知識(ビジネスマナー、会社・部署特有のルール・やり方、営業・マーケティングなどの自分の職種に関する普遍的な知識)を身につけるのに精一杯なのに、加えて「マネジメント」について勉強をしている暇なんてまずない。
- 長期インターン生については、自分の仕事の片手間に、これまでの部活・サークル・アルバイトなどの経験をもとに、それっぽいやり方で指導をしておくだけになる
- マネジメントをステータスか何かと捉えてしまい、人として偉くなったと勘違いして天狗になってしまう
- マネジメントについて対して勉強しないままなんとなくで乗り切ってしまった結果「成功体験の誤学習」をしてしまう
その結果、長期インターン生に対して誤ったマネジメントをしてしまい、長期インターン生を潰してしまったり、
運よく長期インターン生が潰れなかったとしても、「成功体験の誤学習」をしてしまうことで、今度はその数年後に、新卒で入ってきた部下を潰すことになってしまったり、ということが発生してしまいます。
また当たり前ですが、チーム内の人材を適切にマネジメントできないと、出せる成果も出すことができません。
実際私の会社は、上記のような社員が非常に多くいる状態でした。
「毎日5分だけ」などでもいいため、必ず日々の学び・業務と並行して、マネジメントに関する勉強を少しずつ、無理やりにでも行うようにしましょう。
5. 長期インターン生に対してやってはいけないマネジメント方法

個人的には、長期インターン生が「成果を出せない」状況になってしまうパターンには、「長期インターン生側に問題がある場合」だけでなく、往々にして「マネジメント社員側が悪い場合」もあると考えています。
前述の「マネジメントについて勉強する時間を必ず確保する」でも少し触れましたが、
マネジメント初心者がいきなり「長期インターン生を育成する」という難易度の高いことをしようとすると
「長期インターン生に対して誤ったマネジメントをしてしまい、結果長期インターン生を潰してしまった」といったことが、度々起こります。
私が声を大にして言いたいのが、「親や学校・地域が十数年かけて大切に育ててきた人間を、職場のパワハラで潰すな」ということです。
少しでも、誤ったマネジメントが長期インターン生に対して行われることがなくなるよう、
以下では、最低限私が伝えたい「こんなマネジメント方法はやめよう」というものを述べていきたいと思います。
いきなりパニックゾーンの仕事を振る
前述の通り、成長に関する環境は3つに分類されると言われています。
- 【コンフォートゾーン】
苦労や努力なしに簡単に達成できる水準のこと。そのため、成長は見込めない。 - 【ストレッチゾーン】
今の状態では背伸びしてやっと届くか届かないかの水準、つまり簡単には達成できない水準のこと。
背伸びして挑戦することになるので、目標に対して不安やストレスを感じる。そのため快適で居心地がいいというわけにはいかない。
しかし成長にはつながる。 - 【パニックゾーン】
不安やストレスを過度に感じるほどの水準。
パニックになってしまうほどに高い水準では、目標に向かった挑戦ができなくなってしまうので、成長は望めなくなる。
例えば
- 1ヶ月後までに新規事業を立ち上げて、◯億の売上を立てて。当然、事業計画を作成して社長にプレゼンして、予算承認を受けてからやるようにしてね。やり方はググったりして自分で調べて。
- 飛び込みで100社営業して、1週間後までに受注を◯社とってきて。営業資料は自分で1から作って。
など「明らかに知識・技能のない新人(しかも大学生)には無理だろ」という内容の業務を、「これが我が社の洗礼・登竜門だから」などと得意げに振る、というのは行わないようにしましょう。
普通、そんな仕事の振られた方をしたら、誰でもパニックに陥ります。
「そんな上司・社員、本当に存在するの?」と思うかもしれません。
が実際本当に、どこかの企業のドラマチックな創業ストーリーに感化でもされてしまっているのか、こういう無茶なことを新人にさせるのが「成長」のためになるとか信じてしまっている人がいるんですよね。
ちなみに私の職場の上司は、上記のパターンでした。実際私も新卒1年目で上記のような目に遭い、適応障害になりました。
(※私が適応障害になった経験については、以下記事で別にまとめているため、ぜひ併せてご覧ください。)
ティーチングなしにいきなりコーチングをし始める
「ティーチング」と「コーチング」の違いは、以下の通りになります。
- 【ティーチング】
ティーチングは、教える側が持つ明確な答えを、受け手に対して教えることや与えることで、相手の成長を促進する。 - 【コーチング】
コーチングは、指導を受ける側にすでに答えがあるという考え方。
コーチは、受け手が自分の中にある答えを導きだせるように、対話や問いかけによってサポートする。
【参考】
・コーチングとティーチングの違いとは?それぞれの有効なケースや使い分け方を解説
基本はまず「ティーチング」で必要な情報を伝達し、仕事にある程度慣れてきたら、自分の仕事の仕方などについて「振り返らせる」という「コーチング」の手法を用い始める、というのが一般的なやり方です。
業務経験がまったくない新人に対して、「君はどうすればいいと思う?」などとコーチングの手法を用いて問いかけても、本人の中に蓄積されている業務経験がない状態では、問いに答えようがありません。
フィードバック入門 耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す技術 (PHPビジネス新書)
- 業務上必要なツールの使い方に関する質問にさえ、「どうやって使うと思います?まず考えてみてください(笑)」と考えさせようとする
- 提出した資料について「これ自分では何点満点のつもりですか(笑)」「この資料のどこが悪いと思うかまず考えてみてください(笑)」と考えさせようとする
など某会社の有名セリフ「お前はどうしたい」に感化されているのかわかりませんが、
何を聞かれてもティーチングは一切行わない、ということはしないようにしましょう。
そんな状況が毎日続いたら、誰でも精神を病むのが普通です。
再度になりますが、実際私も新卒1年目の際、上記のような目に遭い、適応障害になりました。
6. 最後に
私が、長期インターン生のマネジメントのために行っていたことをまとめると
となります。

新しい物事にチャレンジするのは、誰だって勇気がいることです。
自分の実体験が、少しでも皆さんの心を軽くしたり、背中をそっと押すものになることができたら嬉しいです。
このサイトでは、後輩を応援したいという気持ちで、これからもさまざまな記事を執筆していきますので、ぜひご覧ください。
 わたしたちについて
わたしたちについて
またこのブログでは、他にもキャリア・長期インターンについて記事を執筆していますので、ぜひ併せてご覧ください。