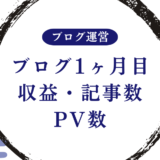この記事では、
- 「新卒でベンチャー企業って実際どうなの?」
- 「新卒でベンチャー企業に就職しようか迷っている」
という方に向けて、
- 新卒でベンチャー企業に入社を決めた理由
- 新卒でベンチャー企業に入社をして良かったと思うこと
- 新卒でベンチャー企業に入社をして後悔していること
- ベンチャー企業の探し方
について、自分も同じように不安になったり挫折した経験を踏まえ、実体験ベースでお伝えします。
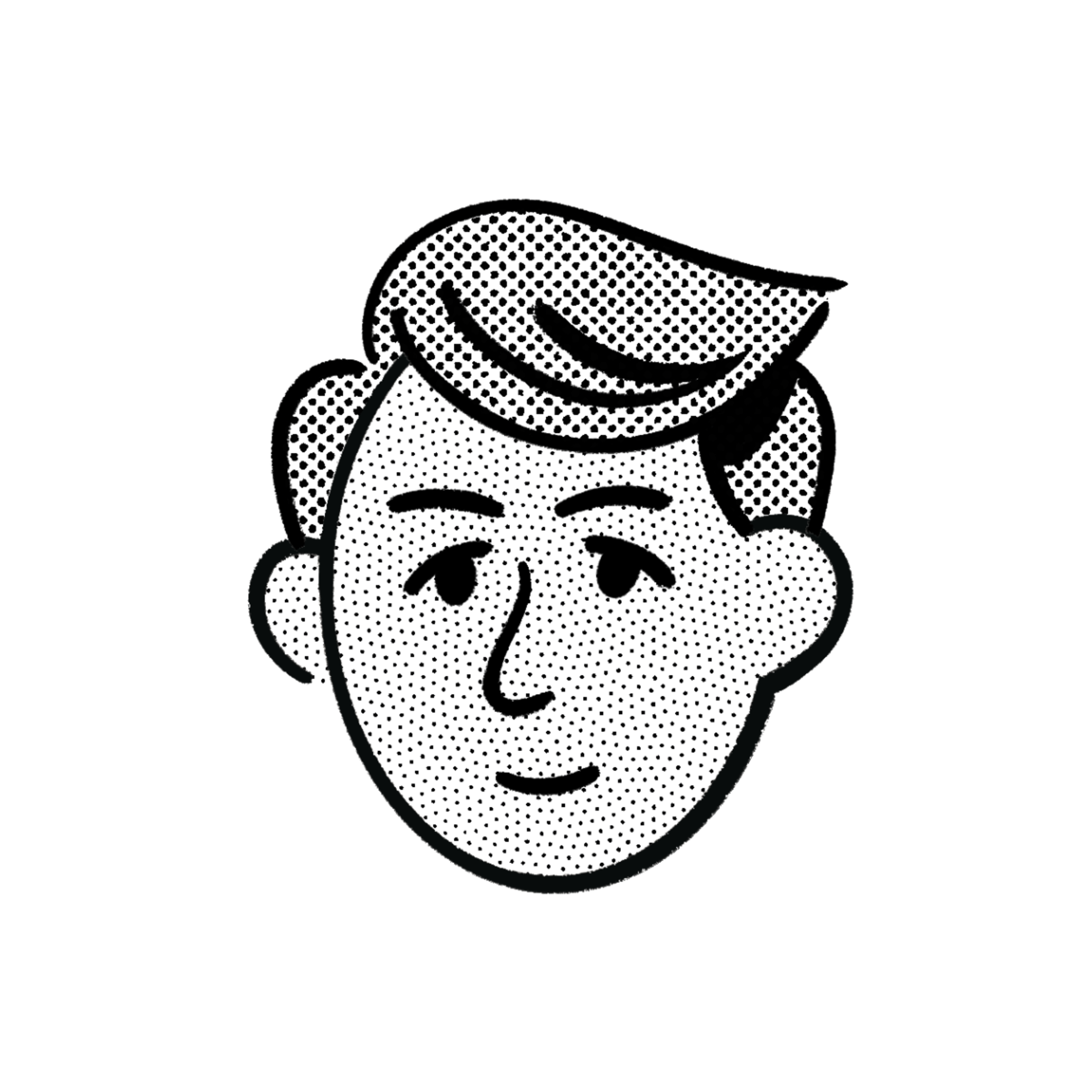
まるで1個上の先輩とサシ飲みに行ったかのように、「有益な情報が得られた」「心が少し軽くなった」「また明日から頑張ろう」、そんな気持ちになっていただけたら嬉しいです。
1. 新卒でベンチャー企業に入社を決めた3つの理由
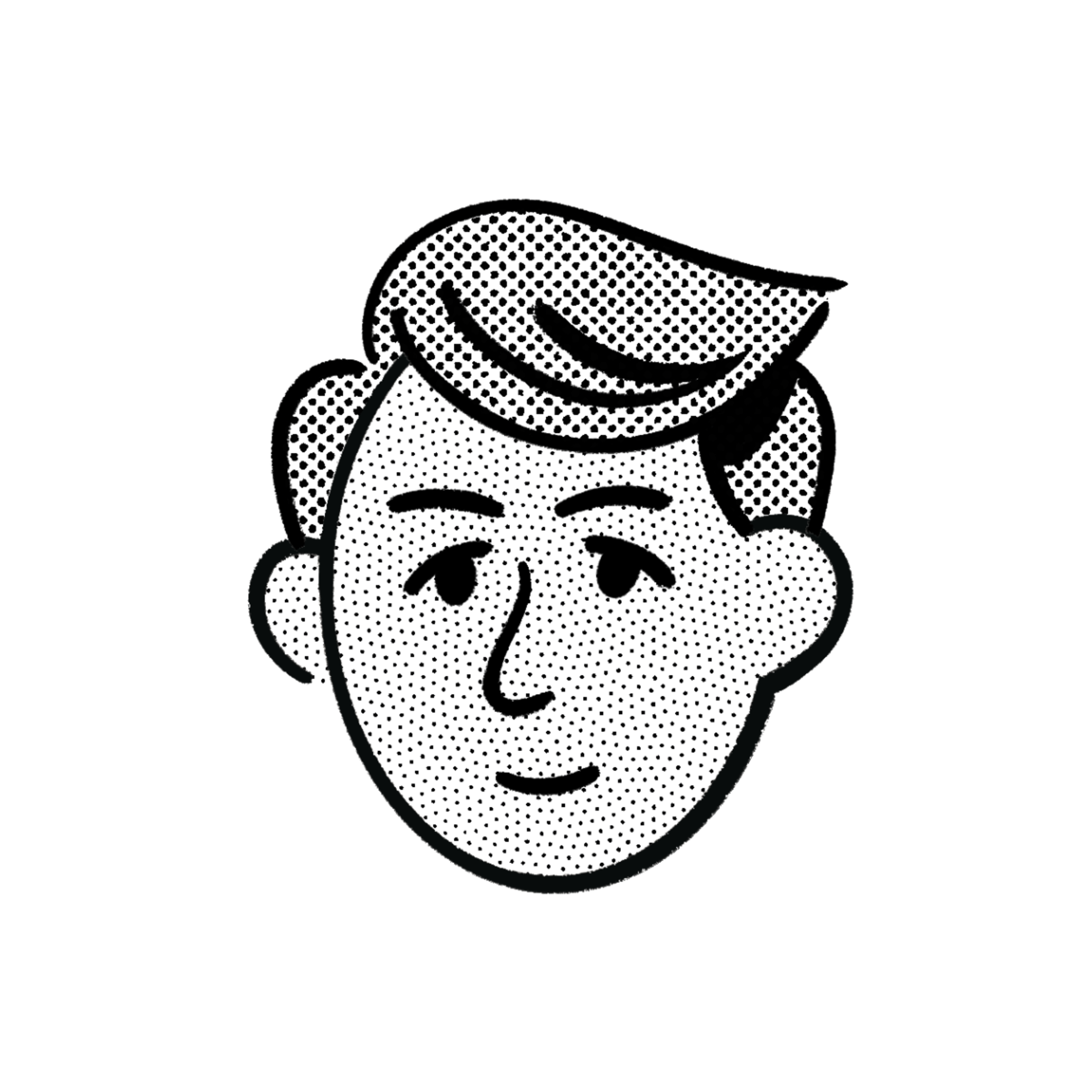
自分がベンチャー企業に入社を決めた理由をお伝えします。
人によって、会社に何を求めるかは違うと思いますが、企業選びをするときの切り口の参考になればうれしいです。
①規模の大きさよりも業務の幅広さ重視
大企業はベンチャー企業と比べて、取り扱うお金の規模が大きいと思います。
しかし、規模が大きい分、実際の業務は細分化されています。
例えば、営業であれば、お客様への提案をするのは先輩で、先輩が話すための資料作成をする。または、資料をつくるための情報を集めるのが仕事。といったような形で実際に自分がお客様に提案するまでには数年かかる可能性もあります。
自分は、いくら大きな規模の案件に携われていても、自分ができる業務の幅が狭いと、自立することができないと感じてしまうタイプなので、案件の規模は大企業と比べると小さいかもしれないけれど、一連の流れに早く携われて、オーナーシップをもって進められる立場になった方が仕事が楽しいだろうと思いました。
実際、自分は大学生の頃にイベントを企画して、周りを巻き込んで何かを実行するのが好きだったことや、高校の頃には生徒会に所属して、体育祭や文化祭の運営側として物事に携わる方が好きだったことから、割り振られた仕事をするよりも、自ら仕事を作り出して、周囲を巻き込んでいく立場の方がイキイキとしているなと感じていました。
②給料よりもスキルアップ重視
若いうちから大手企業で高い給料をもらうのもいいですが、自分はスキルを身に着けることで、どこへ行っても活躍できる人材になりたいという気持ちが強かったです。現在は新卒で入社した会社で一生働き続けるという考えも以前と比べると変わってきているかと思うので、転職した際や副業をした際にどこでも活躍できる人材になった方が自由なキャリアを歩めると考えていました。
また、自分の場合は彼女と同棲をする予定だったこともあり、1人暮らしに比べると、お金も多少余裕があるだろうと思っていた部分もあり、給料がこれだけないと生きていけなくなるという不安に駆られることもなかったというのは大きなポイントだと思います。給料を意識する人は多いと思いますが、贅沢をしたいとかでなければ、給与水準が低い業界などを除いて、問題なく暮らしていけるのではないかと思います。ベンチャー企業のリアルな給料についても、別の記事でお伝えできればと思います。
③会社名よりもビジョン・サービス共感重視
大手企業で勤めると、経歴書に箔がつくと言いますが、大事なのは実際に業務で何ができるか、成果が出せるかだと思います。そのため、自分は箔のために仕事をするのではなく、社会に対してどんな価値を提供できるのか、提供しようとしているのかを重視して働くことによって、自分自身の仕事のやりがいやスキルアップにもつながるだろうと考えました。
2. 新卒でベンチャー企業に入社をして良かったと思うこと
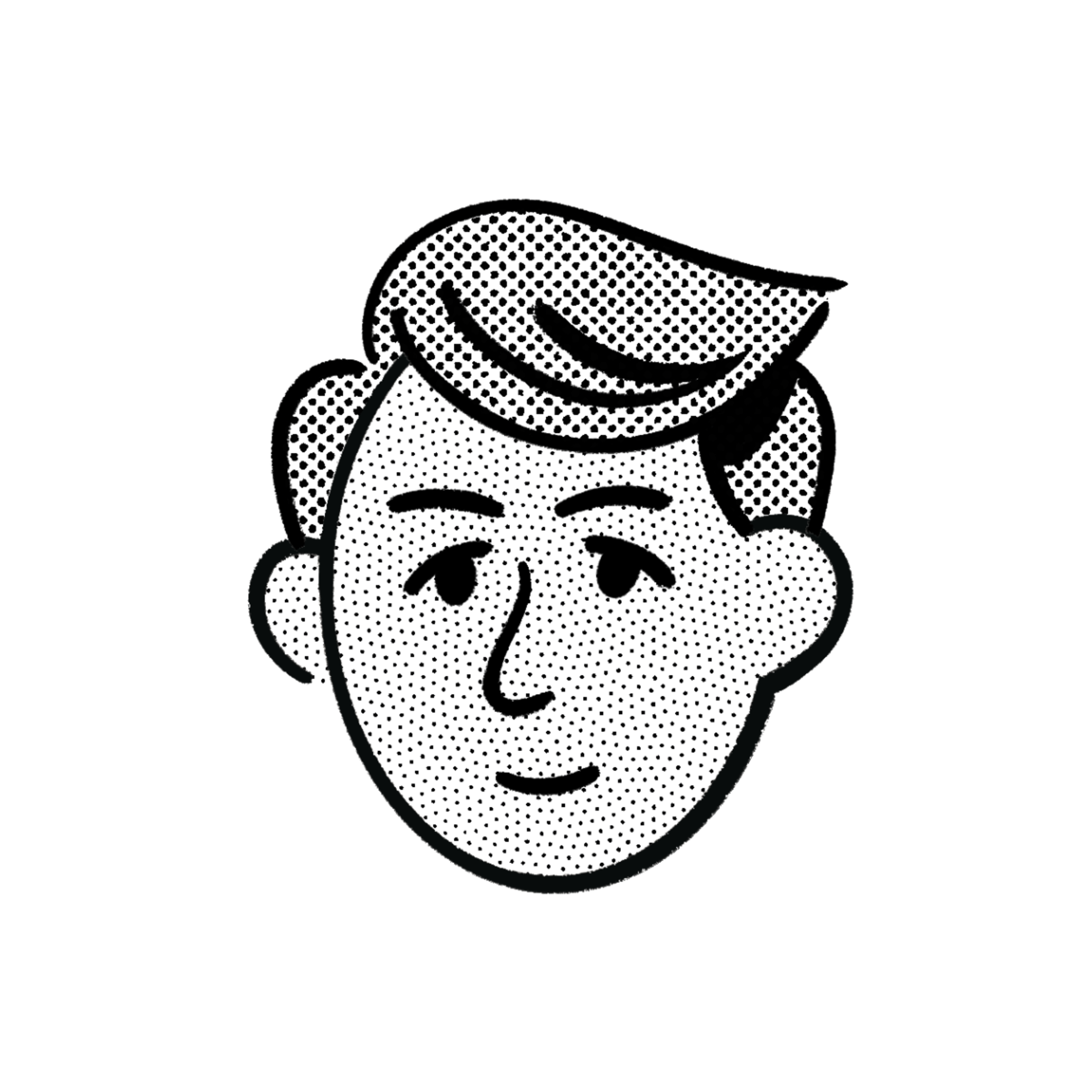
新卒でベンチャー企業に入社をして、執筆時点でも勤務を継続しています。
何度か転職を考えたことはありますが、考えるたびに「この会社でまだ成長できる可能性がある」と現職に残る選択をしてきました。
これからベンチャー企業に入社を考えている人は、1つの企業の例ですが、ベンチャー企業に入社するかどうかを判断する1つの材料になればうれしいです。
①幅広くさまざまな業務を経験できる
ベンチャー企業は人手も少ないため、やろうと思えばやれる仕事はたくさんあります。
そのため、積極的に手を挙げて、様々な業務に取り組むことで、何かチャンスがあったときに、「この人に任せよう」と思ってもらいやすくなります。
実際、自分の場合は、新卒で入社して営業をやっていましたが、営業の傍ら、全社イベントの責任者や部署横断のプロジェクトの推進など積極的に社内プロジェクトに取り組んでいたため、社長から新サービスの営業立ち上げに抜擢していただくことができました。そこで、営業以外にもマーケティング的な視点を学んだり、そもそもサービスを立ち上げるとはどういうことなのかを勉強していくことで、新規事業の立ち上げの社内公募ポジションに応募した際にも、スムーズに受け入れてもらえました。そして今では、新規事業のサービス責任者とアライアンスを行っています。
このように、営業だけでなく、サービスの立ち上げからアライアンスまで幅広く業務に携わることで、広い視野を持って仕事をすることができるようになったと感じています。おそらく大手企業に入社していたら、同じ年齢でここまで多くのことを経験することはできなかっただろうと思います。
②変化のスピードが早く飽きにくい
現在は市場の変化が激しいこともあり、社内の方針や体制も大きく変化することがあります。大手企業の場合には、数ヶ月で意思決定をするのは大変だと思いますが、ベンチャー企業の場合は、当月の中旬に来月からやることが変わるなどと伝えられ、実際に異動になるケースもあります。
また、振り返ってみると、1年前と今では大きく施策や体制が異なります。特に不動産やデベロッパーのような業界では、10ないしは20年越しのプロジェクトを完遂したというのも、長く残るとても偉大な取り組みだと思いつつ、自分はそこまで我慢できずにもっと早く結果を求めてしまうなと感じました。
素早く結果を出すために、変化しながら新たな取り組みをしていくという働き方は、変化の激しい市場で生き残っていくために必須であるベンチャー企業ならではなのかもしれません。実際、創業から100年近く続いている会社では、これまで蓄積してきた資産があるため、変化しようと思ってもなかなか変化に踏み切ることができない・変化する文化にならないという話も聞いたことがあります。
③ワークライフバランスと成長の両立ができる
ベンチャー企業はハードワークで残業時間もとても多いイメージがあるかもしれませんが、そうでない会社もあります。自分自身、平均残業時間は20時間程度で、忙しくても30~40時間、入社したばかりのことは残業時間が10時間程度ということもありました。また、リモートワークも可能で出勤時間も自由など、柔軟な働き方ができる職場です。
そのため、妻が仕事で忙しそうなときには、自分が家事を多くすることで、お互いの生活に負担をかけることなく、生活をすることもできます。実際、妻が新卒1年目のときに、仕事が辛すぎて適応障害になってしまったときには、基本的にすべての家事を自分がやっていましたが、働き方の柔軟さがないと今頃どうなっていただろうかと思います。
しかし、仕事にコミットするときは、自分の仕事に加えて学んだり、情報収集をしたりすることで、自分自身の成長も実感しています。ベンチャー企業は一概にハードワークでワークライフバランスが保てないというのは、そういう企業が多いので情報が多いだけで、ワークライフバランスと成長を両立することができる会社もあるので、いろんな企業を見ていただくのが良いと思います。
3. 新卒でベンチャー企業に入社をして後悔していること
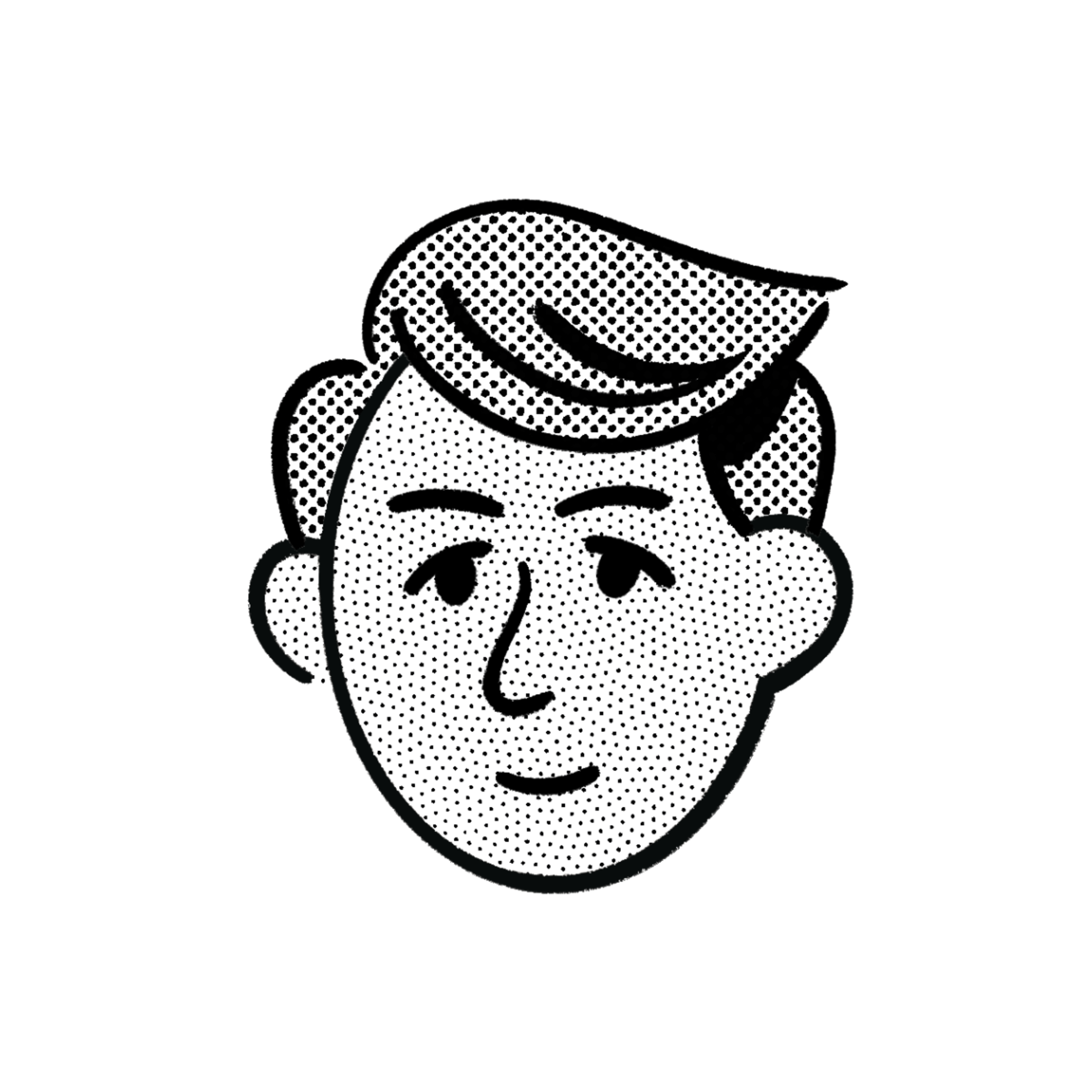
基本的に、後悔していることはないです!
しいて挙げるとするのであれば、この2つかなと思ってお伝えしますが、どちらも自分自身の考え方1つで解決できるものなので、転職に至るほど大きな要因になるとは思っていません。
ベンチャー企業の実態を知るという意味では参考になると思いますので、ぜひ見てみてください。
①会社として必要な機能が不足している
大手企業ほど、人員が潤沢ではないため、限られた人数で必要な仕事をしていくのがベンチャー企業です。
また、モチベーションの高い人や仕事ができる人がお互いに必要な業務をカバーしながら業務を進めている場合においては、その人達が忙しくなった時に、必要な業務を誰も担っていない状態になることがあります。
実際に、自分の勤める企業では、営業力でなんとか製品を売ってきたため、営業がお客様から求められた機能を開発部門に作ってもらう体制になっており、製品の目指す方向性や製品企画をする人がいなくても、何とかなってきたが、それだけでは厳しい状態になった際に、製品企画力が弱いため、次に繋がる一手が打ちにくい状態になっています。
大手企業でも、これまでの会社の経験などから、強み弱みがあるかと思いますが、人が多い分必要な機能が揃っている可能性が高いのではないかなと思っています。
②学ぶ機会は自ら作らなくてはいけない
ベンチャー企業は、教育体制が整っていないケースが多いと思います。そのため、この会社で学ぶことができないと感じたのであれば、社外に出て学ぶ必要があります。社内にロールモデルがいない場合は、社外で探すというのは、面倒に感じてしまうかもしれません。実際に大手企業であれば、10年後の自分、20年後の自分を重ねることができるような人が社内にいる可能性があります。
4. ベンチャー企業ってどう探したらいい?おすすめの探し方
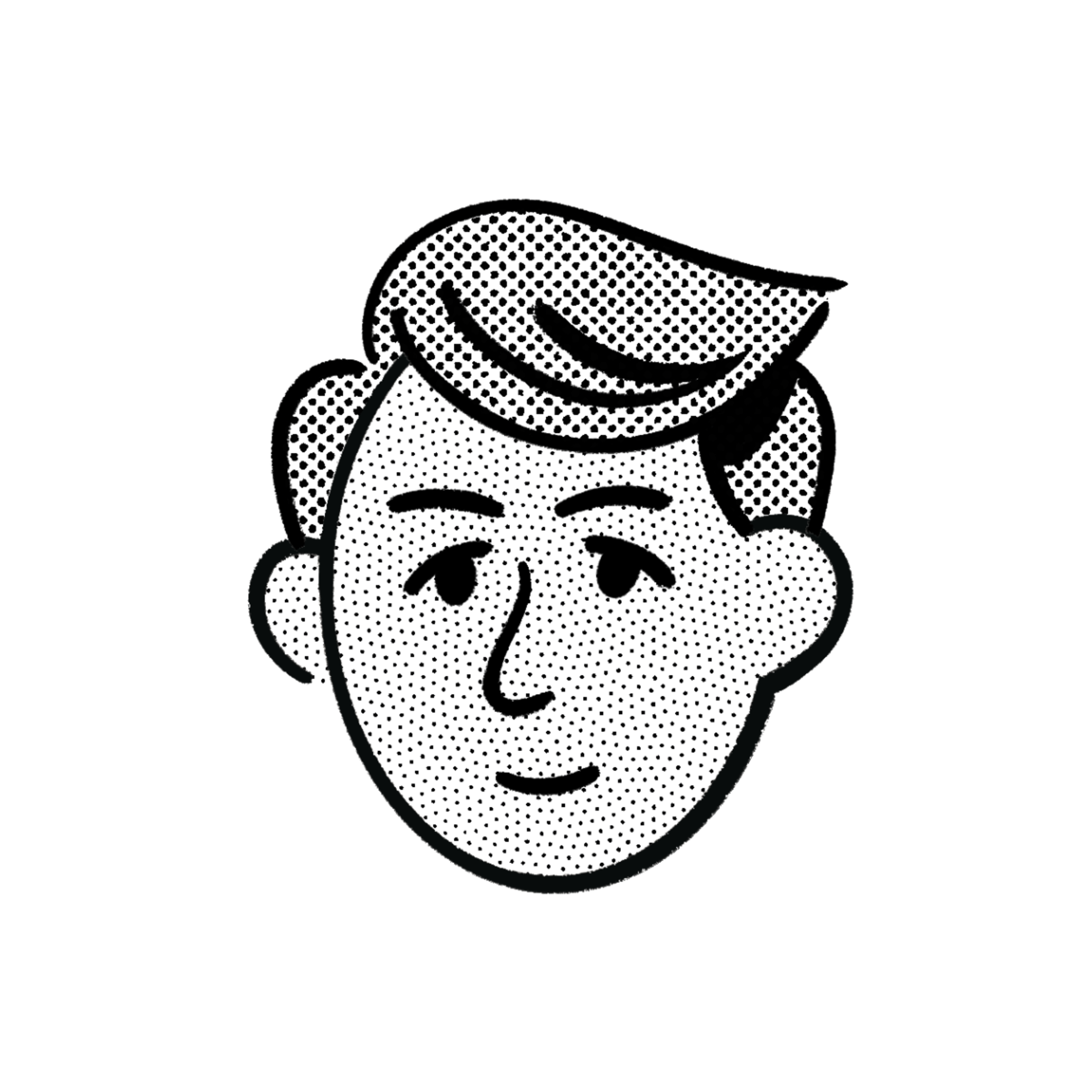
大手企業は聞いたことがある名前が多いと思うので、求人も目につきやすいと思いますが、
ベンチャー企業は名前を知らない会社がとても多くあります。正直全部を把握するのは無理だと思います。
そのため、ベンチャー企業は効率良く多くの企業と出会い、「ここだ!」と思える会社を見つけることが重要となります。その方法についてご紹介していきますね。
①スカウトサービスに登録する
スカウトサービスは企業から、自分たち求職者に対して、スカウトを送ることができるサービスです。
自分から1社1社企業を探しに行くよりも、企業側から声をかけてもらえるので、効率的に企業との出会いを作ることができます。スカウトサービスに登録するときは、ただ登録だけするのではなく、自分のプロフィールをしっかりと入力することで、「この人を採用したい!」と思ってもらえるようにするのがポイントです。
自分が使っていたサービスや知っているサービスをご紹介しますので、ご参考にしてみてください。

OfferBox:https://offerbox.jp

Wantedly:https://www.wantedly.com/

キャリアチケットスカウト:https://media.careerticket.jp/
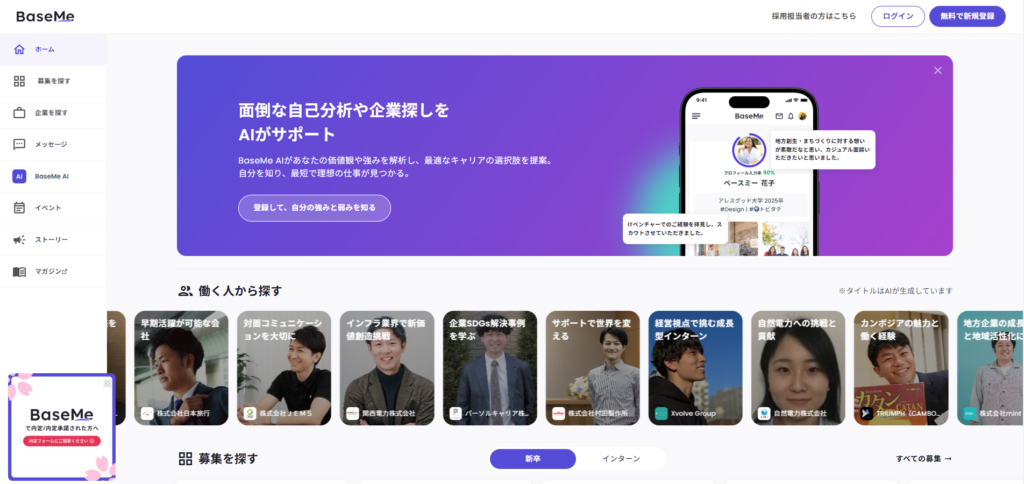
BaseMe:https://baseme.app/
②就活イベントや合同説明会に参加する
1回の参加で多くの企業と出会える就活イベントや合同説明会もおススメです。
興味のある企業を見つけるだけでなく、興味のない企業はなぜ興味がないと感じたのかを書いて残しておくと、自分の中で価値観の整理をするときに役立つので、すべての企業で自分がどう感じたのかをメモするようにすると良いでしょう。
さまざまなイベントが開催されていますが、自分が就職した企業を見つけるきっかけとなったイベントをご紹介します。

ジョブトラ:https://realive.co.jp/service/job-tryout

エンカレッジ:https://app.en-courage.com/?locale=ja
③相性の良いエージェントを見つける
自分と相性の良いエージェントを見つけることも、自分に合った企業を探すためにはとても重要です。
多くのエージェントと面談をして、忙しくなってしまうかもしれませんが、色んなエージェントと話すことで、「この人は自分のことを良く理解してくれているな」「この人にならもっと深く相談できそうだな」と信頼できるパートナーとしてのエージェントが分かってきます。すぐに企業を紹介してきたり、面談をさせようとしてきたりするエージェントは、自分たちの成果にしようとただ紹介しているだけかもしれないので、注意が必要です。
自分が使って良かったと思うエージェントを紹介します。
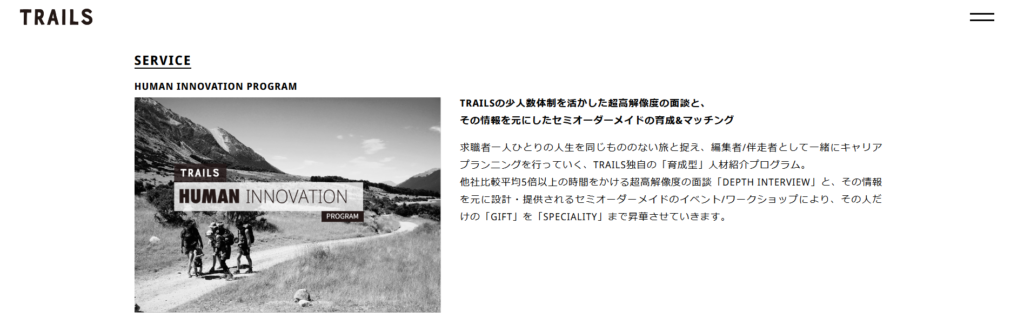
TRAILS:https://trails.co.jp/human/ ※自分のときは招待制でした

intee:https://intee.jp/student/
5. 最後に
新卒でベンチャーに入社して良かったことと後悔していることをまとめると
- 良かったことは、以下のような点です
- 幅広くさまざまな業務を経験できる
- 変化のスピードが早く飽きにくい
- ワークライフバランスと成長の両立ができる
- 後悔したことは基本はないですが、しいて挙げるのであれば以下のような点です
- 会社として必要な機能が不足している
- 学ぶ機会は自ら作らなくてはいけない
となります。
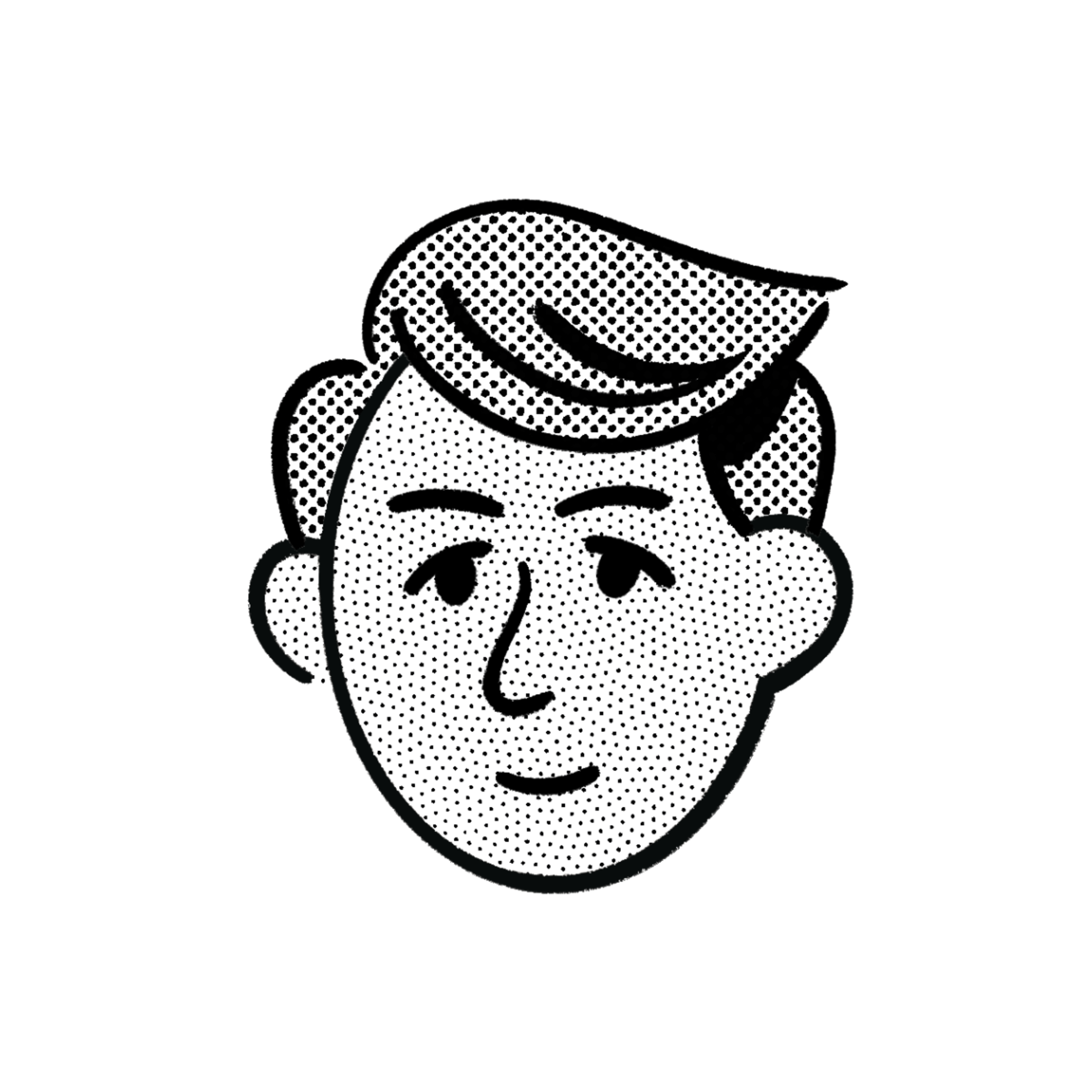
新しい物事にチャレンジするのは、誰だって勇気がいることです。
自分の実体験が、少しでも皆さんの心を軽くしたり、背中をそっと押すものになることができたら嬉しいです。
このサイトでは、後輩を応援したいという気持ちで、これからもさまざまな記事を執筆していきますので、ぜひご覧ください。
 わたしたちについて
わたしたちについて
またこのブログでは、他にもキャリアについて記事を執筆していますので、ぜひ併せてご覧ください。