この記事では、
- 「教育でビジネスをするってどうなの?」と感じている就活生
- 「教育業界のベンチャー企業に転職を考えているため、そこで働く人の声を知りたい」という社会人
という方に向けて、
- 実際に私が教育業界のベンチャー企業に勤めて感じた、「教育×ビジネス」へのモヤモヤ感
について、自分も同じように不安になったり挫折した経験を踏まえ、実体験ベースでお伝えします。

まるで1個上の先輩とサシ飲みに行ったかのように、「有益な情報が得られた」「心が少し軽くなった」「また明日から頑張ろう」、そんな気持ちになっていただけたら嬉しいです。
1. 私が勤めている会社・携わっている事業の前提

一口に「教育ビジネスが難しい」といっても、
「なぜ教育ビジネスに携わりたいと思うようになったのか」
「どんな事業に携わっているのか」
「会社の規模は」
などによって話が変わってくると考えています。
そこで以下では、まず私が勤めている会社、携わっている事業の前提についてお伝えいたします。
私の経歴の前提
- 中学生の頃から教師になりたいと思うようになり始め、大学では教育学部に入学
- しかし自分は教員に向いている性格ではないと思い始め、就活に切り替え。
- 教職を最後まで取り切る予定だったので、教育実習との両立ができるよう、早期内定を出してくれるベンチャーを狙って就活。
- 就活に切り替えたとしても、興味関心は「教育・人材業界」にあることに変わりはなく、
最終的に、大学3年の1月に内定を出してくれた今の「教育ベンチャー」の会社に入社を決めて就活終了。 - 現在も、今の会社を辞めることなく勤め続けている
(※私が「教師になりたい」と思った理由、および「教師は辞めよう」と思うに至った理由については、以下記事に別でまとめているため、ぜひ併せてご覧ください。)
私が「『教育×ビジネス』でどんなことを行いたいと考えていたか」については、就活時に企業に提出していた当時の文章がそのままPCに残っていたため、そちらをご紹介いたします。
私の志は、「子どもたちが、自己肯定感をもって自分の道を歩み社会・世界に貢献する人材となるよう、子供たちの学習環境を整える」というものです。
教育は、個人の自己実現と、社会の発展のために行われるものです。しかし現状日本では効率よく社会を発展させることの方が重視されており、そのような中で学校教育が行われた結果、成績不振・人間関係などで自己肯定感を失ってしまう子どもたちや、与えられたことをただこなすように洗脳され、個性を失ってしまう子どもたちが多く出てきてしまい、大きな社会課題になっていると私は思います。
そこで私は、子供たちの学習環境を整えることでこの課題を解決させたいと考えています。具体的には、受け身ではなく主体的に学習に向かうことができるような学習プログラムを作る、教師・親など大人への教育を行う、教育機関から零れ落ちた子供を救い上げる機関を作る、などを今は考えています。
このようにして、自分の志をしっかり持ったうえで、社会・世界を発展させていくような人材を世の中に輩出していきたいと考えています。
会社の規模
私が勤めている会社は、社員数100名未満のベンチャー企業です。
つまり、大手のように資金力に余裕がないため、「稼げない事業だけど慈善活動的に行う」ということはできない立場にあります。
行っている事業
身バレを防ぎたく、かなり粗い紹介になってしまうのですが、私の会社では主に以下2つの事業を行っています。
- 小中高校生向けの教育ビジネス(toC)
- 学校向けの教材・イベント販売等(toB)
なお私が在籍しているのは「小中高生向けの教育ビジネス」を行っている部署の方になります。
(※私が新卒で入社してから、具体的にどんな仕事を行っていたかについては、以下記事に別でまとめています。ぜひ併せてご覧ください。)
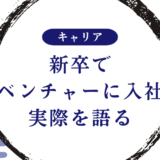 新卒ベンチャー入社の実際を語る|仕事内容・メリット・デメリット
新卒ベンチャー入社の実際を語る|仕事内容・メリット・デメリット
また私の会社では、社会人向けの資格ビジネスなどは行っていません。
そのため今回の話では、そういった社会人向け教育サービスについて触れることはないため、ご認識ください。
2. 実際に教育ベンチャーに入って感じた「教育×ビジネス」の難しさ・モヤモヤ感

以上の前提をもとに、ここからは私が新卒で「教育ベンチャー」に入社して感じた「教育×ビジネス」の難しさ、モヤモヤ感についてご紹介いたします。
①教育コンテンツの質は最低限。力を入れるのはマーケティング・営業の部分
- 教材制作など、プロダクトの作成にはそれなりの工数を要する。
- 「こうしたら絶対に志望校に合格する」「こう教育したら絶対に良い人間に育つ」というメソッドはそもそもこの世に存在しない。
そもそも「良い教育」というものを定義するのは難しいことです。
受験に受かったからといって、必ずしもその経験が人生の「成功」に繋がるわけではありません。
例えばよくあるわかりやすい事例で言えば、以下のようなものが考えられると思います。
- 過激な受験競争に晒された結果、友人などに向かって平気で「こんな問題も解けないなんてバカだな」などの暴言を吐くような人間になってしまった
- 知識を直前に詰め込むだけ詰め込んで、受験が終わった後は一気にそれらを全て忘れていく。そこで学んだ内容に意味はあったのか
- 第一志望の難関大に合格したものの、そこで何を学ぶのかの意思はなにもなかったために、大学の授業についていけなくなった。
これらは果たして「成功」と言えるものなのでしょうか。
しかし教育に携わる人間として、そんなことを時間をかけて真剣に考えようとしても、結局生徒・保護者が私たち企業に求めるのは「合格」のみになります。
しかもその「合格」についても、「こうしたら必ず合格する」というメソッドが存在するわけでもありません。
合格というのは
- 本人が、今の学力に対して、どれだけのレベルの学校を志望しているか
- ここからどれだけ勉強に割ける時間があるか
- 本人がどれだけ努力する意志を持っているか
- その学校の倍率
- 当日の本人のコンディション・試験内容
などさまざまな要素が複合的に絡まって、合格不合格が出ます。
企業側では、合格の「可能性」を限りなく上げることはできても、「必ず合格させる」ということは保証できないものです。
変化の激しい時代の中で、ベンチャー企業は生き残りをかけて、スピード感持って尖ったことをして売上を上げなければいけない立場にあります。
時間をかけて「良い教育とは何か」「合格可能性を限りなく上げることができる素晴らしい受験プログラムとはどういうものか」などを定義し、教材・アプリ・動画とかそういうプロダクトを丁寧に作ったとしても、
- ヤマが外れて売れなかった
- 売るタイミングが遅く、競合に先を越されてしまい、売れなかった
となってしまっては、一瞬で会社が潰れてしまいます。
ベンチャー企業にはそのような失敗を許容できるような資金的な余裕はないのです。
上記のような「良い教育とは何か」「合格可能性を限りなく上げることができる素晴らしい受験プログラムとはどういうものか」などを真面目に定義することに時間を使うよりも、
最低限の質のプロダクトのものを、さも「最高級の教育が受けられる」かのようにセールストークで盛りに盛ってプロモーションを行い、生徒数を増やす方が会社としては手っ取り早く利益を上げることができます。
例えば私が会社で実際に指示された内容としては
- まずは試しにLP(ランディングページ)を作ってリスティング広告を流して、申し込みが数件きて需要があるってわかったら、そこから適当に教材を作って。
- 教材の質は1日・2日でできる最低限のものでいいから。
- 外注すると費用がかかっちゃうから、外注はせずあなたが自分で適当につくるようにしてね。
というものでした。
一応私の会社にも、体裁上申し訳程度に「教務チーム」というのが存在していますが、実態は「入会面談でいかにそれっぽいことを話し入会率を上げるか」がミッションになっている、つまり「営業」部隊のような形になっています。
基本的に受験産業の場合、毎年お客様が入れ替わります。
例えばBtoBだと、その業界に存在する会社というのが毎年コロコロ入れ替わることはないと思います。しかし教育業界の場合、毎年受験生は入れ替わっていきます。
今年の生徒・保護者にどれだけ文句を言われようとも、その人たちは1年経つと卒業していき、また新しい受験生が市場に登場します。
そのため、「お客様を丁寧に扱おう」「丁寧に扱わなければ市場から排除されてしまう」という気持ちが、受験業界では薄いように感じます。
②できない生徒に非現実的な「夢」を売ることで売上を上げようとする
これは教育ビジネスに携わっている人ではなくても、塾に通っていた自分の実体験などから、「受験産業の闇」としてうっすら把握している方も多いのではないでしょうか。
基本的に塾というのは、「頭のいい2割の生徒」が合格実績を作っていて、残りの「8割」の生徒はその塾の売上に貢献しているだけ、という状態です。
塾は基本的に、もとから頭が良い人に、一瞬だけその塾の短期講座を無料で受けてもらい、それを「うちの塾に通っていた生徒がこんな合格実績を出しました」の材料にし、
肝心の塾の売上となる部分については、できない生徒にどんどん講座を追加で売りまくり稼いでいく、という仕組みになっています。
実際私の会社では
- 「努力をしないくせに高望みをしていて、家にはある程度お金がある」、そういう生徒が一番のカモだよね〜そこをガッツリ狙いたいよね〜
という会話が普通に行われています。
また、その時のセールストークで使われる文言がまた「一発逆転合格」とか「偏差値〇〇からの難関校合格」とかそういうもので、都合の良い「夢」を見させようとするものなんですよね。
私は基本的に、人生に「一発逆転」といったものはないと思っています。
難関校に合格するのは、最初から真面目にコツコツ勉強をし続けていた生徒です。
直前になって焦って、それっぽいノウハウにしがみつき一発逆転を狙って楽しようという人が合格するといったことは基本的にありません。
③教育ベンチャーが利益を出そうとすると、富裕層向けサービスにならざるを得ない
ベンチャー企業は、大手が狙わないようなニッチな市場で戦うしかありません。
【参考】
・コトラーの競争地位戦略 | 用語解説 | 野村総合研究所(NRI)
そのため、市場に存在する顧客の母数が少なく、なるべく高単価にしないと利益が出なくなります。
実際私の会社では、事業計画に明確に「富裕層をターゲットにする」と書かれており、実際行われている事業も
- 富裕層向けプログラミング教育
- 中学受験ビジネス
といったものです。
日常の会話の中でも部長が
- 港区のタワマンとかに住んでる富裕層何人かに、このプログラミング講座を買わせればそれである程度ビジネスが成り立つから、別にそれでよくね
といったことを平気で言っている状況です。
また、違う部署では学校へのキャリア教育教材の販売なども行っていますが、これも営業をかけるのは私立の学校がほとんどです。
「まず私立で導入実績を作って、そこからゆくゆくは公立にも」と上辺では言っていますが、名前の知られていない小さなベンチャー企業が私立で数校導入実績を作るだけでも大変なことなのに、
公立学校にも普及させていくなんて、何十年先の話になるのやら、というのが実情になります。
④教育ベンチャーで働き続ける社員に、真に「教育を変えたい」という社員はなかなかいない
「今の日本の教育を変えたい」という意志を持って教育業界に入ってくる人(特にまだ擦れていない新卒に多いイメージ)には、「教育格差をなくしたい」のパターンが多いように思います。
しかしそれで実際に、何か先進的なことを行っていそうな尖ったベンチャー企業に入社してしまうと、実態としては逆に、富裕層向けサービスに従事することになり、教育格差を一時的に助長することになってしまいます。
実際私の会社でも、新しく入った社員からは、「富裕層向けではなく、自分のような中流階級向けに何か教育サービスを届けたい」という声がよく出がちです。
しかし部長からは一瞬で「そういうのは資金力のある大手にやらせておいて、自分たちは稼げるところを狙いにいけばいいから(笑)」と却下される光景が日常茶飯事です。
毎日・毎週のレベルで教育に関する諸問題のニュースは上がってきます。
そんな中、「まずは富裕層向けのサービスで実績を作って、そこから中流階級にも流すようにしよう」と上辺だけ言われても、そんな何十年先のスパンで考えられる人ってなかなかいないと思います。
結局、本当に教育のことを考える熱意ある人はどんどん会社を辞めていき、教育をビジネスの道具としてしか考えていないような人が会社に残り続けることになります。
ちなみに私の会社では、私が入社した数年後あたりから、採用サイトに明確に潔く「教育への想いを持つ人よりも、ビジネス思考が強い人の方が成長できるし評価されます」と書くようになりました。
私が入社する前にその文言を書いておいて欲しかったな、と正直思います。
3. 最後に
私が実際に教育ベンチャーに入って感じた「教育×ビジネス」へのモヤモヤ感をまとめると
となります。
今回の話は、もしかしたら私の会社だけに限られる話なのかもしれません。
(※なお私は今の会社に入社した後、激しめの入社後ギャップを感じて適応障害になっています。その時の体験談については以下に別でまとめているため、ぜひ併せてご覧ください。)
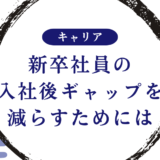 適応障害になった経験から考える、新卒の入社後ギャップの減らし方
適応障害になった経験から考える、新卒の入社後ギャップの減らし方
もしくは今回の話は「教育×ビジネス」に限られる話ではなく、「そもそもビジネスってそういうものでしょ」という話なのかもしれません。
しかしそれでも、私の経験談が皆さんの何かの参考になりましたら幸いです。

新しい物事にチャレンジするのは、誰だって勇気がいることです。
自分の実体験が、少しでも皆さんの心を軽くしたり、背中をそっと押すものになることができたら嬉しいです。
このサイトでは、後輩を応援したいという気持ちで、これからもさまざまな記事を執筆していきますので、ぜひご覧ください。
 わたしたちについて
わたしたちについて
またこのブログでは、他にもキャリアについて記事を執筆していますので、ぜひ併せてご覧ください。










