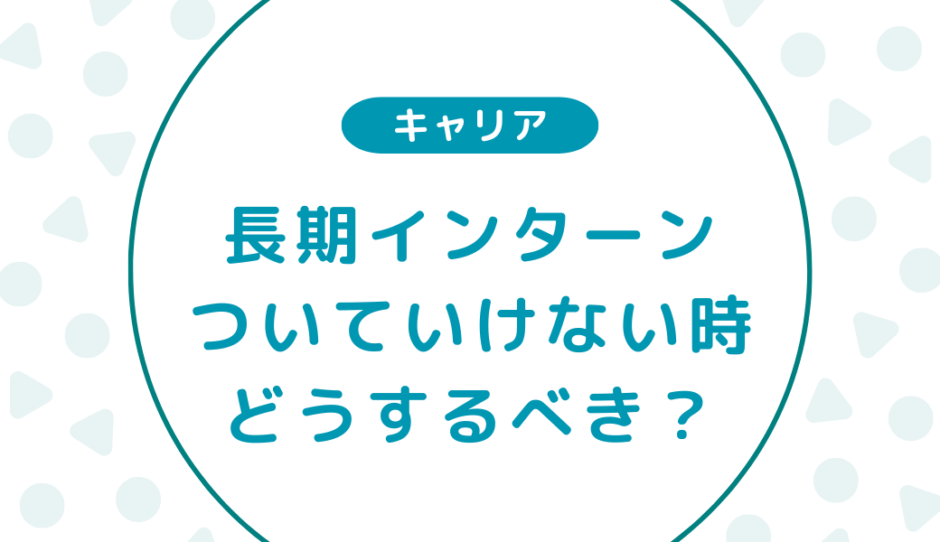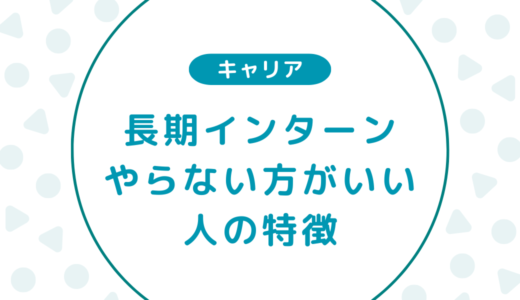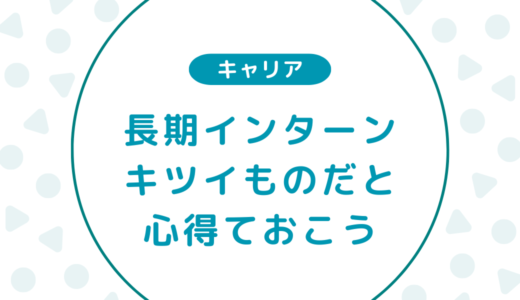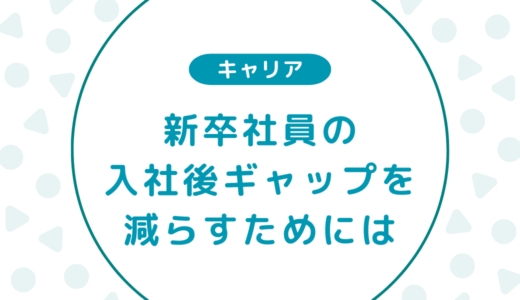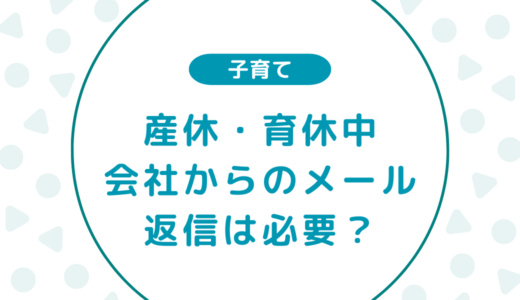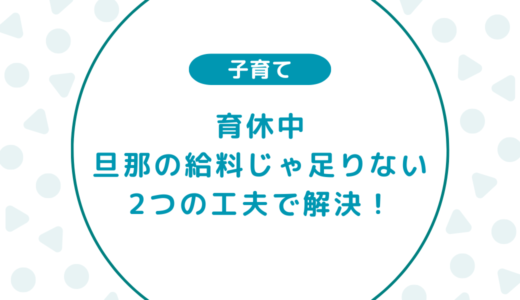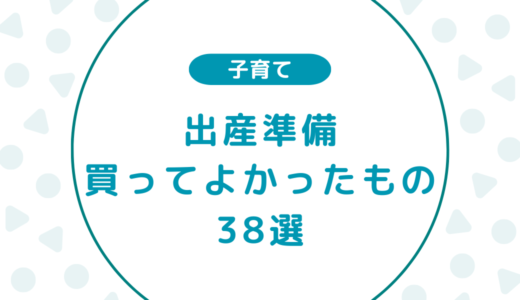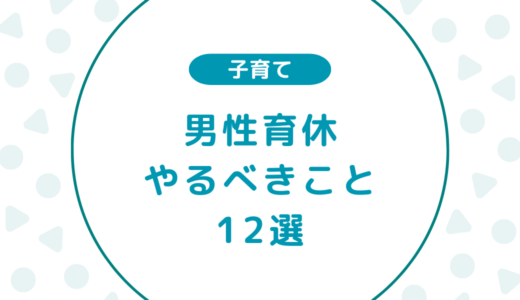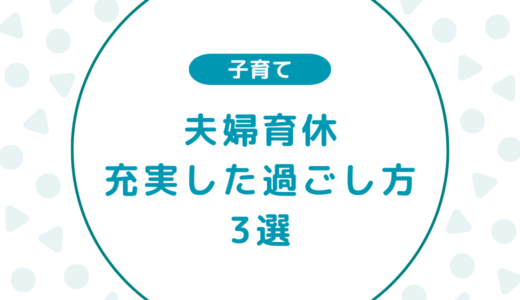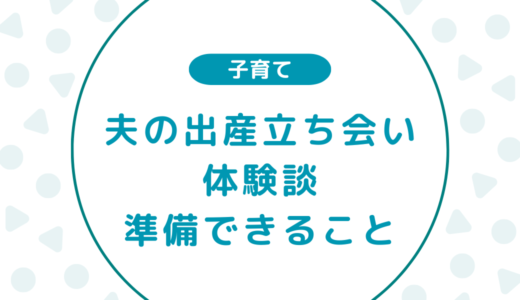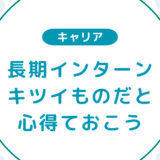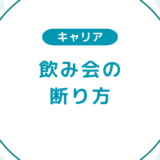この記事では、
- 「長期インターンで働いているが、ついていけなくてきつさを感じている」
- 「長期インターンについていけない時はどうしたらいいのか、とにかく誰かに意見をもらいたい」
という方に向けて、
- そもそも長期インターンに「ついていけない」と感じやすい理由について
- 長期インターンについていけないと感じた時の適切な対応方法
について、実体験ベースでお伝えします。

まるで1個上の先輩とサシ飲みに行ったかのように、「有益な情報が得られた」「心が少し軽くなった」「また明日から頑張ろう」、そんな気持ちになっていただけたら嬉しいです。
1. 前提:私の会社の特徴、私の長期インターン生マネジメント経験

私は「長期インターンをしていた大学生」側ではなく、「長期インターン生をマネジメントしていた担当社員」側の人間になります。
以下、私の勤めている会社、および私の長期インターン生のマネジメント経験の前提についてお伝えします。
(※私の勤めている会社、および私の長期インターン生のマネジメント経験の前提については、以下記事で別で詳しく記載しているため、ぜひ併せてご覧ください。)
私がマネジメントしていた長期インターン生の状況は、以下の通りです。
- 【長期インターン生に任せていた仕事】
・SEOライティング、SEO戦略・戦術の作成
・Webサイトの数値分析
・後輩のマネジメント - 【勤務条件】
・月50時間以上働くことが必須
・卒業まで働くことが必須
・フルリモート - 【私がマネジメントしていた長期インターン生の在籍大学】
・東大生・京大生・慶應生・東工大生・その他複数大学
以上の前提をもとに、以降では私のマネジメントの実体験をもとに「なぜ長期インターンはきついものであるのか」について、解説していきたいと思います。
2. 長期インターンについていけなくなるパターン①:業務内容・周りの人のレベルの高さについていけない

まず一番多いパターンが「業務内容・周りの人のレベルの高さについていけない」になります。
以下、どのような事象がよくみられるのかと、その対応方法について解説します。
「業務内容・周りの人のレベルが高くついていけない」という学生によく見られる事象
特に長期インターンを始めたての学生だと
- 業務内容がシンプルに難しく理解が追いつかない、成果を出すことができない
- 周りの優秀な先輩・社員とできない自分を比べてしまう
- 自分はもっとできると思っていた。理想と現実のギャップに自信を喪失してしまった
など「業務内容・周りの人のレベルが高くついていけない」と感じてしまう方は多く存在します。
そもそも長期インターンは「きつい」ものです。
(※なぜ長期インターンが「きつい」ものであるのかについては、以下記事で別にまとめているため、ぜひ併せてご覧ください。)
長期インターン生には、以下のようなレベルが求められることになります。
- 「大学生」としてではなく「一社会人」として扱われ、「一社会人」としてのスキル・ビジネスマナーを求められる。
- イメージとしては、数歳年上の社会人、例えば新卒2〜3年目レベルと同等レベルで成果を出すことが求められる
- アルバイトのように、ただ所定の時間分働いていればいいというわけではない。
「◯時間働きました」だけでは「だから何?契約通りの時間働くのは大前提だけど。」「その時間・時給を使ってどういう成果を出したのかを述べて」と言われてしまう。
昨日まで普通の大学生だった人が、いきなり「一社会人」として扱われ出すため、そのギャップに「ついていけない」と感じてしまうのも無理ありません。
対応方法
個人的には、上記の状態は「みんなが通る道」だと考えています。
最初はいきなりなんでも完璧にできる人なんてこの世に存在しません。ですので
- 一人前になるまでには数ヶ月・数年の時間を要する、ということを受け入れる
- できない自分を素直に受け入れる
- みんなこの道を通っているんだ、ここから這い上がっていくんだ、と踏ん張る
というマインドを持つことが第一に必要だと考えています。
そのマインドセットができたら、次に
- ①具体的に業務の中のどの部分で躓いているのか分解する
- ②躓いているポイントがわかったら、そこを一つずつ潰していく
というのを行っていきましょう。
- 【例:Webライティングの業務なら】
- セールスライティングについて学ばなければいけないことが多く、途方に暮れているのか
- 自分の考えを言語化し、構成・文字に起こすことに躓いているのか
- HTML・CSSのコードがわからず躓いているのか
- 【例:数値分析の業務なら】
- 各指標の意味がわからず躓いているのか
- 膨大な数字のうち、まずどこの数字から見ればいいのかわからず躓いているのか
- この数値が示す意味について、仮説が全く思い浮かばないのか
上記のように、業務の中のどこで躓いているのかを整理するようにしましょう。
その際「何がわからないのかわからない」という状態になることも非常に多いと思います。
その際は、先輩や社員に積極的に1on1を申し込み、
- そもそも業務の全体像はどうなっているのか
- それらのうち、周りの先輩・社員からみて自分はどこで躓いているように見えるか
などを積極的に聞き出すのが良いでしょう。
また「周りの優秀な先輩・社員との差に圧倒されている」のであれば、その先輩・社員と今の自分で何が違うのかを全て洗い出す、ということを行ってみるのがおすすめです。
例えば
- 先輩・社員はこういうスキルを持っている
- 先輩はこういう責任感・裁量権ある仕事を振られている
- 先輩のミーティングでの喋り方がかっこいい
- 先輩は時間管理が完璧にできている
などが出てくるのではないでしょうか。
躓いているポイントがわかったら、あとはそれを一つずつクリアしていくだけです。
例えば
- セールスライティングについて学ばなければいけないことが多く、ただただ途方に暮れている
→毎日30分ずつセールスライティングについて勉強をし、1ヶ月でセールスライティングの分野についてマスターする - 先輩のミーティングでの喋り方がかっこよく、自分の辿々しい話し方とつい比べてしまう
→先輩の話している言葉を全て文字起こしし、「先輩はどのような順序・構成で自分の意見を述べているか」を勉強する。先輩が使っている言葉の中でわからない単語があれば即調べる。
など目標を設定してそれを愚直にこなしていく、などをするのが良いでしょう。
この際も、「躓いているポイントを解消するための適切な行動・方法がわからない」ということがよくあると思います。
その際はいつまでも自分1人で悩みを抱え込んでしまうのではなく、
- こういうところ・スキルで躓いている時って、どういうふうに解決するのがいいですか
- 今の自分が、先輩みたいに裁量権ある大きな仕事を任せてもらえるようになるためには、どういうスキルをつけてどういう行動をすればいいですか
と素直に周りの先輩・社員にアドバイスをもらうようにしましょう。
3. 長期インターンについていけなくなるパターン②:業務量の多さについていけない

続いてよく見られるパターンが「業務量の多さについていけない」になります。
以下、どのような事象がよくみられるのかと、その対応方法について解説します。
「業務量が多くついていけない」という学生によく見られる事象
- やる気は十分にあるが、長期インターンの他にもやりたいことがたくさんあり(学業・サークル・就活・留学等)、それらとの両立がうまくできず、
結果、成長スピードが他の人より遅くなってしまい、自分より後に入った後輩にも抜かされるようになり、ついていけなくなっている
長期インターンをしようというくらい意欲がある学生なので、やはり上記のように「なんでも全部全力で頑張りたい」という考えを持っている学生は一定数存在します。
しかし、基本的にビジネススキルというのは一朝一夕で身につくものではないため、スキルを身につけ成果を出すためには多くの時間を長期インターンに割く必要があります。
具体例として、例えば私の勤めている会社だと、長期インターンで成果を出していた学生は、1ヶ月の勤務時間が70〜80時間以上、多い人だと100時間を超えている、ということが多かったです。
それができなかった結果、「後から入ってきた後輩に抜かされた」「『あの人入社して数ヶ月・数年経っているのに全然だね』と周りからの視線が痛い」などで、
「ついていけない」と感じるようになる学生も一定数いました。
対応方法
自分の大学生生活の中で、何を一番頑張りたいのか優先順位をつけるようにしましょう。
時間は有限です。「全部全力で頑張りたい」は通用しないということを受け入れましょう。
その上で「長期インターンを頑張りたい」と決めたのであれば、他の活動の何か一つは潔く諦めるようにしましょう。
また「長期インターンは辞める」と決めたのであれば、担当の社員にその旨を伝えるようにしましょう。
その際は、いきなり飛ぶのではなく
- 長期インターンでは、〇〇のような貴重な経験をさせてもらい、自分も本当に成長できたと思う。
ただ、長期インターンよりも優先したいと思うことができた。実際今は長期インターンにあまり時間を割くことができていない。
このまま長期インターンを中途半端に続けても、メンバーに迷惑をかけてしまうため、ここで長期インターンを辞めさせてほしい。
など誠実にコミュニケーションを取ってから辞めるようにしましょう。
大抵の職場であれば、上記のようなコミュニケーションを取れば、問題なく辞めることができるはずです。
4. 長期インターンについていけなくなるパターン③:マネジメント社員側が悪い場合

個人的には、長期インターン生が「ついていけない」と感じてしまうパターンには、「マネジメント社員側が悪い場合」もあると考えています。
以下、どのような事象がよくみられるのかと、その対応方法について解説します。
「マネジメント社員側が悪い場合」によく見られる事象
例えば入社して即、以下のような状況に置かれた結果「ついていけない」と感じている場合は、それはあなたではなく「マネジメント社員側」が悪いパターンと言えます。
- いきなり「パニックゾーン」の仕事を振られる
- 必要最低限の研修・教育すら行われない
- OJT(On the Job Training)・メンターなどが一切つくことなく、完全に一人きりにさせられている
- 「ティーチング」なしにいきなり「コーチング」
- きつい物言いでフィードバックをされる。人格を否定される。
「最低限の研修・教育が行われない」「先輩がつくことなく、完全に一人きりにさせられている」「人格を否定される」などについては、
適切なマネジメント手法について知識がない方でも、「この上司・会社やばいんじゃないか」と察することがしやすいと思います。
ただ「パニックゾーンの仕事をいきなりふる」「いきなりコーチングから入る」などについては、パッと見「それっぽい」手法になるため
無垢な方だと、「仕事とはこういうものなんだ」「ついていけない自分がきっと悪いんだ」と自分を責める結果になってしまうのではないかと考えています。
まず以下では、「パニックゾーン」「ティーチングとコーチングの違い」について簡単に解説します。
基本的に、成長に関する環境は3つに分類されると言われています。
- 【コンフォートゾーン】
苦労や努力なしに簡単に達成できる水準のこと。そのため、成長は見込めない。 - 【ストレッチゾーン】
今の状態では背伸びしてやっと届くか届かないかの水準、つまり簡単には達成できない水準のこと。
背伸びして挑戦することになるので、目標に対して不安やストレスを感じる。そのため快適で居心地がいいというわけにはいかない。
しかし成長にはつながる。 - 【パニックゾーン】
不安やストレスを過度に感じるほどの水準。
パニックになってしまうほどに高い水準では、目標に向かった挑戦ができなくなってしまうので、成長は望めなくなる。
【参考】
・ストレッチゾーン?パニックゾーン? | 『日本の人事部』プロフェッショナルコラム
例えば
- 1ヶ月後までに新規事業を立ち上げて、◯億の売上を立てて。当然、事業計画を作成して社長にプレゼンして、予算承認を受けてからやるようにしてね。やり方はググったりして自分で調べて。
- 飛び込みで100社営業して、1週間後までに受注を◯社とってきて。営業資料は自分で1から作って。
など「明らかに知識・技能のない新人(しかも大学生)には無理だろ」という内容の業務を、「これが我が社の洗礼・登竜門だから」などと得意げに振ってくる上司・社員には注意してください。
普通、そんな仕事の振られた方をしたら、誰でもパニックに陥ります。
「そんな上司・社員、本当に存在するの?」と思うかもしれません。
が実際本当に、どこかの企業のドラマチックな創業ストーリーに感化でもされてしまっているのか、こういう無茶なことを新人にさせるのが「成長」のためになるとか信じてしまっている人がいるんですよね。
ちなみに私の職場の上司は、上記のパターンでした。実際私も新卒1年目で上記のような目に遭い、適応障害になりました。
(※私が適応障害になった経験については、以下記事で別にまとめているため、ぜひ併せてご覧ください。)
- 【ティーチング】
ティーチングは、教える側が持つ明確な答えを、受け手に対して教えることや与えることで、相手の成長を促進する。 - 【コーチング】
コーチングは、指導を受ける側にすでに答えがあるという考え方。
コーチは、受け手が自分の中にある答えを導きだせるように、対話や問いかけによってサポートする。
【参考】
・コーチングとティーチングの違いとは?それぞれの有効なケースや使い分け方を解説
基本はまず「ティーチング」で必要な情報を伝達し、仕事にある程度慣れてきたら、自分の仕事の仕方などについて「振り返らせる」という「コーチング」の手法を用い始める、というのが一般的なやり方です。
業務経験がまったくない新人に対して、「君はどうすればいいと思う?」などとコーチングの手法を用いて問いかけても、本人の中に蓄積されている業務経験がない状態では、問いに答えようがありません。
フィードバック入門 耳の痛いことを伝えて部下と職場を立て直す技術 (PHPビジネス新書)
それが
- 業務上必要なツールの使い方に関する質問にさえ、「どうやって使うと思います?まず考えてみてください(笑)」と考えさせようとしてくる
- 提出した資料について「これ自分では何点満点のつもりですか(笑)」「この資料のどこが悪いと思うかまず考えてみてください(笑)」と考えさせようとしてくる
などのように何を聞いても、某会社の有名セリフ「お前はどうしたい」の1点張りで、ティーチングは一切行わないという上司・社員には気をつけてください。
そんな状況が毎日続いたら、誰でも精神を病むのが普通です。
再度になりますが、実際私も新卒1年目の際、上記のような目に遭い、適応障害になりました。
「会社に新しく入ってきた新入社員を育成・マネジメントするのであればともかく、大学生の長期インターン生くらいであれば、そこらへんの新人社員にでもマネジメントを任せておけばいっか」と考えている会社は、結構多いと思っています。
特に、社員数が少ないベンチャー企業・スタートアップなんかだと、
少ない人数で膨大な仕事量を回しているため(だからこそ労働力として猫の手すら借りたい=長期インターン生を採用したい、となるのかもしれませんが)、
長期インターン生のマネジメントごときにそこまで工数をかけていられません。
実際私の会社では「新卒1年目(入社数日〜数ヶ月)がいきなり長期インターン生のマネジメントを任される」という光景は日常茶飯事でした。
そうなると、長期インターン生のマネジメントを任された新人社員は
- ただでさえ、自分が会社についていくための必要最低限の知識(ビジネスマナー、会社・部署特有のルール・やり方、営業・マーケティングなどの自分の職種に関する普遍的な知識)を身につけるのに精一杯なのに、加えて「マネジメント」について勉強をしている暇なんてまずない。
- 長期インターン生については、自分の仕事の片手間に、これまでの部活・サークル・アルバイトなどの経験をもとに、それっぽいやり方で指導をしておくだけになる
- マネジメントをステータスか何かと捉えてしまい、人として偉くなったと勘違いして天狗になってしまう
- マネジメントについて対して勉強しないままなんとなくで乗り切ってしまった結果「成功体験の誤学習」をしてしまう
といった状況になることが非常に多いです。
実際私の会社は、上記のような社員が非常に多くいる状態でした。
対応方法
では、長期インターンで入社した先が、運悪くそういった上司・会社であった場合、どのように対応するのが良いのでしょうか。
個人的には
- 上司に思い切って「こういうやり方でマネジメントされるのは辛いです」と直談判する
- それでも状況が変わらなければ、即逃げる
というのが良いと考えています。
まず思い切って、上司に「辛いです」と本音をぶつけてみましょう。
運がよければ、「このマネジメントの仕方は良くなかったんだな」と上司が学習をしてくれ、その後の行動を改めてくれることもあります。
が、「辛いです」と直談判しても状況が変わらなかった場合は、素直にその環境からは即逃げたほうが良いでしょう。
どうしようもない、救いようのない職場というのはこの世に存在します。
「心を病んで再起不能になり、その後数年間をパーにしてしまう」という取り返しのつかないことになる前に、そういった職場からはすぐに逃げるようにしてください。
間違っても、「できない自分が悪いんだ」と自分を責めてしまうことがないようにしてください。
5. 最後に
長期インターンについていけなくなる、よくあるパターンをまとめると
となります。

新しい物事にチャレンジするのは、誰だって勇気がいることです。
自分の実体験が、少しでも皆さんの心を軽くしたり、背中をそっと押すものになることができたら嬉しいです。
このサイトでは、後輩を応援したいという気持ちで、これからもさまざまな記事を執筆していきますので、ぜひご覧ください。
 わたしたちについて
わたしたちについて
またこのブログでは、他にもキャリア・長期インターンについて記事を執筆していますので、ぜひ併せてご覧ください。